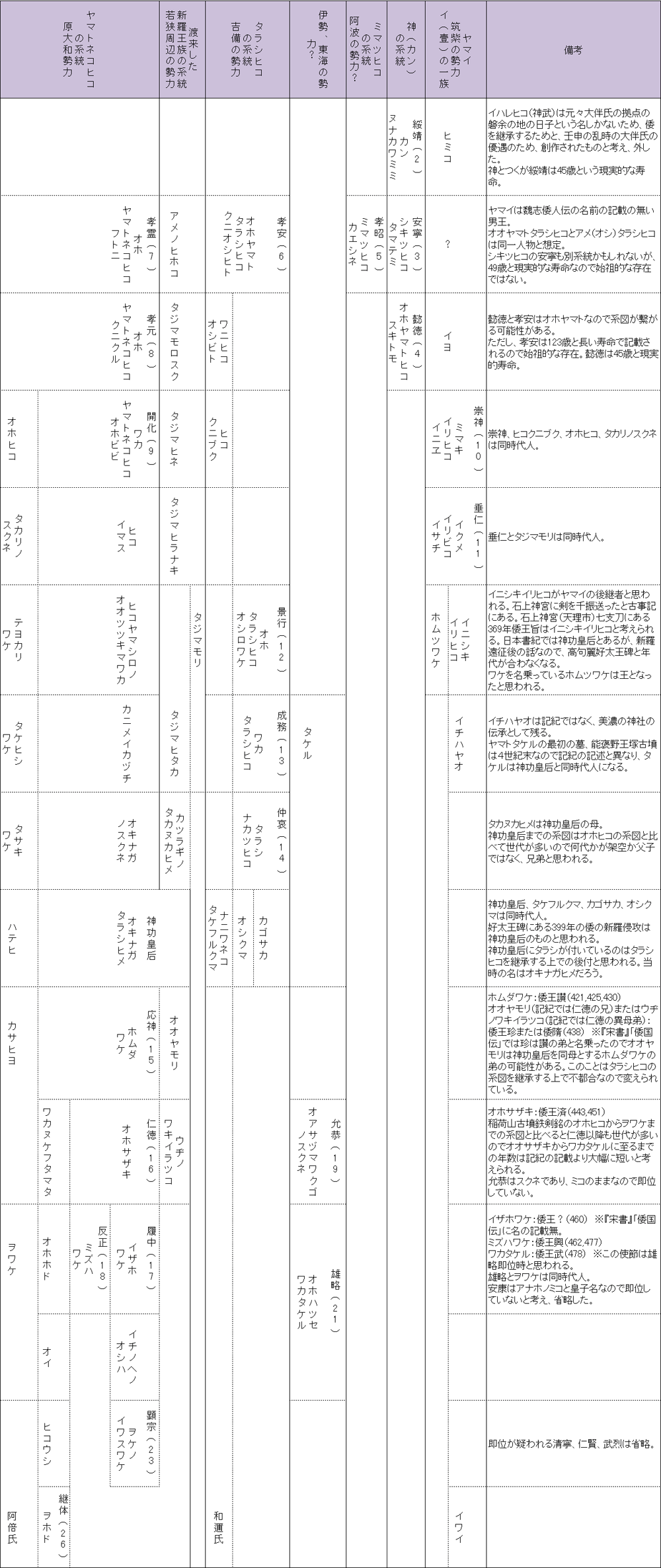邪馬壹 壹(イ)の一族
魏志倭人伝の邪馬壹国への行程を以下の通り、追ってみた。長い邪馬台国論争では、魏志倭人伝の行程の不正確さばかりが取り上げられたが、魏志倭人伝は実際の地図と比較しても、かなり正確な行程を記載していることがわかる。
 まず、九州説を否定する論者は周代に使われた短里(1里=76m)の採用を頑なに否定するが、確実な行程とされる帯方郡から一大国までの実行程を見ても、長里(1里=434m)はあり得ないことがわかる。三国志より前に書かれ、陳寿が行程を書く上で参考にしたと見られる漢書西域伝では長里で記載されている。陸上の計測においては宋代の『事物起原』によると黄帝の時代から車を転がすメーターのような記里車という計測機があったと記載されていたのでそれが使われていたと考えれる。ところが、海路が多い邪馬壹国の行程にはそれは使えない。『周髀算経』によると八尺の棒(周髀)の影を夏至の正午に陽城で計ると1尺6寸、千里南では1尺5寸、千里北では1尺7寸とある。この長さは6371km(地球の直径)✕((1.7(陽城北千里の影)/8(周髀))-(1.6(陽城の影)/8(周髀)))=80km=1000里となり、誤差はあるものの短里に近い数字となる。このように海路では日の高さから距離を求めたと推測出来る。『邪馬台国はなかった』(古田武彦 1971)では三国志全体が短里で書かれたとし、『かくも明快な魏志倭人伝』(木佐敬久 2016)ではエピソード記録は長里、実測値は短里で書かれたとしているが、魏志倭人伝は行程の距離は短里以外ありえない。
まず、九州説を否定する論者は周代に使われた短里(1里=76m)の採用を頑なに否定するが、確実な行程とされる帯方郡から一大国までの実行程を見ても、長里(1里=434m)はあり得ないことがわかる。三国志より前に書かれ、陳寿が行程を書く上で参考にしたと見られる漢書西域伝では長里で記載されている。陸上の計測においては宋代の『事物起原』によると黄帝の時代から車を転がすメーターのような記里車という計測機があったと記載されていたのでそれが使われていたと考えれる。ところが、海路が多い邪馬壹国の行程にはそれは使えない。『周髀算経』によると八尺の棒(周髀)の影を夏至の正午に陽城で計ると1尺6寸、千里南では1尺5寸、千里北では1尺7寸とある。この長さは6371km(地球の直径)✕((1.7(陽城北千里の影)/8(周髀))-(1.6(陽城の影)/8(周髀)))=80km=1000里となり、誤差はあるものの短里に近い数字となる。このように海路では日の高さから距離を求めたと推測出来る。『邪馬台国はなかった』(古田武彦 1971)では三国志全体が短里で書かれたとし、『かくも明快な魏志倭人伝』(木佐敬久 2016)ではエピソード記録は長里、実測値は短里で書かれたとしているが、魏志倭人伝は行程の距離は短里以外ありえない。
⑤の末廬国の行程では方角が書いていないため、末廬国=松浦を認めない場合、上陸地点について検討の余地はあるかもしれない。また、傍線行程を日程記載と考える⑨投馬国のみとするか、[動詞]+至を主線行程とし、至のみを傍線行程として⑦奴国も含めるかは、『かくも明快な魏志倭人伝』では前者を取り、『邪馬台国はなかった』は後者を取る。ここでは距離の記載方法よりも文法的解釈から後者で記載した。するとこの奴国は有明海西岸となり、1世紀に漢に使節派遣した奴国の位置、漢委奴国王金印が出土した志賀島とは距離があり、1世紀の奴国とは異なることになる。『後漢書』ではこの使節を倭奴国、つまり、倭の奴国と記載しているが、『後漢書』自体が南朝宋の政治家范曄が5世紀に書いたものなので、三国志が書かれた4世紀よりも後になる。金印の通り、奴国ではなく、委奴国だった可能性もある。こうなると糸島半島の勢力にも見えるが、主線行程にある伊都国も糸島半島から離れている。
従来の九州説、畿内説、古田武彦氏、木佐敬久氏もみな九州への上陸地点、末廬国を東松浦半島の東側、唐津としている。ただ、一大国から千余里という距離を考慮した場合、東松浦半島の西、伊万里あたりまで海路で来たと考えられる。また、奴国を傍線行程とし、伊都国の東南で2万戸を有するならば、そこから佐賀の有明海西岸から長崎南部半島一帯が奴国と考えるべきだ。
委奴国の委奴はイネの語源とも思われる。志賀島の田んぼの中から金印が出土したことも象徴的だ。ともかく、魏志倭人伝の奴国とは無関係で、稲の伝来した時代にまで遡る古い国だったのだろう。伊都国についてはその音から糸島半島に結び付けられてきた。従来の九州説も畿内説もそこに比定してきた。魏志倭人伝を正確に読み解いた古田武彦氏でさえ、末廬国のある松浦から東南ではなく、東北にある糸島半島を伊都国とする従来説を踏襲した。木佐敬久氏は伊都国の読みは漢音ではなく呉音で読み、イツ国としている。糸島半島にはこの時代に平原遺跡があり、邪馬台国にも比定される場所だ。それに対し伊都国は千余戸とあり、奴国(2万余戸)、投馬国(5万余戸)、邪馬壹国(7万余戸)と比較しても小さな国として記載される。大きな国があったことは間違いはないが伊都国ではない。主線行程とはやや離れた場所にあるため、傍線行程にも書かれなかったと考えられる。旁国二十一国の奴国かもしれない。
『後漢書』が記載する奴国は「倭國之極南界也」と記載され、つまり倭国の南端と記載される。金印が出土した志賀島または、糸島半島が奴国だとすると、倭国は九州よりも朝鮮半島が主体だったことになる。とすると『三国志』韓伝の「韓在帯方之南 東西以海為限南與倭接」つまり、韓は南で倭と地続きで接するという記載と一致する。また、『日本書紀』が記載する任那の前身とされる弁韓は三韓の一つで韓に属し、倭には入らない。ただし、長崎半島を奴国と考えれば、北部九州一帯が倭と考えることが出来るので、朝鮮半島よりも九州が主体だったことになる。金印は埋められる前に長く運用されたと考えられるため、出土地を奴国に指定するのも当てにならないかもしれない。(R03.12.27追記)水行20日と委奴国よりもよっぽど遠い投馬国(沖縄)が、わざわざ傍線行程として何故記載されるかは、魏を巡る当時の国際情勢を見る必要がある。そもそも魏が公孫氏を討伐し、邪馬壹国と接触した目的は、江南の呉がそれらの国と結び、包囲網を築こうとしたからだ。邪馬壹国よりも、呉に近い投馬国の行程を記載するのは軍事上最も重要なことだった。また、伊都国に帯方郡の使者が常駐しており、不弥国を通した交易の情報が重要かつ入りやすかったこともある。呉との関係を気にする必要のない九州北部沿岸や本州、四国はそもそも眼中に無かったのだ。それに対し、呉側の海に通じる有明海西岸の奴国、邪馬壹国南部の狗奴国の情勢もまた魏は注視していた。この対応を指揮したのは三国志最後の勝利者司馬懿だ。そういった目的を持つ邪馬壹国への行程の記述は不正確なはずがないのである。
日本に残る唐初に書かれた『翰苑』には晋代に書かれた『広志』の逸文が残る。伊都国、邪馬臺国(原文では『邪馬嘉国』)と続く行程に続く国として斯馬国、已百支国、伊邪国、伊邪久国が記載される。伊都国の南に邪馬臺国と奴国、不彌国、投馬国が省かれた記載になっている。奴国、投馬国の行程は傍線行程であることを裏付ける内容となっている。不彌国は邪馬壹国に隣接または邪馬壹国そのものだから省かれている。(ただし、『広志』自体ではなく、『翰苑』の著者は「邪」を覗いた「馬臺国」という記載をしており、「邪」を「奴国」を考える混乱が起きている。)伊邪久国は『隋書』「琉球国伝」に「夷邪久国」として記載される。投馬国、斯馬国の「投」と「斯」の音は異なるので同一とは言えないが、邪馬壹国行程記述で沖縄方面は意識されていたことは伺える。『隋書』「俀国伝」の「都於邪靡堆,則《魏志》所謂邪馬臺者也」の記載は邪馬壹国説に対する反証になりうる記載だが、既に邪靡堆(ヤマト)に都していることがわかっていたので『後漢書』の通り「邪馬臺国」の記載が正しいということが当時の共通認識になっていたということを示すまでだろう。(R03.12.27追記)水行十日陸行一月は漢書西域伝を見ても最後に全行程を書くのが倣いなので、全行程である。また、別途、郡(帯方郡)から女王国まで一万二千里と書かれており、⑦奴国の傍線行程を除いた主線行程の里数の合算10500里とは1500里の差がある。②~⑤までは余里と書かれているので、実際の地図を見てこのこの差を余里に割り振ると②7300里、③1300里、④1300里、⑤1100里程度となるだろう。この合算11700里程度を一万二千里と記載したと考えられる。②の7千余里は①と②を合わせた帯方郡~狗邪韓国の行程となる。②乍南乍東とは南進と東進を繰り返すという意味になるので、直線距離ではなく、ジグザグに進む行程となり、南進の直線距離と東進の直線距離の合算値、またはそれ以上の距離となる。
韓国行程は陸行にしなければ、「陸行一月」は成立しない。①の通り、水行したのは帯方郡から韓国までの行程だ。そうしなければ③の始めて海を渡るという記載も成立しなくなる。(R03.12.27追記)魏志倭人伝には邪馬壹国の奴婢の殉葬について記述がある。ところが日本の古墳にはその痕跡はみつかっていない。行程から導いた邪馬壹国の位置、その勢力範囲には吉野ケ里遺跡がある。ここは紀元前4世紀縄文時代からの遺跡だが、古墳時代にはその役割を終えている。ここには首なしの人骨を治めた甕棺もみつかっている。判明していないか、残っていないだけで、邪馬壹国には殉葬の習慣があったと思われる。
前回書いた『熊曾とは何か? ヤマトとヤマイの古代史』からその後の考察を経て、古代日本勢力の系図を見直してみた。前回、また、石上神宮に剣を奉納し、池沼池などを作ったのはオシロワケの業績にしてしまったが、古事記に記載されるのは同時代のイニシキの業績なので訂正した。