熊曾とは何か? ヤマトとヤマイの古代史
日本書紀の欽明天皇の巻で、欽明天皇の子女、七男六女を記す際、当時伝えられ書物によって出生の順番が変わり、兄弟が入り乱れて記載されている現状を編者が嘆く記載がある。帝王本紀に古い名が多く、選集する人も移り変わり、伝え写す際に混乱した現状を伝えている。欽明天皇という比較的新しい代でさえこんな状態だ。古事記の原本となる帝紀においては口頭伝承から起こしており、これ以上に混乱した伝承であったことが予想される。同一人物に当時から執筆時までの間にいくつもの呼び方があり、人物の特定が難しく、まして系図の順序も定かでは無かっただろう。年代もわからない名を集めて系図化していく、それが帝紀の編集方法だったのではないか。
前回書いた『天皇和風諡号からの見る古代日本』で、後で気づいたことをバラバラと追記していったが、それをまとめると以下のようになる。
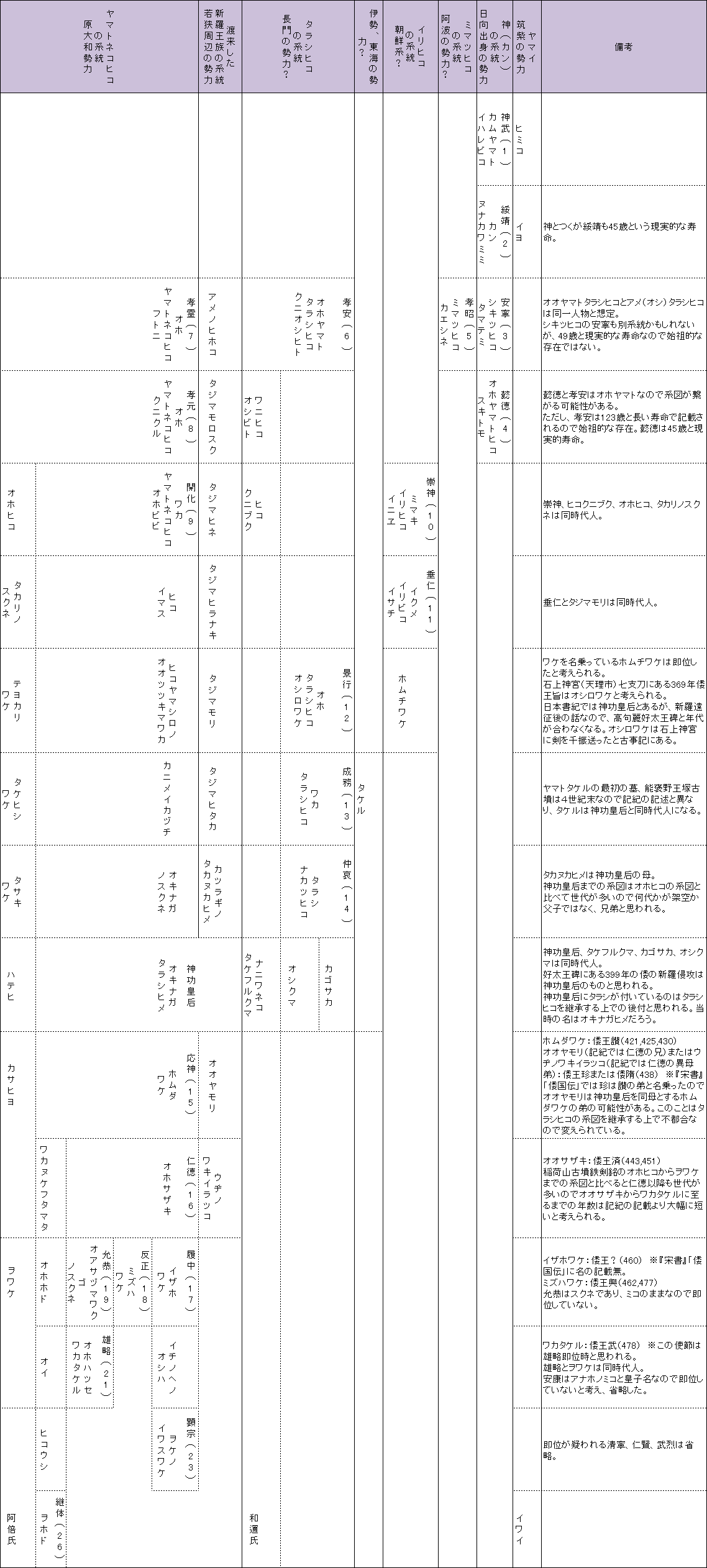
現在の九州のことを『古事記』では筑紫島という。筑紫国という地域名は筑前、筑後に分かれる前の福岡県西部を指す。そしてここは魏志倭人伝が伝えるヤマイ(邪馬壹)国の場所であり、後のイワイの根拠地となる。つまり、九州の中心は筑紫であったということだ。九州という現在の呼び名についてはいつから呼ばれていたかわからない。九州とは古代中華のそれぞれの州、その全域を指す言葉だ。日本としてみれば蝦夷地が認識されるまでの2番目に大きい島に過ぎない。筑紫島という呼び方はヤマトから見た他称であり、自称では九州という呼び方は古くから使われていたと思われる。
倭国大乱期であり、魏志倭人伝においてヤマイ国が成立したとされる2世紀からヒミコ、イヨの3世紀にかけて、九州こそが倭の中原という歴史認識があったと思われる。魏志倭人伝に記載される旁国21国(斯馬国、百支国、伊邪国、都支国、彌奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、對蘇国、蘇奴国、呼邑国、華奴蘇奴国、鬼国、爲吾国、鬼奴国、邪馬国、躬臣国、巴利国、支惟国、烏奴国、奴国)は、遠絶の地として位置が示されない国として記載される。その割には沖縄(投馬国)、ミクロネシア(裸国、黒歯国)という遠隔地の記載はある。本州の記述については中国地方の倭種、四国の侏儒国の記載しかない。(『かくも明快な魏志倭人伝』(木佐敬久 2016)参照。私はこの著書で邪馬台国論争は終結したと考える。)
投馬国をわざわざ記載したのは中国に近く、より2次元的に邪馬壹国の位置を指定するために記載されたと思われるが、船で行くのに1年かかると記載がある裸国、黒歯国がわざわざ記載されているのはなぜか。それはヤマイが後のヤマトよりも海洋文明であったことを語っている。本州が倭種という記載になっているのは、そこにある各国が南の狗奴国に比べれば反抗的でないにしても、行く手を阻む軍事力を持っていたことを示している。なので旁国21国は行き方を記載出来ない遠絶の地と記載されているのだ。海洋国としては後のヤマトよりも力を持っていたが、陸上国としてのヤマイの限界を示していると言える。
五胡十六国の動乱で中国の文献に倭の記録が残らなかった3世紀後半から4世紀において、ヤマイの力は瀬戸内海を通してヤマトまで及んだと考えられる。それはギリシャ、ローマを育んだヨーロッパの地中海の海運と同様、瀬戸内海の海運もヤマイにとって有利なものだっただろう。この時期、ヤマイによって日向出身とされる後に神と呼ばれるイハレビコ、ヌナカワミミの系統がヤマトまで派遣されたと思われる。それとは別に在来のヤマトの王もいたと思われる。それがヤマト根子日子の系統だろう。この系統は最初はヤマイの軍事力の前に恭順していたのだろう。ただし、瀬戸内海の勢力の及ばない地域もあった。山陰北陸は新羅王族を自称する勢力の支配地域だった。伊勢、東海はヒミコの時代にも前方後方墳を作る独自の勢力がいた。
イハレヒコの名前の由来、磐余の地は『ヤマト王権の古代学』(坂靖 神泉社2020)によるともともと大伴氏の地盤だったという。壬申の乱の際に活躍した大伴吹負のおかげでこの地が建国の地となり、藤原京造営に至ったとされる。『天皇陵古墳を歩く』(今尾文昭 朝日新聞出版2018)によるとこの藤原京造営でこの地の四条古墳群が壊されたわけだが。このようにイハレヒコの名前の由来は天武天皇の意向が入っており、この磐余の地に纒向遺跡のようなヤマトの原型は無い。欠史八代に旧辞が無く、イハレヒコに突然長い旧辞が現れる不自然さを見ても、イハレヒコの実在性は欠史八代より低い。(R02.09.22追記)
イハレビコ、ヌナカワミミの系統もスキトモで絶えたと思われる。その後、新たにヤマイから派遣されたのは日を表す朝鮮系の音の響きを持つイリヒコの系統イニヱだ。この系統は奴隷の殉葬という残酷なヤマイの習慣も持ち込んでいる。古事記に記載されるイニヱの時代の疫病、三輪山の大物主神とのやりとりを見る限り、簡単にヤマトを支配出来たわけでは無さそうだ。ヤマト根子日子のオホビビの兄弟、オホヒコを味方につけ分断し、その異母兄弟タケハニヤスを討っている。この時期に、北陸、伊勢、東海の勢力とも接触する。その際に将軍となったのはオホヒコと、その子タカリノスクネだ。2代目イリヒコのイサチは北陸の新羅系タジマモリも支配し、伊勢には娘を送っている。
瀬戸内海の入り口という拠点の長門ではタラシヒコの系統が力を付けてくる。天下を治めることを「天の下治らしめいしき(アメノシタシラシメシキ)」と読む。それを自称するほどの力を持ってくる。イリヒコの系統は3代目ホムチワケの代にこの勢力のオシロワケに敗れることになる。古事記のホムチワケの記述には出雲の祟りの話も出てくるので出雲の勢力もタラシヒコに味方したのだろう。西からの圧力がなった伊勢、東海では後にヤマトタケルと呼ばれるタケルが東国に力を及ばすようになる。
百済はヤマイではなく、タラシヒコのオシロワケに七支刀を送っているので、この時点でヤマイの力を凌駕していた可能性もある。また、イリヒコのイサチ、イニヱはヤマイが送ったのではなく、ヤマイの本家が直々やってきた可能性もある。となると、イワイはヤマイの傍系なのか。(R01.12.16追記) 石神神宮はオシロワケよりもイニシキとの関係が深く、イニシキは、イサチ、イニヱの直径と見られるため、まだ、ヤマイの力が強かったと思われる。(R03.01.24追記)
古事記でにはホムダワケ(応神)の求めで百済から和邇吉師(日本書紀では王仁)が来日したと記述される。その後継はフミノオビトとされる。また、続日本紀では王仁の子孫、文忌寸最弟(ふみのいみきもおと)は漢の血筋を引くとされている。和邇氏は文献上、和邇吉師との系図の記載は無い。また、これを認めてしまうと、イニヱ(崇神)の代に活躍したヒコクニブク、オキナガヒメの代に活躍したタケフルクマの事績を否定してしまうことになる。しかし、和邇氏勢力圏の東大寺古墳からは出土した鉄剣に後漢の元号である中平(184~189)と書かれていたことから考えると、和邇氏は漢からの渡来系であることが見えてくる。また、元祖タラシヒコの欠史八代のクニオシヒトの奈良時代に作られた漢風諡号「孝安」は後漢の6代皇帝安帝(正式名は孝安皇帝。在位106~125年。)から来ている。文献の記載とどちらが事実でどちらが歴史認識かはわらないが、タラシヒコの系統は漢の末裔という歴史認識の痕跡が見える。傍系の和邇氏は残ったが、タラシヒコの本家はオキナガヒメが滅ぼしてしまったので傍系の和邇氏の扱いもヤマトとしては難しかったと思われる。古事記において和邇吉師は『論語』十巻と『千字文』一巻を持ち込んだと記載されているが、ワカタケル(雄略)の時代の鉄剣銘についても中国人が書いており、この時代に日本人で漢字が使える者はいなかった。ホムダワケ(応神)は宋に使節を送った倭王讃なのでその関連からこの時代に比定されたのだろう。クニオシヒト(孝安)は漢の皇帝そのものを指し、タラシヒコはその後継を称したと考えられる。
系図としてはクニオシヒトから続くフトニ、クニクルの漢風諡号もそれぞれ、後漢12代霊帝(正式名は孝霊皇帝。在位168~189年。)、前漢10代元帝(正式名は孝元皇帝。在位紀元前48~紀元前33年。)と前後した漢の皇帝名が漢風諡号として使われている。ただ、こちらは和風諡号がヤマト根子日子なので在来ヤマトの系統だ。漢風諡号は安帝から続く系統として適当に付けられたものだろう。ただ、フトニの漢風諡号に使われた霊帝については在位の末期が中平であるため、和邇氏の系統を意識したものである可能性はある。黄巾の乱が起きた期間であり、霊帝の死と共に洛陽に董卓が入ってきた。漢王室の人々が僻地まで逃亡する必要性が十分にあった時代だ。公孫度が遼東太守になるのは189年なので、まだ遼東、楽浪郡が独立状態になる前だ。(R02.1.19追記)
同じく力の空白地帯であったヤマトでは在来ヤマトネコヒコの系統と北陸新羅系タジマモリの孫娘が結婚し、両者の統合女王オキナガヒメが立つ。オキナガヒメは新羅王の血筋も引いているので、本来女王国で、当時男王が立っていた新羅を攻め、新羅女王になろうとする。その過程でタラシヒコの勢力にはタラシヒコの傍系だったタケフルクマを味方に付けて、分断し、本家タラシヒコのカゴサカ、オシクマを滅ぼしてしまう。そのまま朝鮮半島に上陸し、新羅を攻め取ると、高句麗の好太王と衝突し、撤退することになる。ただし、この遠征において軍事的にヤマトはヤマイよりも優位になる。九州に東国の前方後方墳と西国の円墳の特徴を両方取り入れたヤマト独自の前方後円墳が作られ始めるのもこの時期になる。東国ではワカタケルの時代に前方後方墳から前方後円墳に変えられている。
新羅初の女王は632年即位の善徳女王となるのでこの時、女王国というのは誤り。ただし、『三国史記』に記される建国神話も含めて王妃の立場は高い。そのため、オキナガヒメの新羅遠征の動機として新羅王の血を引くからという点はありうるが、女王国にするためという点は誤りとなる。逆に善徳女王のような女帝が生まれ、王妃の地位が高かったのはオキナガヒメの影響があると思われる。善徳女王はシャーマン的な存在だったが、内乱の中陣中に没するという男勝りの死に様も見せている。(R02.01.13追記)
最古の前方後円墳は近畿の3世紀初頭の纒向石塚古墳と播磨の瓢塚古墳。ところが3世紀の千葉内房にも神門古墳群のように前方後円墳は築造されている。九州、四国の最古とされる前方後円墳は前方後円墳というよりも帆立貝型古墳で円墳の延長だ。ここでの東国の前方後方墳と西国の円墳の特徴を両方取り入れたヤマト独自の前方後円墳とは箸墓のことを言うつもりだった。ただ、その原型はそれ以前から存在していた。3世紀はイハレヒコ以前の時代であり、記録が皆無だが、一時的にヤマトの影響力が千葉まで及んだ時期があると考えらる。もし、この時代が記録に残っていたとすれば、日向から来たイハレヒコ自体がヤマイの日子を継承する上での創作で、ヌナカワミミはヒミコ以前に九州とは別に東海、千葉内房まで影響力を持ったとも考えられる。そうだとすると、ヌナカワミミの墓は宮内庁指定とは別の前方後円墳と考えられる。(R02.02.08追記)
神門古墳は現在、3号墳、4号墳が宅地になり消失して、5号墳のみが残る。現在残る5号墳も形状が分かりづらいほど風化しており、隣接する小山が前方部に見えるが発掘調査によると無関係な小山で実際は帆立貝式古墳だ。西の姉ヶ崎にある姉崎天神山古墳は4世紀築造、姉崎二子山古墳は5世紀前半で立派な大型前方後円墳だ。後にこの地は上総の国の国府となり、上総の国分寺も建てられる。つまり、この地のヤマトの影響力は一時的なものではなく、3世紀から続いてきたようだ。4世紀には愛知では二子古墳、静岡では北岡大塚古墳、神奈川では秋葉山古墳と前方後円墳が出現し、ヤマトの影響力が確立している。この時期はイリヒコのイニヱ、イサチの時代だ。古事記にはイニヱの時代にオホヒコが北陸から、タカリノスクネ(古事記ではタケヌナカハワケ)が東海から攻め入り、会津で合流したとある。4世紀前半に東北までヤマトの勢力が行けたかは疑わしいが、この時期に東海を経て内房まではヤマトの影響力が及んだようだ。しかし、このオホヒコの系統はヤマト根子日子のクニクルからの系統なので、イリヒコの系統がヤマトや中国、九州の対処で追われる中、半独立的に動けたことが想像出来る。後にタケルを生み出す伊勢の勢力も接触したばかりなので半独立であったのだろう。内房でヤマトの影響力が入るのが早かったのはヤマト根子日子の時代に遠交近攻で海を通して東海を攻める上で同盟関係にあったためなのではないだろうか。北関東の前方後円墳は5世紀後半以降が多いが4世紀も皆無ではなく、前橋天神山古墳は4世紀の前方後円墳だ。(現在ほぼ削平されてしまっている。)一時的に遠交近攻の同盟関係にあったと考えられる。4世紀後半に入ると出雲等中国地方の実力者タラシヒコの系統がイリヒコの系統を圧倒する。伊勢のタケルはその時期に伊勢、東海を独立状態にしたと思われる。そのタケルの勢力もヤマト根子日子の系統のオキナガヒメに帰順したのだろう。神門古墳などのように見た目の風化が激しいが、歴史的に見ると重要な古墳が消失してしまっていることは結構起きているようだ。(R02.02.09追記)
オホヒコ自体が名としてはあいまいな名で意味としては大日子。つまり、大王という意味しかない。新潟には既に4世紀前半に城の山古墳のような中型古墳がある。稲荷山古墳鉄剣銘にもオホヒコ以前の系図は無く、大和根子日子との関連は後から付けられたもので、独立勢力だったという従来の考え方は正しいかもしれない。(R02.05.08追記)
3世紀末の東日本前方後円墳としては甲斐天神山古墳がある。こちらはホタテ貝型ではなく、前方部がしっかりした大型前方後円墳だ。付近には4世紀後半の前方後円墳、甲斐銚子塚古墳もある。こちらは造り出しまで発展している。東日本の古墳としては上野の5世紀後半の太田天神山古墳に次ぎ、4世紀としては東日本最大となる。箸墓古墳型古墳は同時期に東日本にも存在していたことになる。甲斐はヤマトの直接的な影響下にあったと考えられる。ヤマトは西日本よりも東日本の縄文文化の影響が大きいように思える。その時代は初めて国を治めたとされるイリヒコの時代以前、欠史八代のヤマト根子日子の時代に遡る。(R02.11.21追記)
倭を統一しないまま、朝鮮半島に攻め込んだわけだが、大航海時代以降のヨーロッパ帝国主義はそれぞれヨーロッパ列強を倒すために、競ってヨーロッパ以外の世界に攻め込んだ。これと同様にヤマトもヤマイを超えるために朝鮮半島に攻め入ったのだ。その後もヤマイは倭の中原としての権威と海洋国として実力は持ち続けたと思われる。
そのオキナガヒメは最初は熊曾を攻めるつもりだったのが、天照大神の託宣で新羅を攻めることになったと、古事記、日本書紀共に記載される。熊曾とは何なのか。九州であればヤマイのはずである。魏志倭人伝にはヤマイ国の南にヤマイに従わない狗奴国があったとしている。九州は筑紫島と呼ばれたぐらいなのでさすがにこの時期は狗奴国もヤマイに制圧されていたはずだ。
熊曾が帝紀に初めて出てくるのはオシロワケの時代だ。ヤマトタケルが熊曾を討ったとある。しかし、実際のタケルは伊勢の勢力なのでそれはありえない。伊勢のタケルはワカタケルの時代にヤマトに改葬され、ヤマトタケルとして偶像化された。ヤマトタケルは出雲も平定している。これは伊勢のタケルではなく、ワカタケルが行ったことだろう。そして熊曾を討つ話は、それまでも権威だけは持ち続けたヤマイつまりイワイを滅ぼしたヲホドの事績を思い起こさせるのだ。
ワカタケルの寿命は古事記では124歳、日本書紀では60歳と珍しく、日本書紀の年齢が現実的な年齢となっている。『日本書紀の謎を解く』(森博達 中公新書1999)によると、日本書紀は雄略記から書かれ、それを書いたのは中国人だという。そのため、非現実的な年齢は避けられたと考えられる。その父、オアサヅマワクゴノスクネは記紀共にイズホワケ、ミズホワケと兄弟相続された弟とされたが、宿禰という官位を持つオアサヅマワクゴが即位したとは思われない。イズホワケ、ミズホワケとワケ(王)の弟であったかも疑わしい。ワカタケルは宋への施設において、倭王興つまり、ミズホワケの兄弟と称した。それは皇位の正当性を示すためである。つまり、イズホワケ、ミズホワケと同世代人だったのではないだろうか。ヲオドにより、皇位はホムダワケの血統に戻ったが、ここも実は皇統の断絶期間だった可能性がある。
古事記に記載されるオアサヅマワクゴの78歳という年齢、日本書紀に記載される42年という長い在位期間は、オアサヅマワクゴがオホサザキに仕える大臣の期間なのではないだろうか。こうしてみると倭王武の上表文でわが祖先が自ら甲冑を付け山海を渡り歩きと語られているところがしっくりくるのである。オオキミ自らがそこまでしたと思われない。そしてオアサヅマワクゴは伊勢のタケルの子か孫だろう。(R02.09.22追記)
つまり、ヲホドにとっても元祖日女、日子の権威を持っていたヤマイを滅ぼすとは言えなかったわけだ。そこでヤマイとは別の名を出し、ヤマトはそれを討ったことにしたのだろう。ヲホドの時代に任那四県を百済に割譲する代わりに南朝梁の五経博士がやって来る。そこで魏志倭人伝を読んだだろう。こういうものが伝わった時にまず、関心を持つのは、現代の日本でもそうだが、自分の国のことだ。そこに邪馬台国(魏志倭人伝では邪馬壹国だが後漢書から邪馬臺国に記載が変わった。)の南に狗奴国があったことを知る。陳寿の時代に狗奴をクヌと読んだかはわからない。ただ、ヲホド時代にはそう読んだのだろう。ここからクマソが誕生したのだろう。自分たちが倒したのは魏志倭人伝に書かれた邪馬台国ではなく、狗奴国だと。自分達が邪馬台国の継承者だと。そして、イワイを倒したことが邪馬台国の本来の姿を浮かび上がらせたことにして、天の岩屋伝説を作ったのだろう。
陳寿が『三国志』を書いたのは西晋280~290年辺り。范曄が『後漢書』を書いたのは南朝宋432~440年辺り。范曄は宋の政治家でもあったので倭王讃の使節には直接会ったと思われる。邪馬壹を邪馬臺に書き換えたのは彼らがヤマトを名乗ったためであろう。(R02.01.12追記)
熊曾は神代の記述にも書かれる。ただ、神代の記述は天の岩屋伝説と同様に帝紀よりも新しく、ヲホド以降に作り上げられたものだ。神代の記述では、熊曾はタケヒワケとも言うという。タケヒワケとはイリヒコのイニヱの時代に東国に向かったオホヒコのひ孫、タケヒシワケだ。その名は文献資料にはなく、埼玉稲荷山古墳鉄剣銘に記載される。オホヒコの一族はタケヒシワケの4代後、ヲワケ、そしてオオキミはワカタケルの時代に埼玉まで来たのだから、九州に行ったわけではないだろう。これもヲホドのイワイ征伐をヤマトタケルにかけ合わせ、オホヒコの系譜からおおよそタケヒシワケの代だったと逆算して記載しているのだ。
偽書説もある『先代旧事本紀』の国造本紀には、ワカタラシヒコの時代にオホヒコの5世孫、田道命が筑志國造に任命されたとある。日本書紀でもオホヒコは筑紫国造の先祖とあるので根拠の無い記述ではないだろう。稲荷山古墳鉄剣銘では5世孫はハテヒなのでヲワケとは別系統と考えられる。ヲワケまで続くオホヒコのひ孫、タケヒシワケの名が熊襲の地に付けられたのもこれと関連するのかもしれない。古田武彦の『『風土記』にいた卑弥呼』では風土記筑紫国逸文(原文は散逸し、『釈日本紀』巻五「筑紫洲」に引用として残る。)にある筑紫君等が祖、甕依姫(ミカヨリヒメ)が卑弥呼だとする。磐井をヤマイの後継と考える上でも納得のいく仮説だ。では田道命とはなんなのか。オシロワケの時代にヤマトとヤマイの力関係は既に逆転していたと考えるとヤマイの力を抑える上でオホヒコの系統を目付として派遣したいたことも考えれる。『先代旧事本紀』に田道命を祀ったとある筑紫神社は筑紫中央部にあり、ヤマイがあったと思われる地点より北にある。オホヒコのひ孫、タケヒシワケもその南部に派遣されていたのかもしれない。あるいは実支配はしていないが、この時代の九州をヤマトが支配していたことを裏付けるために、ヲオド以降にオホヒコ系の名を国造として使ったのかもしれない。『古代豪族系図集覧』では大彦命―武渟川別命―大屋田子命―田道命となっており、そうなると、田道命はタケヒシワケと同世代になる。甕依姫を祀ったことで、荒ぶる神を鎮め、筑紫の神と呼ばれたと記載があり、まさに倭国大乱を鎮めた卑弥呼を連想させ、当時崇拝の対象ともなっていたことを示している。甕依姫が卑弥呼というのは最も可能性が高いと思われる。(R02.09.08追記)
ヲホドとその後継としてはヤマイ、邪馬台国の権威も引き継ぐ必要があった。なので魏志倭人伝に書かれる邪馬台国のヒミコ、イヨの記述は残すことが出来なかった。このことはその記憶のない後代の日本書紀の編者達も悩ますことになったのだろう。ただ、人道的には人身供犠を伴う悪質な奴隷社会だったヤマイからの解放は良かったことと言えるだろう。
R01.12.08