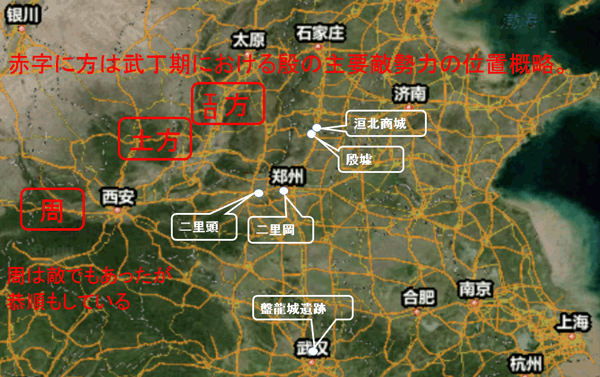 中国4000年と言われて久しいが、以前は中国3000年と言われ方もあった。史記の記述では、殷は紀元前17世紀に遡るものの、殷墟遺跡は早くても紀元前14世紀より前には遡るものではなかった。殷墟遺跡の発掘が行われる前には、夏王朝と共に殷王朝も伝説の王朝とされていた。それが紀元前16世紀に遡る二里岡遺跡、紀元前19世紀に遡る二里頭遺跡の発見により、所謂、黄河文明は紀元前19世紀まで遡った。それに伴い中国4000年と言われていった。しかし、黄河の南にある長江上流、四川省成都(蜀)北部から河口の杭州の南に至るまで、黄河文明をさらに1000年以上遡る長江文明が存在していた。史記にはそれらの記載はほとんど無い。あっても蜀が殷末に周の武王による、殷の紂王征伐に参加したという周辺の扱いだ。それは何故か。中国において文字を発明したのが黄河文明の殷だったためだ。長江文明は黄河文明より遡って、青銅器、城塞都市を作り上げたが、文字を持たなかったため、自分達を中心にする歴史を残し、紡げなかった。 中国4000年と言われて久しいが、以前は中国3000年と言われ方もあった。史記の記述では、殷は紀元前17世紀に遡るものの、殷墟遺跡は早くても紀元前14世紀より前には遡るものではなかった。殷墟遺跡の発掘が行われる前には、夏王朝と共に殷王朝も伝説の王朝とされていた。それが紀元前16世紀に遡る二里岡遺跡、紀元前19世紀に遡る二里頭遺跡の発見により、所謂、黄河文明は紀元前19世紀まで遡った。それに伴い中国4000年と言われていった。しかし、黄河の南にある長江上流、四川省成都(蜀)北部から河口の杭州の南に至るまで、黄河文明をさらに1000年以上遡る長江文明が存在していた。史記にはそれらの記載はほとんど無い。あっても蜀が殷末に周の武王による、殷の紂王征伐に参加したという周辺の扱いだ。それは何故か。中国において文字を発明したのが黄河文明の殷だったためだ。長江文明は黄河文明より遡って、青銅器、城塞都市を作り上げたが、文字を持たなかったため、自分達を中心にする歴史を残し、紡げなかった。とはいえ、二里頭遺跡や二里岡遺跡では文字は出土していない。文字が出土されるのは殷墟遺跡からだ。文字と言っても歴史を記載したり、思想を記述したりするものではない。そうしたことが行われたのは春秋戦国時代からだ。国同士の契約に使われたのは周王朝に入ってからだ。殷後期である殷墟時代では文字は動物の骨や甲羅に記載され、用途は占卜だった。史記の記述と遺跡の年代測定から二里岡遺跡は殷前期、二里頭遺跡は夏王朝とされる。黄河文明が史記に、当時の漢に繋がる王朝の歴史として記載があるのは文字を発明した殷墟の源流にあたるためだ。 私自身は黄河文明とは別の長江文明にしても、上流の四川省蜀、中流域、下流は別源流であるし、秦が中国を統一するまではそれぞれ異なる源流を持つ文化、地域が存在したと考え、所謂、統一中国が誕生するのは秦からだと考えていた。しかし、まだ文字を持たない殷前期である二里岡文化は長江にも盤龍城遺跡を持ち、それぞれの文化は緩い結合であったとしても、殷を中心とした統一体を持っていた。中原は殷を中心にしてこの当時から存在していたのである。 二里頭文化については本書の著者は影響がその周辺に限られることから、九州(冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、予州、梁州、雍州。つまり当時の世界観における世界全域)を治めたとされる夏王朝ではないとしている。私はそれでも夏王朝の記述の元となった文化が二里頭にあったことの方が驚きだ。殷という名前にしても周の時代に付けられた名前で当時そう言われていた訳ではない。殷墟の発掘から当時商と呼ばれていたとも言われていたが、実は商というのは殷墟の都市の名前だ。当時は歴代王朝が冠する国号という考えも無いし、春秋戦国時代にそれぞれ争い合う国という概念も無い。ただ、甲骨文字には味方については都市の名前、敵については~方という記載がされている。王朝について自称もなく、地理と勢力が区別されず漠然としていたのだ。自称した王朝が始まったのは周からだ。中国の歴代王朝からしてモンゴル帝国の元より前までは地域の名前が使用されていた。自称したのは周からだが、それでも中国の国号は地域なのか国なのかの判断は漠然としたものだった。この理屈で言えば殷も存在はしない。殷は史記の記述からすると600年続いたとされるが、この理屈では後期の殷墟の時代は商で、二里岡は文字が出ていないので当時何と呼ばれていたのかはわからないが系図が辿れたとしても、別物ということになる。現代からその時代、王朝を呼ぶ場合、二里岡~殷墟は殷で、二里頭は夏で構わないのではないか。ともかく殷の源流となる王朝という意味での夏王朝は存在していたのだ。 漢字という文字の歴史から見て殷の時代から史記の書かれた前漢の時代まで繋がっているのだが、歴史文献として記述が始まったのは春秋戦国時代からだ。史記は口頭伝承とともにそれらの文献を元にして、夏、殷の時代を書いている。春秋時代より前については同時代資料としてそのような文献はない。殷の同時代資料は文献ではなく、殷墟で占卜として用いられた甲骨文字だ。そのため、文字としては連綿として続いてきたものではあったが、春秋戦国時代と殷後期では断絶がある。同時代の一次資料として甲骨文字を見る時に、価値は高いが、歴史文献ではないためにそこから歴史を再現するのは困難な作業だった。それを成し遂げたのが本著となる。 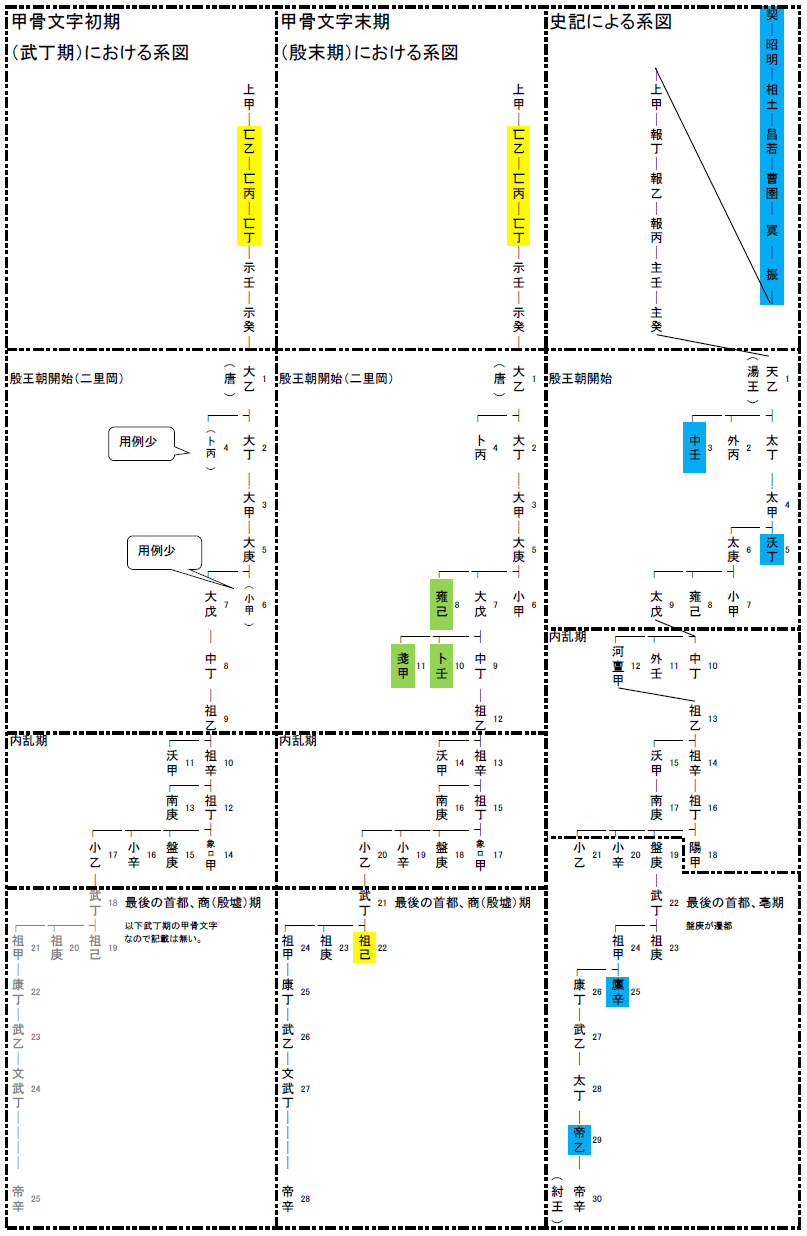 甲骨文字による占卜は殷王が貞人とよばれる占卜の専門集団に行わせる。様々な自然神に対して占卜を行うのと共に祖先に対しても祭祀を行うために、そこで同時代資料として系図が浮かび上がる。史記に記載された系図とそれを比較したのが左記図となる。 甲骨文字による占卜は殷王が貞人とよばれる占卜の専門集団に行わせる。様々な自然神に対して占卜を行うのと共に祖先に対しても祭祀を行うために、そこで同時代資料として系図が浮かび上がる。史記に記載された系図とそれを比較したのが左記図となる。史記には殷王朝を建国した湯王より前から系図がある。そのうち契から振までの系図は甲骨文字末期にすら無い。これは殷滅亡後、周王朝が宋を殷の後継者にするために入れられた系譜だと本著で考証している。以前、宋王の血筋を引く孔子は殷の末裔の可能性があると書いたが、実は宋王に殷の血の繋がりは無かったのだ。その後も同じ殷墟の時代であっても、初期から末期で系図の追加が行われている。時の王朝の政治的都合でこのように系図が改竄されることはあるようだ。これは日本においては徳川家康が征夷大将軍になるために、自らの系譜を源氏の系譜に変えたのと似ている。徳川家康の本当の血筋は踊り念仏の時宗の僧だ。 湯(トウ)という名前は甲骨文字前期にも唐という名であった。湯王は史記においても天乙という名も持っている。周の伝統から湯王が死後の王号で天乙が名だとされてきたが、殷の伝統では王号に十干を後ろに付ける伝統で唐が名で、大乙が王号と本著はしている。 史記の記述において中丁以降は内紛が多かったとされている。二里岡遺跡も紀元前15世紀頃に首都機能を失っている。ただ、甲骨文字では中丁よりも後の祖乙を始祖上甲、建国者大乙と並ぶ存在として祀っていて、それよりも後の王は祟りを呼ぶ存在としている。混乱期の始まりはその後の祖辛の時代からと考えられる。二里岡以降の殷遺跡の代表的な遺跡は1992年というごく最近に発見された洹北商城遺跡で殷墟のすぐ北東部にある。系図は1系統で書いたが、この時期について著者は複数の系統に分かれて争ったと考えている。史記の記述でも短期間で遷都が繰り返されたとの記載がある。また、武丁期の甲骨文字では中丁の兄弟卜壬、戔甲の記述が無い。卜壬、戔甲がいないとすれば中丁の時代に相続争いが起きるはずがないという証明にもなるが、混乱期に系統が複数に別れたという説を取るならば、武丁の時代には王として認められなかった卜壬、戔甲が武丁の死後、名誉回復されたとも考えうると私は思う。史記ではこの混乱期を収束し、殷の最後の都「亳」に遷都したのは盤庚としている。亳は最後の都のため、甲骨文字における商つまり殷墟であると考えられるが、甲骨文字では商に遷都したのは武丁であり、記述が異なっている。(※亳は殷建国の地と史記、竹書紀年、尚書では記載しているので二里岡を指している可能性が高い。それでは盤庚は他の地にあった都を戻したことになる。竹書紀年、尚書は亳ではなく殷に都を移したと書いてある。また、国名としての殷のことを商と呼ぶのは甲骨文字だけでなく、尚書や唐代の文献『括地志』にもある。H27/04/12追記。) 武丁は史記では賢人とされる。日本で言えば仁徳天皇のような記述のされ方だ。しかし、殷墟の発掘からその人物像は随分異なっていたことがわかる。大量の首が切断された人骨が出土されたのはまさに武丁の墓からだった。甲骨文字による占卜が行われたのは殷墟に都を移した武丁時代で、占卜での人身供儀が行われたのもこの時代だ。ただ、占卜で必ず人身供儀が行われたわけではなく、動物の供儀もあった。供儀を行うことの吉凶を占う占卜での記述でそれがわかる。また、人身供儀が行われたのは敵国の捕虜に対してだった。中国共産党の階級闘争史観から殷を奴隷制時代と呼んでいた時期もあったが、奴隷は階級社会としての階級ではなく、あくまで敵勢力から捕えられた人々だった。内乱期を統一した武丁は多く戦争を行ったと考えられる。武丁の墓からは当時の人口と比例しても大量の人骨がみつかったが、全てが殉葬という訳でなく、武丁の戦争での栄光を誇るために葬られたと考えられる。 史記の記述では殷6世紀の間、王は30代。殷末期の甲骨文字からは、王は28代。武丁期の甲骨文字からは、王は25代。用例の少ない4代卜丙、6代卜丙を王位についてないと考えると23代になる。殷墟時代は武丁から紂王こと帝辛まで8代3世紀に渡る。その間に系図は変わっており、文字の無かったそれ以前はさらに変わってくると考えられる。基本的に後になるほど追加されている。19代祖己のみが史記の記述からは減っている。史記にも祖己の名はあるが王位についていないとされている。また、殷墟時代の8代3世紀とすると1代37.5年の計算になり、そのうち2代が兄弟相続をしているので長すぎる計算になる。江戸幕府が260年15代だ。殷墟の墓は13基見つかっている。武丁が遷都したことは確かなので、王不在の期間があるのか、完全に抹消された王がいるのか、兄弟相続は無かったのか、実態は何が起きているのかはわからないといったところだろう。殷の時代は象もいたぐらい温暖だったので長生きで、晩年婚も可能だったのだろうか。また、祖己、祖庚、祖甲について著者は王でない人物も祀っているために、武丁との血の繋がりはないとしている。混乱期とともに王の相続が一つの系統ではない可能性もある。(盤庚が二里岡に都を戻したとするならば、武丁が遷都する前にも商は都として使われていた可能性もある。それであれば甲骨文字を使用し始めたのが武丁なだけであって、殷墟自体が使用されたのは盤庚より遡り、武丁の代は紀元前13世紀ではなく、それ以降になるかもしれない。※H27/04/12追記。) 以上のように系図については史記との記述に差異は確かにあるが、適合しているものも多いことに私は驚かされる。史記が1000年前の殷の系図をよく残せたものだと私には思える。現代と比較すれば平安時代以前の記述である。しかも、春秋時代以前は歴史文献は断絶していた。未だに古事記、日本書紀からそれが書かれた5世紀前の魏志倭人伝に書かれた卑弥呼の特定は出来ていない。司馬遷、または司馬遷が参照した春秋戦国時代の文献の著述者達は甲骨文字を読んでいたのだろうか。口頭伝承だけでここまで残るのだろうか。実際、殷墟遺跡の発掘前から、甲骨文字が記載された骨、甲羅は流通していた。ただ、史記の記述は周の祖先崇拝や伝統を前提にしており、甲骨文字から見えてくる殷独自の伝統についての無理解は否めない。伝承としても伝わっていなかったのだろう。たとえ甲骨文字を見ていたとしてもそこまで理解出来ていなかっただろう。 甲骨文字の占卜のやり方は文字が書かれた骨や甲羅を火で炙り、ひび割れが卜の字となれば吉だ。卜の字が出る箇所には裏に穴を開けてあり、著者が試したところ必ず卜の字が出るようになっているという。つまり、本当の吉凶の占いで用いられたのではなく、王の決定が正しいことの証明として使われたとのことだ。また、武丁の時代には後で字を付け加えることによって改竄も行わたという。神権的よりも政治的な用途で使われたようだ。そのため、戦争を行う際の承認としても使われており、そこからどのような戦争が行われたかもわかるという。その中には後に殷の紂王を倒した周の名も武丁の時代から現れた。周は現在の西安の西、天水との間辺りがという殷からみて辺境に拠点があり、甲骨文字によると戦った後、従わせたという。その他にも主に羌という殷の人身供犠の犠牲となった人々がいた北西の勢力に脅かされたようだ。兵力の動員数についても殷末期、紂王が70万人を動員して周の武王と戦ったとあるが、これは戦国時代の動員数を前提としていて、当時は5千人、多くて1万人だったという。 甲骨文字を私も見たことがあるが虫眼鏡で見ないと識別出来ないほど小さい彫り字だ。後の時代に毛筆で書かれた字とは随分違う。政治的なアピールという点では小さい字過ぎる気がするが、小さい字が逆に神秘性とともに最新テクノロジーを当時の人々に感じさせたのかもしれない。殷の時代の青銅器は後の周の時代の青銅器よりも複雑な文様で芸術性が高い。また、蓋付きで脚のある古代中国独特の盃も殷の時代から使われている。脚が付いている理由は下から火で酒を温めたためだ。神秘性と当時における最新テクノロジー両方において殷は統治を行ったのだ。 甲骨文字には狩りに行く際の吉凶を占うものが多い。殷末期に近づくにしたがって多くなる。これだけ見ていれば史記の記載や、孟子における革命史観における「一夫紂」(仁義を損なう紂王)通り、君主が遊びほうけて、政治を顧みなくなって滅亡したという歴史観に適合する。ただ、祖先祭祀については殷末に行くに従って多くなる。この儒教革命史観では武乙や紂王こと帝辛が祖先祭祀を軽んじたから滅んだとするが、むしろ逆だった。殷においては自然崇拝だったため、至高神「帝」や祖先祭祀は祭祀の中の一つに過ぎなかったが、周は帝や祖先祭祀を重視していた。それは儒教に継承されていった。孔子は殷の末裔という説を私は注視してたが、孔子は既に周の伝統に染まりきり、儒教は周のアジテーターであり、権威者だった。著者は殷で行われた狩りについても、狩りの地での示威行動、味方勢力の交流、軍事訓練など政治的な行動であったとする。 宋代の朱子学が説く「古えの明徳」は、殷、夏、三皇五帝まで遡るはずであるが、結局は周の伝統と殷の滅ぼした後の政治的ご都合主義までにしか行き着かない。殷の伝統、価値観は断絶されている。殷もまた政治的ご都合主義で甲骨文字の占卜を利用してきた。むしろ、伝統や形式化する前の、武丁代の占卜の改竄まで行った政治性を伴っていた時に殷は栄え、儒教の言うところの古えの祖先崇拝を重視するほど衰えていったと言える。儒教の崇拝するところは非常にイデオロギー的で、正解ありきの観念論的である。むしろ、それを「大道廃れて仁義有り、 知恵出でて大偽有り。」と看破した老子の方が実態に従っていたことになる。 本著で随分批判の的となっている史記だが、司馬遷もまた当時前漢の儒者達の批判の的となっていた。司馬遷は儒教イデオロギーに縛られるのではなく、あるがままを書こうとした。だからこそ、前漢当時から一千年前のこともここまで伝えられたのだ。甲骨文字からわかったことの差異はもう既に伝わってなく断絶していまっていたから書けなかったのだ。 儒教もまた現代中国の価値観、そして日本の建国や現代の価値観に至るまで影響を与え続けているものでもある。古いものが権威を持っていると新しいものの居場所が無くなるという反作用の中で、儒教は時に破壊の的にもなってきた。その破壊する動機もまた観念的な動機であった。ただ、政治的な改竄が行われたことも含めて、事実は文字に残る。それが地理、文化の物理的、軍事的な統合を経なくても中国4000年、いや東洋4000年の歴史を紡いできたのだろう。それは観念的で実態から離れた時にその落差から遡って現れてくるものだ。 |