�P�@��ނƌ��N
�i�P�jJ�J�[�u
�ŏ��ɁA�݂Ȃ��A�ł��S���������ł���Ǝv����b��u�����ƌ��N�v�ɂ��Ď��グ�Ă݂܂��傤�B
�u���͕S��̒��v�ƌ����܂����A���̌��t�́A�P�X�W�P�N�ɃC�M���X�l�̃}�[���b�g���m�ɂ���ĉȊw�I�ɏؖ�����Ă���܂��B���Ȃ킿�A�܂�������������Ȃ������A���ʈ����������̕��������ł��邱�Ƃ����v�ɂ�薾�炩�ɂ��ꂽ�̂ł��B�����ł͒���ɂȂ��Ă���܂��āA�}�\�P�i���^���S���Ȑ��͂��̂��Ƃ�\�������̂ł��B�c�������S���A�����������̈���ʂ�\���Ă��܂��B�Ȑ��́A����ʂ������łP�����炢�̎��ɍŏ��l�������Ă���܂��̂ŁA����1�����炢��������ƍł����S�����Ⴍ�A����ȉ��ł�����ȏ�ł����S���͍����Ȃ邱�Ƃ�\���Ă��܂��B�S�̓I�Ɍ��܂��Ƃ��̎��S���Ȑ��̓A���t�@�x�b�g�́uJ�v�̎��Ɏ��Ă��鎖����J�J�[�u�ƌĂ�܂��B�i�ł͂Ȃ��Ăt�̎��ł���Ǝ咣������ރ��[�J�[������܂��B�܂�A��������Ȃ����Ƒ�ʈ����҂Ƃ͎��S�����������A�Ƃ������̂ł��B���[�J�[�Ƃ��Ă͂����������ł������������̂͂킩��܂����A�{���ɂ����ł���A���ɂƂ��Ă����ꂵ���̂ł����A�c�O�Ȃ���ԈႢ�ł��B����ʂƎ��S���̊W�͂i�̌`�ɂȂ�܂��B
�}�[���b�g���̃f�[�^�̓C�M���X�l�𒆐S�ɏW�v����Ă��܂����A�P�X�X�S�N�ɂ͎����w�̌����O���[�v�����l�̔��\�����Ă��܂��̂ŁAJ�J�[�u�͓��{�l�ɂ��K�p�����悤�ł��B�������A�ꕔ�̕����٘_�������Ă��܂��B�܂�A�܂�������������Ȃ����̒��ɂ͑̒�������A��҂���������֎~����Ă���l�����������Ă���A�����̕��͓��R�A���S���������Ȃ�̂ň���������Ȃ����̎��S����^�̒l��荂�߂Ă���Ǝ咣�����̂ł��B�������A�����̕��X�������Ă�J�J�[�u�͐��藧�����ł��B
�@���ʂ̈������l�Ԃ̎��������������́A�A���R�[���̎����Ǐ�p�ɂ��Ƃ���Ă��܂��B�����҂͐S�����̎��S�����Ⴍ�A����n���y�f���������サ�Ă���A�Ƃ����������ʂ�����܂��B���̒m�l�Ɍx�@�̊ӎ��ۂɋΖ�����Ă���������܂��B�ނ��畷�����b�ł����A�Ď@��͉�U�����̐l�����O�A�����K�����������ł��������ǂ����A�킩��ƌ������ł��B�����K�����������̕��̏ꍇ�͌��ǂ����ɂ��ꂢ�Ȃ̂������ł��B
�@�v����ɁA�A���R�[���͗ǂ���p�ƈ�����p��̂ɋy�ڂ��̂ł����A�ێ�ʂ����ʂ̏ꍇ�A�ǂ���p�̂�����Ƃ������Ƃł��傤���BJ�J�[�u�́A�A���R�[���͌��N�ɗǂ����炽���������ł����v�Ƃ͌����Ă���܂���B�u�ߓx�������Ĉ������邱�Ɓv�ƁA�Ƃ炦��ׂ��ł���ƍl���܂��B�����͂��߂Ƃ��āA�����̈��D�҂ɂ́A���s���邱�Ƃ͔��ɓ�����Ƃł����B
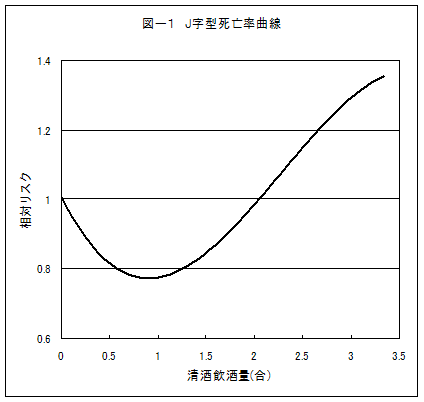
�i�Q�j�X�g���X����
�@�������ނ̎��L�v�ȍ�p�̓X�g���X�̔��U�ł��B���������ނ��Ƃ��A�l�X�ȃX�g���X�̉����ɂǂ�قǗL���ł��邩�͏O�l�F�߂�Ƃ���ł��傤�B����̂悤�ȃX�g���X�̑����Љ�ł͓K�x�̈����قNJȒP�ȃX�g���X�������@�͌�������܂���B����͑z���̈���o�Ȃ��̂ł����A�l�I�ɂ́A��ނ̎��u�X�g���X�����v��p��J�J�[�u�����̗v���̈�ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B�������A�u�X�g���X�����v��ړI�Ɉ�������ƁA������ʂ������Ȃ肪���ł��B�K�ʂ̈�����S�����Ȃ��ƁA�X�g���X�ɂ�鎾���͉���ł��Ă��A���R�[���̎��}�C�i�X�̍�p�ɂ���đ̒�������Ă��܂��܂����炲�p�S���������B
�@�܂��A�������邱�Ƃɂ��A�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������ɂƂ�邱�Ƃ�����܂��B���Ȃ��̍��e��͍l�����܂��A�����́A�Љ�̏������̍�p���ʂ����Ă���Ƃ������܂��B���݁A���E���ŗl�X�ȑ������N���Ă��āA�����̑����l�����]���ɂȂ��Ă��܂��B�����̍���ɕn�������邱�Ƃ͘_��҂��Ȃ��Ǝv���܂����A�C�X�������ɔʎᓒ������]���҂͂����������Ȃ��Ȃ�悤�ȋC�����܂��B�s�ސT�ł��傤���B
�Q�@�����ƌ��N�i��������������Ό��N�ɗǂ��B�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@����܂ł́A��ޑS�̂ƌ��N�Ƃ̊W�����グ�܂������A�����ł́A�����ɍi���Ęb���������Ǝv���܂��B�Ō�ɂ́u���C�����܂߂���ނ̒��Ő�����������Ԍ��N�ɗǂ��̂��B�v�ƌ��_���܂����A�͂����āA�݂Ȃ��܂ɂ��^��������������ł��傤���B
�i�P�j�����Ƒ��̎�ނƂ̔�r
���C���͍ł����N�ɗǂ��Ƃ�����ނł��B�u�t�����`�p���h�b�N�X�v�Ƃ������t������܂��B����́A�t�����X�l���t�����X�����Ƃ������E�Ɋ����鍂�`���E�����b������H���Ă�����ɂ͋ߗ����Ɣ�ג����ł��邱�Ƃ�\���������̂ł��B���̃p���h�b�N�X�͎��̂悤�ɐ�������܂��B�t�����X�l�̓��C�����ʂɐێ悷��̂ŁA���C��������ԃ��C���ɑ����܂܂��|���t�F�m�[�����A�̓��ő����Ă��܂��L�Q�Ȋ����_�f���������A���̉e�����琶�̂�h�䂵�Ă���Ă���B������A�t�����X������H���Ă��Ă������Ȃ̂ł���ƁB�܂��A���C���͉ʎ��������Ƃ��Ă��邽�߃J���E����i�g���E�����̃A���J�������𑽗ʂɊܗL���Ă���A�A���J���H�i�ɕ��ނ���܂��B�Ȃ�قǁA�_���͋����̂ł����_���̌��������ł���L�@�_�́A�̓��ő�ӂ���Y�_�K�X�Ɛ��ɂȂ��Ĕr�o����Ă��܂��܂�����B��������C�������N�ɗǂ��C���[�W��������ł��B����܂ʼn��x�����C���u�[��������܂������A���C���������������@�\�����u�[�����N����������ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�ł�����ʂ̑����A�r�[���┭�A�̃z�b�v��p�������A����A���R�[�������i�ȉ��A�r�[���ނƏ̂��܂��B�j�ł́A���̗��A��p��z�b�v�̎�����ɒ��ڂ��Č��N�ɗǂ����Ƃ��A�s�[������܂��B�܂��A�A���R�[���x�����Ⴂ���Ƃő̂ւ̈��e�������Ȃ��ƍl���Ă�����������܂��B�P���������傤���イ�i�]���̉��ނ��傤���イ�j���ێ悷�邱�Ƃɂ�茌��n�����������シ��Ƃ��Č��N�֊�^���邱�Ƃ��咣���Ă��܂��B
�����͂ƌ����܂��ƁA��������������ʂ̂��鐬�����ܗL����Ă���Ƃ�������������܂����A���̃C���p�N�g�͑��̎�ނɔ�ׂ�Ƃ͂Ȃ͂��ア�ƌ��킴��܂���B���C���̂悤�ɍR�_����p�����|���t�F�m�[���͑��݂��܂��A�Ă������Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�̓��ő�ӂ��ꂽ��ɂ̓����_���c��A�_���������܂�����A���J���H�i�ł�����܂���B���̏�A�������ɂ��Ă͈�������鎞�̃A���R�[���x���������A�G�L�X�����T�����炢����A��ނƂ��Ă̑��J�����[�������Ǝv��ꂪ���ł��B����͌���ł��̂Ō�قǐ��������Ă��������܂�����ǂ��A��ʓI�Ɍ����āu�����́A���̎�ނƌ��N�Ɋւ����p���r����Ɓu����肷��B�v�ƍl�����Ă���悤�ł��B���̂��Ƃ͏���҂����ł͂Ȃ��A�����ƊE�̊W�ґS�������̂悤�Ɏv���Ă���߂�����܂��B
�i�Q�j�H�����̌��N�ւ̊�^�͗����Ƃ̑�����
�H���������オ�鎞�ɋ��ɖ��킢�A�����ɗ����̖��킢���������Ă��ނ̂��Ƃ�H�����Ɛ\���܂����A�������H�����ɕ��ނ���܂����A��Ȏ�ނł���A�r�[���ށA�P���������傤���イ�y�у��C���͂قƂ�ǂ̏ꍇ�A�H�����Ƃ��ď����Ă��܂��B
������������ɂƂ��ẮD�������ނƂ������Ƃ͗[�H���Ƃ�A�Ɠ������Ƃł���ƍl���Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł�����A�H�����ł��鐴���̌��N�ւ̉e�����l����ꍇ�͈ꏏ�ɐH����u�����ȁv�܂Ŋ܂߂�ׂ��ł͂Ȃ����A�Ǝv���̂ł��B�ꏏ�ɑ̂̒��ɓ���̂ł�����A�u�����ȁv�ƐH�����̑g�ݍ��킹�ł��̎�ނ̌��N�ւ̊�^��_����ׂ��ł���Ǝ��͎咣�������̂ł��B
�u�����ȁv�̒��g���l���Č��܂��傤�B�����Ƒ����̗ǂ��u�����ȁv�̒��ōō��Ȃ̂́A�u�������݁v�ł��傤���A���́A�u�Ă����v�A�u���������v�A�u�ϕ��v�A�u�|�̕��v���A������A���ӂ���̖��ƌ����܂��傤���A���{�I�ȗ��������ɕ����т܂��B�����A�[���ɂȂ��Ă���A�Ƃ����C���ɂȂ�܂��B���܂��Ă�����t��}���āA���ɕ������̂�������Ɛ������Ă݂܂��傤�B�җ���߂������ɂ́A�����ɂ���炪���^�{���b�N�V���h���[����\�h���邽�߂ɐێ悷��Ɨǂ��A�ƈ�҂Ɋ��߂��Ă���H�i�Q�ƈ�v���邱�Ƃ��킩��܂��B�܂�A�����A�A���`�����A�H���@�ۂ��܂ޒ�J�����[�H�i�Ȃ̂ł��B��������ނ̒��ň�Ԍ��N�I�ł���Ƃ��闝�R�͂����ɂ���܂��B��ނ̌��N�ւ̊�^���l����ꍇ�́A�u�ꏏ�ɐH������̂܂ł��l���邱�ƁB��������A�����̌��N�ւ̊�^�͑��̐H�����ɕ����Ȃ��B�v�Ǝ咣�������̂ł��B
�i�R�j��ނ̎��u���t���b�V���́v�ƐH�i�́u�����₷���v
�ł́A���́A���������{�I�ȗ����ɍ����̂��ƌ����^�₪�c��܂��B������ؖ����Ȃ����莄�̍l���͐����͂������܂���B���̋^��ɓ����邽�߂Ɏ�ނ�����@�\�������Ă���ƍl���܂��B���̋@�\���u��ނ������Ă�������́i����͏ȗ����āu���t���b�V���́v�ƌĂт܂��B�j�v�ƒ�`���܂��B�ł��u���t���b�V���́v�̋����H�����͋���Ȏ_���ƃ|���t�F�m�[����L����ԃ��C���ł���A�t�ɍł��ア�H�������W���킵�������ł���Ǝv���܂��B����A�����H�i�f�ނɂ��A�u�����₷���v������ƍl�����܂��B�܂�A�H�i�Ɩ���F��������̖��Q�Ƃ̊Ԃɂ́A�����̐e�a�͂����݂���̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�������`��������́A�������Q�ƌ��т������ł����A���ށA�����y�і�Ȃǂ͐�������ł��ȒP�ɐ����ꂻ���ł��B
����ł́A�u���t���b�V���́v�Ɓu�����₷���v�ɂ���āA�H�����Ɨ����̑��������������悤�Ǝv���܂��B
�����̗[�т͏ē��ł��B�ē���H�ׂ����̐�̏��z�����Č��Ă��������B���Q�́A���炭���܂݂�ŏē����t�����Ă��邱�Ƃł��傤�B�����Ƀ��C���A������ԃ��C���������Ă��܂��B����Ȏ_�ƁA�|���t�F�m�[���i�|���t�F�m�[���͒`�����Ɨǂ��e�a���܂��B�j�ɂ��A���Q�ɂւ���Ă������Ɠ������`�����͂����Ƃ����Ԃɐ�����čs�����Ƃł��傤�B�オ�A���m�ɂ͖��Q�����t���b�V������܂����B����Ɠ����Ƀ��C�����g�����Q�ƐڐG�����C�����u���܂��v�Ɗ����Ă���Ǝv���܂��B�����ŁA�ē�����������H�ׂ܂��Ɩ��Q���烏�C����������A���t���b�V���������Q�͍ŏ��ɏē������ɂ������Ɠ����u���܂��v�Ƃ����M����]�ɑ���͂��ł��B�Ȍ�͂��̌J��Ԃ��ŁA�����ɂȂ�܂ŐH�n�߂����Ɠ������������ŏē������\���A���C���̂��܂����H�����I����܂Ŗ��키���Ƃ��ł��܂��B���C�����ē��̐H�����Ƃ��Č����ɋ@�\���Ă��邱�Ƃ����������������܂��ł��傤���B
�ł́A�ԃ��C���œ��{�����̑�\�Ƃ��āA��z��H�ׂ鎞��z�����܂��傤�B���Q�ɂ͑哤�`�������t�����Ă���Ƒz���ł��܂��B�ԃ��C���������Ă��܂��B���̈��|�I�Ȑ��͂ɂ���Đ�̏�͐ԃ��C���Ő�̂���܂��B���C�����̂��̂̎��u���܂��v���Q�͊����܂��B���ɁA�ݖ��Ȃǂ�t�������������ɓ���܂����A��̂��Ă��郏�C���Ɏז�����đ@�ׂȓ����́u���܂��v���Q�͔��M�ł��܂���B���̐�̗ǂ����C���ł�����A����Ȃ��Ƃ͋N��Ȃ��̂ł����B�ĂсA���C���������Ă��āA�哤�`���������Ƃ����Ԃɗ�������܂��B�Ȍ�͂��̌J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���ʂƂ��āA���C��������܂�̓����́u���܂��v�͂��܂芴����ꂸ�A���C���̖�����̏���̂����܂ܐH�����i�s���܂��B����ł́A�ԃ��C����P�Ƃň���ł���̂Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͎��Ɨ����̃~�X�}�b�`�ȊO�̉��҂ł��Ȃ��Ǝv���܂���ł��傤���B
�����Ő����̓o��ł��B�����̃��t���b�V���͎͂ア�̂ł����A���Q�ɕt�������u�����₷������v�ł���哤�`������������Ƃ��ł��܂��B�����ɖ��Q�́A�����́u���������v��]�֔��M���܂��B���ɓ�����H�ׂ����A�����͐����Ɏ���đ����Ė��Q���̂��邱�Ƃ��ł��܂��B�W���킵�������́A������ݖ��ɖ��Q�ɂ����邻�̍��������ɏ����Ă��܂��܂��B�����Ė��Q�͍ŏ��Ɋ����������̑@�ׂȁu���܂��v��]�֔��M����͂��ł��B�Ă����ƃ��C���̊W���������܂��B
���x�͐�����H�����Ƃ��ďē���H�ׂ鎞��z�����Ă݂܂��傤�B�����́u���t���b�V���́v���ア�̂Ŗ��Q�ɕt���������Ɩ�������܂���B���Ŗ���������z�����Ă��������B���̌��ʁA�ē��̖��ɖO���Ă��܂����A�����́u���܂��v�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�i�S�j�[�����������܂������B
�����Ǝ�ނ̑�����������邽�߂Ɏ�ނ́u���t���b�V���́v�ƐH�i�́u�����₷���v�Ƃ����l��������܂������A���܂������ł���Ƃ��^�����������܂��ł��傤���B�^������������Ƃ���A�����̌��N�ւ̊�^�͌����ă��C���ɂ������Ă��Ȃ��A����ԃ��C���ȏ�Ɍ��N�I�ȐH�����ł���ƁA�咣����̂����Ȃ����ł���߂ł͂Ȃ��Ƃ��l�����������܂��ˁB�����Ƒ����̗ǂ������́A��҂̊��߂郁�g�{���b�N�V���h���[���\�h�H�ł���A���C���Ƒ����̗ǂ��H�i�́A��肷����ƌ��N�˂���Ɩ��ł�����ˁB�[�H�ɐ��������݂����Ȃ闿����H���邱�ƁA���ꂪ�A���^�{���b�N�V���h���[������������̎�i�ł���ƍl���܂��B
�i�T�j���̎�ނ́u���t���b�V���́v
���̎�ނ́u���t���b�V���́v���l���Ă݂܂��傤�B�r�[���ނ́u���t���b�V���́v�́A�I�[���}�C�e�B�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�I�[���}�C�e�B�ƕ\�������̂͂ǂ�ȗ����Ƃ��K���Ƀ}�b�`����A�Ƃ������Ƃł��B�����̖����������Ă܂����A��ނ̎����킢���y���ނ��Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B�A���R�[�������������オ��Ȃ������H���̎��ɂ����␅�Ŗ��Q�����t���b�V������Ă��܂����A�r�[���ނ͈����K���̂���҂ɂƂ��Ắu���v�ɑ������Ă���A�Ǝv���鎞������܂��B
�P���������傤���イ�������̋@��ƂɃX�g���[�g�A��������ȂǁA�����`�ԂɑI���̗]�n���L�x�ɂ���A���A�āA���ȂǁA�����̑��l���Ƃ����܂��ė����ɑ��鑊���̏_��������Ă��܂��B�r�[���ނ̔̔��ʂ��A�f�R���̎�ނ����|���Ă��܂����A�ŋ߂̒P���������傤���イ�̔̔��ʂ̐i�W�������Ȃ��̂�����܂��B�����̂��Ƃ́A�����Ƃ̑����A�����Ɍ����u��ނ̎����t���b�V���́v���e�����Ă��錋�ʂł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�H�����Ƃ��ăI�[���}�C�e�B�ł���r�[���ނ�P���������傤���イ�ł����K��������Ƀx�X�g�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�l�ɂ����Ǝv���܂����A�H�����Ƃ��Ęa�H�ɂ��m�H�ɂ��K���ł��܂����A�����Ƙa�H�A�ԃ��C���Əē��قǂ́u�����Ƃ҂�����Ƃ����v���͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA�r�[���ƍł������������グ��A������������g�p���������A��\�I�Ȃ��̂��u�g�����v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ޕʂ̃J�����[�̏��ł���������������Ǝv���܂����A���Ɍ����r�[�����́A�r�[���̎��J�����[�������ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B��ނ̎��J�����[�͑啔�����A���R�[���ɂ���Đ�߂��Ă��܂�����r�[�����̌����́A�����̗ǂ������A�܂荂���J�����[��L����u�g�����v�ł���Ǝ��͐������Ă��܂��B����������S����Ē�J�����[�r�[����o���ꂽ�Z�p�҂̕��ɂ͐\����Ȃ��̂ł����A�r�[�������������߂邽�߂ɂ́u�܂݁v���H�v���邵���Ȃ����Ƃ�����҂ɍL�ׂ��ł���ƍl���܂��B������Ƃ����������ł����ˡ
�i�U�j��ޕʂ̃J�����[
�@�����͑��̎�ނƔ�r����ƃJ�����[�������Ƃ���������������߂ɁA��ނ��Ƃ̃J�����[�ɂ��Ă��b���܂��傤�B���݂̍��ۓx�ʍt�̌ď̂ɏ]���W���[���ŕ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�݂Ȃ�����s���Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��̂Ŏg�����ꂽ�J�����[�ŕ\�����邱�ƂƂ��܂��B�J�����[���r���邽�߂Ɏ�ނ̃A���R�[���x�����P���܂Ŋ�߂����Ƃ��܂��B���Ɋ�߂�����ނ̂P�O�O����ێ悵�����̊e��ނ̎��J�����[�����Z�o���܂��B�������邱�Ƃœ����y�U�Ŏ�ނ̎��J�����[���r�ł��܂��B���ʂ͕\�|�P��ޕʂ̃J�����[���Ɏ����܂����B�����̏ꍇ�A�A���R�[���x���͂P�T���ł�����P�T�{�Ɋ�߂����̓��̂P�O�O���̃J�����[�����v��ƂU.�X�L���J�����[�ɂȂ邱�Ƃ������Ă��܂��B���傤���イ���T.�V�L���J�����[�ōł����Ȃ��ł�����Ǎł������r�[���ł��W.�S�L���J�����[�ł��B�{����������킯�ł͂���܂���B���̕\���痝�����Ă������������̂͂ǂ�Ȏ�ނ������オ���Ă������ʂ̃A���R�[����ێ悵�����͂��̑��J�����[���͂���قǕς��Ȃ��ƌ������Ƃł��B�܂�A��ނ����J�����[���̓A���R�[���̗ʂłقڌ��܂��Ă��܂��̂ł��B����҂���̒��ɂ͂��̂��Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��������\��������Ⴂ�܂��B���A�a�̕��͂ǂ����Ă��������݂����Ȃ炵�傤���イ�����݂Ȃ����A�Ƃ���������������悤�ł�����B�Ԉ���Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂ł����A���̎�ނƂ̃J�����[�̍��𐳊m�ɂ����m�Ȃ̂ł��傤���B�A���R�[�����̂����J�����[�Ȃ̂Ŏ�ނ͂��ׂč��J�����[�H�i�ł��邱�Ƃ�m���Ă����Ă��������B���݂̃J�����[�ێ�ߑ��̎���ɂ����ẮA���ꂪ�A�S��ދ��ʂ̈������ʂł��B�c�O�Ȃ��瓜�A�a�̕��́A�����͔��������������ł��B
�\�\1�@��ޕʂ̃J�����[���@
|
�@ |
�ٺ�ٓx�� |
�ٺ�قP��������̔M�� |
|
���{�� |
�P�T�D�S �� |
�U�D�X kcal |
|
�ԃ��C�� |
�P�P�D�U �� |
�U�D�R kcal |
|
�r�[�� |
�T�D�O �� |
�W�D�S kcal |
|
�Ē� |
�Q�T �� |
�T�D�V kcal |
�i�V�j�����̑������
�����ƃJ�����[�̊W���l���鎞�����s�v�c�Ɏv�����Ƃ�����܂��B�u�����̑�H���v�Ƃ������t������܂����A�u�����̑�����݁v�����݂���̂ł��B���ɋ����A��ʂɈ�������Ă��銄��ɃX�����ȕ�����������Ⴂ�܂��B�����܂�������ł����A�����̕����悭�ώ@���Ă��܂��ƈ����̋@��ɂ��܂݂��قƂ�ǐH�ׂĂ�������Ⴂ�܂���B�{���ɃA���R�[�������D���Ȃ̂ł��傤�ˁB�������Ƃ��Ă܂݂�H�ׂ��Ɉ���������Ȃ���������܂����A����Ȏ��̗����̕����u�������������ȁv����������H�ׂ������A���R�[���̉e�������Ȃ��悤�Ɋ����܂��B�h�{�w�I�ɂ́A�A���R�[���Ƃ����G�l���M�[���݂̂�ێ悵�A�r�^�~����`�����Ƃ������h�{�f���s�����đ̂ɂ͈����͂��Ȃ̂ł����B�u�����ȁv�̕s�v�Ȕ����������ɉ��_�C�G�b�g���ł���̂ł��傤���B
(�W)������̃��[����
�܂݂����܂菢���オ��Ȃ������������������ň�����Ƀ��[������Â��������߂�������܂��B�������̈�l�ŁA������A�P�[�L��A�C�X�N���[�������H�ׂĂ��܂��܂��B���̗��R�Ƃ��āA�̑����A���R�[�����ӂ��邽�߂ɃJ�����[�������̂ł��̕⋋�p�ɓb�����ⓜ����g�̂��v������A�Ƃ�����������܂ł͐M���Ă��܂����B
���鎞�A�����l���R���g���[�����Ă���m�l����A�������������͊m���Ɍ����l���������Ă���̂͂ǂ����ĂȂ̂ł��傤���A�Ƃ�����������������܂����B�O�q�����l�����ł������ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�ǂ����������肵�܂���B����A�ЂƂ̊w���ɏo��A������̕����A�����͂�����悤�Ɏv���܂����̂ł��Љ�܂��B
���̐��ɂ��������A���R�[���ƂԂǂ����͉��w�I�ɍ\�������Ă��邱�Ƃ������ł���Ƃ����̂ł��B�Ȃ�قǁA�A���R�[�����u�h�E�����Y�f�A�_�f�y�ѐ��f����������CH�Q�\O�\H�Ƃ������q�\���������Ă��܂��B�ł�����A�̓��Ō����l���R���g���[�����Ă���Ƃ��낪�A�A���R�[�����Ԃǂ����ƊԈႦ�ăC���V�������傷��悤�Ɏw�߂���̂������ł��B�C���V�������������̂Ԃǂ����Z�x��ቺ�����邱�Ƃ͂������Ǝv���܂��B�C���V�������̕���łԂǂ����Z�x�͉�����܂����A�A���R�[���Z�x�͒ቺ���܂���̂ŃC���V�������͕��傳�ꑱ���܂��B���̌��ʁA�Ԃǂ����Z�x���ɒ[�ɒቺ����̂œb���ⓜ����ێ悵�����Ɗ�����悤�ɂȂ�̂������ł��B�����āA�����ɂ��C���V���������ׂ����܂邱�ƂɂȂ�܂����瓜�A�a�ƈ����̈��ʊW�������Ȃ������ł��܂��B�������A������̐��ł����Ă������l�̍������ɂ͈����̓��X�N���悤�ł��B
�i�X�j�H�����ƐH�O�y�ѐH���
��قǂ͂����Ȃ�u�����͐H�����ł���B�v�Ƃ��Ęb���n�߂܂������A�����ŐH�����ƐH�O���y�ѐH����ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B
�K���I�ɁA��ނ͂��̈����@��ɂ���āA�H�����ƐH�O�y�ѐH����ɕ��ނ���܂��B�H�O�y�ђ�����́A��ނ��̂��̂𖡂키���Ƃ��ړI�̈�ł���A�����̑��݂͕K�{�̂��̂ł͂Ȃ��ƍl�����܂��B�H�O���ɂ̓��L���[�����̓����̍������̂��A�H����ɂ́A�u�����f�[�E�E�C�X�L�[���̏��������p����ꂱ�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�����͌��L���Ŏ�ނ̂������A���킢�����\�ł����ނ���ł��B�u�������𖡂���Ă���B�v�Ǝ����咣���܂��B�ڂ����������̈������Ė��ɂ͉��Ȃ��A�u�܂݂Ȃ��Ŕ������A���킢������B�v�Ƃ��������Ǝv���܂��B���̓u�����f�[����D���ł��B���ẮA����ʂ��L�тȂ��͍̂����i���������Ă��邽�߂Ȃ̂��ƍl���Ă��܂����B�������A���ł́u�u�����f�[�͐H�O�y�ѐH����Ƃ��čœK�Ȏ������A�H�����ł͂Ȃ�����v�Ɨ������Ă��܂��B�ߍ��̃E�C�X�L�[���v�̌������E�C�X�L�[���H�����ɂȂ蓾�Ȃ����Ƃ��ؖ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�H�O�y�ѐH����̏���ʂ͏��Ȃ��̂ł��B�����������́A�H���Ƌ��Ɉ��܂��A�������Ԃ̒����H�����Ȃ̂ł��B
�����̒��ɂ��H�O�y�ѐH����ɕ��ނ��������悢�Ǝv����W������������܂��B������̍��������������ɊY������Ǝv���܂��B���̎��́A���̍���̍������ז����ė����̈������Ė��ɂȂ�Ȃ��̂ł��B�ȒP�Ȃ܂݂ł�������Ɩ�����Ă�肽�����Ȃ̂ł��B�ǂ�Ȃɓm������J���đ������̂��낤���A�Ƒz�����Ȃ��疡����Ă�肽���̂ł��B
�ł́A�u�����f�[�A�E�C�X�L�[�A������̍����������H�����Ƃ��Ĉ���ł͂����Ȃ����A�Ƃ������Ƃł����A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�n�D�i�ł�����B����ŐH�����ɂ͈����������܂��B�Â��͂ł��邾���T������ނ��]�܂����̂ł��B���������Ɩ����������h������܂��̂ŊÂ���ނ͑����ɖ����������������Ă��܂��܂��B���������āA�����̂̏���ʂ��L�тȂ����ƂɂȂ�̂ł��B�����́A���̎�ނƔ�r����ƊÂ��������܂����A����͎_�����������Ȃ����ƂƁA�A�~�m�_�̊ܗL�ʂ��������ƂɋN�����Ă��܂��B�m���Ɉꕔ�ɂ͓����̑����Ì��̂��̂�����܂�����ǂ��B�\�\�P��ޕʂ̃J�����[������A�A���R�[�����P��������̓����̊ܗL�ʂ͐ԃ��C����葽���ł����r�[����菭�Ȃ��̂ł��B
�R�@�u���t���b�V���́v���猩���Ă��鐴���̎��v
�@�H�����ł���Ƃ������_���琴�������N�I�Ȉ����ł���Ǝ咣���Ă����̂ł����A�����ϓ_���琴���̎��v�ɂ��čl���Ă݂܂����B
�i�P�j�����̎��v���ނ̈��
�u���t���b�V���́v�Ƃ����l����ʂ̊p�x���猩��Ɛ����̎��v���ނ̈���������Ă��܂��B�����́A�ē��ɍ���Ȃ��Ɛ\���܂����B�ē��͑����̎�҂ɑ�\�����J�����[�y�ђ`�������ʂɏ����l�ɍD�܂�܂��B���������āA�����͎�Ҍ����̎�ނł͂Ȃ����Ƃ͎����̗��ł��B�����ƊE�̒��ɂ́A�Ⴂ������ނ��ꐶ�������邩��A��`�ɂ���Ď�҂̐��𗣂��h�����ƍl���Ă�����������܂����A�^�₪�c��܂��B���̎����̐����ł͏ē��Ƃ̑����͍ň�������ł��B����܂ł͎�ނ̎��v�̑傫�ȕ�������҂���߂Ă��܂����̂Ť���ɂƂ��Ă͐����̎��v�����ނ��邱�Ƃ͎��R�Ȃ��ƂɎv����̂ł��B
�������A�������g�⓯���̒����N�Ӓ芯�̊ώ@����A��ނɊւ���n�D���N��Ƌ��ɕω�����悤�Ɋ����Ă��܂��B�Ⴂ���́A�����Ɋ֘A�����d�������Ă���̂ɐ����D���́A�����鐴��}�ł͂���܂���ł����B���S�A�x������v��������܂������A�ŋ߂͌����ɐ���}�ɕϐg���܂����B�ʂɓw�͂����킯�ł͂���܂��A����ɂ��A�H���Ɋւ���n�D���傫���ω��������߂ł���ƍl�����܂��B����ɕK�v�ȃJ�����[�����������u�m�H�v������{�I�ȗ����ɉ�A�����̂ł��傤�B�m���ɁA���̗������D���ł����A���̎��͐ԃ��C�������ނ��Ƃ�����܂����A�قƂ�ǂ������Ƀ}�b�`�����H�����D��Ŏ���Ă��܂��B�g�K���h�A���ꂩ����{�͍���Љ���}���A���{�I�ȗ������D�ސl���͑��������܂��B���ꂩ��̓��{�̐l���\���͐��������ɂȂ�A�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ƍl���܂��B�Ȃ�قǁA��l������̎�ނ̏���ʂ���҂قǑ����͂Ȃ��Ǝv���܂����A�����Ƒ����̗ǂ��H����I������l���͊m���ɑ�������̂ł��B���ꂩ�琴���̐�`������Ȃ璆���N�����Ƃ��ׂ��ł��傤�B����Љ���}���A�����ƊE�̖����͖��邢���̂Ɋ�������̂ł����B
�i�Q�j�ꖕ�̕s��
�������A���Ƃ��Đ������v�̏����ɕs���������邱�Ƃ�����܂��B��N�w�𒆐S�Ƃ��ăt�@�[�X�g�t�[�h���D�܂�Ă��邩��ł��B
�Ĕт���H�Ƃ��Ă�����{�l�̐H���̎���������ƁA���̂��������тƂ������������ō������킹�Ė���A������Ă��܂��B���̂悤�ȐH���̕��@�ł��ƁA���R�ɁA�H�i�̑g�ݍ��킹����ǂ�Ȗ��킢�ɂȂ邩�A�z�����Ȃ���H�������Ă���͂��ł��B��U���Ɍ����A���{�l�͐H�i�̍����ɂ�閡�𐄎@���A��莩���̍D�݂ɍ��������o��Nj����Ȃ���H��������Ă���A�Ƃ������܂��B���̗l�ɖ��o�Z���T�[����g���Ȃ���H�������Ă��܂�����A�Ă���H�Ƃ�����{�l�̖��o�Z���T�[�͂��Ȃ蔭�B���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B���o�̔��B�������{�l������W���킵�������̖��킢�������ł���A�����l���Ă��܂��B
���̂��Ƃ��ؖ����邩�̂悤�ɁA���ẮA���{�l�ɖ��ӂ͂��Ȃ��ƌ����Ă��܂����B�������A�ŋ߂̎�҂̐H�i�ɑ���n�D���ώ@���Ă���ƐS�z�ł��B���킢�����I�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�܂�A�t�@�[�X�g�t�[�h�̂悤�ɂ��łɖ��̊��������H�i�𑽂��H���Ă��邩��ł��B���̂悤�ȐH���ł͌����Ŏ����D�݂̖��͑���o���܂���B�ł�����A��҂̖��o�̃Z���T�[�̊��x�͓݂��Ȃ��Ă���̂ł́A�ƐS�z���Ă��܂��B���{�l���������ɂ�萴���ɉ�A����A�Ɛ\�����̂ł����A�ꖕ�̕s���͂����ɂ���܂��B�Ă���H�Ƃ���҂݂̂��^�̐����̖��������ł���Ǝv���ĂȂ�Ȃ�����ł��B���ς�炸�Ă̏���ʂ͒����ᗎ�X���Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��̂ł��B�����̎��v�Ɠ������B
���݁A�����̗A�o�͏����ɐL�тĂ���悤�ł����A�O�q�������R����A�߂������A�A�o�ʂ͓݉�����A�O�a����Ǝv���Ă��������ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ݖ����A�C�O�Œ������Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����A���{�H���u�[���ł���Ƃ����Ă��A�ĔѐH�����E��Ȋ�����Ƃ͓���v���܂���B�ĔѐH�Ȃ����Đ����Ȃ��ł�������͓��{�����̈ꗃ��S���Ă���̂ł��B��������{�H��A�o����Ƃ������Ƃ͓��{�����̗A�o�ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B������Ă��鐴���͐H�����ł͂Ȃ�����̍���������������ƕ����Ă���܂��B�܂��܂��A�A�o���{�i�I�ɐL�т�ɂ͎��Ԃ�������ł��傤�B�����萴���ƊE�́A�����ɖڂ�������ׂ��ł��B���{����������Ȃ������Ă�������\�l�����ꉭ�l�͂���̂ł�����B���E�I�Ɍ��Ă����{�Ƃ����s��͋���Ȃ̂ł��B
�i�R�j�������v�̐ϋɓI�Ȋ��N�̂��߂�
�ϋɓI�ɐ����̎��v�����N���邽�߂ɂ́A���̐����̎�����ς��ďē��ɓK�������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��Ƃ́A�O�q�����u���t���b�V���́v���l������������������邱�ƂƎv���܂��B��Ҍ����Ɉʼn_�ɐ�`���Ă���p�̖��ʂ��Ǝv���܂��B���̐����́u�W��h���v�ƈꌾ�ŕ\�����������ɓ��ꂳ��Ă��܂��܂����B���������A�u�Â����v�A�u�_���ς����v�A�u�n�����Ă��邩�v�����������J�������ׂ����ƍl���Ă��܂��B�L�[���[�h�́u�ē��ɓK����B�v�ł��B�����ƊE�͂ǂ����̏ē��`�F�[���X�Ƌ��͂��ďē��ɍ����W�������̐������J��K�v������̂ł��B
�܂��A�ʂ̎��_�����Ă���Ƃ���A�����ɍ�����Ҍ����̂܂݂��J�����邱�Ƃł��B�����Ō�ɋΖ������H�c���ɂ͔��������H�i�f�ނ���ꂩ�����Ă��܂��B�ށA������A�Ƃ�Ԃ�A���肽��ہi�āj�A����n�{�Ȃǂł��B���ׂĂ̂��̂��S���I�ɒm���Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂ł����A��������҂��D�ނ悤�ɁA�܂��A�����Ő�����悤�ɍH�v���Ĕ��������܂݂�Ύ�҂𐴎��ɂӂ�������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�p���̓r�[���ނ̔����������܂݂ɂȂ�܂��B�召�̈Ⴂ�͂���܂��������ł��锞������Ƃ܂݂��ł��Ă��܂��B�Ă����i�ɂ���ΐ����̂܂݂ɂȂ�܂����A��y�Ȃ�����i���J�����������̂ł��B
�S�@������]�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�i�P�j������]�����邽�߂̊�{���[��
�ސE�O�̎����A���h�����n��������������ԑ�������́A�u���������������������Ă��������B�v�ł��B�����A���������m�点���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA���ẮA�u�l�Ɍ�������悤�ɐ����ɂ���������A���������Ɗ����鐴���͈�l��l�قȂ�܂����玩���ɂ�����������T�����Ƃ�ړI�̈�Ƃ��Đ������y���ނ悤�ɂ��Ă͂������ł����B�v�Ɠ����Ă��܂����B���́A�����̖��킢���Ɛ\���܂����]��������@�����������Ă�����ɉ���悤�ɂ��Ă��܂��B�����ł͂��̓��e�ɂ��Ă��b���܂��傤�B���͖��ƍ��Ŋy���ނ��̂ł�����A�܂��͖�����B
�����ƊE�ł́A���̕\�����@�ƁA�������������̒�`������Ă��܂��B�����y���ގ��ɗ����͕s�v�Ȃ̂�������܂���B��X�v���t�F�b�V���i���������m���Ă���Ηǂ����Ƃ�������܂��A�����m�ł���Ζ����L�����邱�Ƃւ̈ꏕ�ɂȂ�܂����A�����𑼐l�ɏ��ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B�u���������v�����ŕЂÂ��Ă������̕\�������q�ϓI�ɂł��܂��B�܂�A�����̎����Ɋւ������l�Ƌ��L���邱�Ƃ��ł���̂ł��B���̂��߂̊�{���[����m���Ă����đ��͖����Ǝv���܂��B
��{���[���́A�܂��ƂɊȒP�ł��B�����ɂ́A�Ö��A�_���A�h���A�ꖡ�A�a���A��5�̊�{���i�ܖ��A�S�~�Ɠǂ݂܂��B�j������A�ܖ����ǂ����a���Ă���A�������������ł���A�Ƃ������̂ł��B���a���Ă���Ƃ������Ƃ́A�ܖ��̂�����̖���������ꂸ�A���̑���A���i�R�N�Ɠǂ݂܂��B�j������ƕ\������閡�킢������A����ɁA���ݍ���ɁA��̏ォ��R�N�������Ă䂫�A������������肵�Ă��邱�Ƃ������܂��B�i�R�N�̑���ɁA�u���̔Z����Ёv�ƌ��������t�ŕ\������l������܂��B�j�ނ����A�r�[����Ђ̃L���b�`�t���[�Y�Ɂu�R�N�������Đꂪ�ǂ��B�v�Ƃ����̂�����܂����B���̌��t�́A�ܖ��̒��a���I�݂ɕ\���Ă��āA���ׂĂ̎�ނɁi���₷�ׂĂ̈����ɂƌ����ėǂ���������܂���B�j���Ă͂܂�A�������Ė��ł��B���̃L���b�`�t���[�Y�̃R�N������A�͂���������������Ǝv���܂����A�ꂪ�ǂ��A�Ƃ͂ǂ��������Ƃł��傤���B����́A������Ɏc��Ȃ����Ƃ�\���܂��B�܂�A���̃L���b�`�t���[�Y�́A�����������������ݍ��ނƐ�̏ォ�疡�킢�������Ă䂭���Ƃ�\���Ă��܂��B�����Ă��܂��Ɣ��������������Ȃ�Ǝv���邩������܂��A���킢�����܂ł���̏�Ɏc���Ă���ƈ��ݖO���Ă��܂��̂ł��B���̈���̂��߂ɂ͈��ݍ��ނƓ����ɖ��킢�������Ă���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B���������āA���̃L���b�`�t���[�Y�́u���������āA���������������ł����ݖO�����Ȃ��B������ł������������߂���ł��B�v�ƌ����Ă���̂ł��B���̂悤�Ȏ��肽�����̂ł��B����Ȃ��܂ł��A���荇���������̂ł��B
����A�ܖ������a���Ă��Ȃ��ƁA���_�����������Ƃ��ĕ\������܂��B�Â�����A�_�������Ă���i�_���ς��j�A�h������A�ꂢ�A�a���A�Ȃǂƕ\������܂��B�Â�����A�_���ς��A�h������Ȃǂ́A�ꏏ�ɐH���闿���ɂ���ẮA�D�܂����������鎞������܂��B�������A�ꂢ�Əa���́A�����܂���A��������͈��߂܂���B���ݑ����܂��Ɛ�̏オ�ꂭ�A�܂��́A�a���Ȃ���������܂Ȃ��Ȃ�܂��B������ɂ��܂��Ă��R�N�������邱�Ƃ͂���܂���B
�i�Q�j�ܖ��̊e�_
�C�@�Ö��Ǝ_��
�ŏ��ɁA��̊�{���A�Ö��Ǝ_�����Ɏ��グ�������������Ǝv���܂��B��������ɂ͗��R������̂ł��B�ӊO�Ǝv���邩������܂��A�u�����̊Ðh�v�́A�Ö��Ǝ_���̂Q�̊�{�����琬���Ă��āA�Ö��Ǝ_���̍��Ƃ��ĕ\�������ׂ����̂Ȃ̂ł��B�Ö����Â��̎ړx�ł���͓̂��R�ł����A�����ł͎_�x�i�����ς��j���h���̎ړx�ɂȂ��Ă���̂ł��B�������_������������Ɛh���Ƃ������͎_���ς��Ɗ�����悤�ɂȂ�܂����A�͂�����Ǝ_���ς��Ɗ����钼�O�܂ł͎_���͐h���Ƃ������o�������܂��B��ʓI�ɂ͐����̐h���Ƃ����A���R�[���ɋN�����Ă���ƍl�����Ă��܂������A�C�����K�v�Ȃ̂ł��B
�Ö���悷�鐬���́A�G�L�X���̒��̂Ԃǂ����Ȃǂ̓����ł��B���������āA�G�L�X���������قǐ����͊Â��������A�_����悷�鐬���i���_�A�R�n�N�_�A��_�Ȃǂ̗L�@�_�j�������قǐ����͐h���������܂��B�����̗e��ɋL�ڂ���Ă���ړx�Ƃ��ẮA�Ö��͓��{��x�A�_���͎_�x���p�����܂��B���{��x���������قǁi���{��x�͊Ö��Ƌt��Ⴗ��B�j�A�܂��A�_�x���Ⴂ�قǐ����͊Â��������A���{��x���傫���A�_�x�������قǐ����͐h���������܂��B
�_���ƊÖ����������閡�o�ł��邱�Ƃ�[������������ȒP�Ȏ������Љ�܂��B���ɐ|�𐔓H����A�_���ς���������悤�ɂ����Ƃ���ŏ��X�ɍ�����n�����Ă݂Ă��������B�n�����Ȃ���A������Ă��������B���������Ȃ��Ԃ͎_���ς������ł�������������ʂɒB����Ǝ_���ς����Â����Ȃ��Ȃ�܂��B�Â����_���ς����Ȃ��̂ł����A���̃R�N�������邱�ƂƎv���܂��B���̓_���߂���ƍ��x�͊Â����ǂ�ǂ��Ă䂭�͂��ł��B�Ö��Ǝ_���͂��݂��ɑł����������A�܂��A���̔Z���ɂ��W���Ă��邱�Ƃ��̊��ł���Ǝv���܂��B
�v����ɊÖ������ł͐��m�ɐ����̊Ðh��\���ł��Ȃ��̂ł��B�������������Ƃ��A�����̊Ðh�́A�Ö������Ɛ\���܂����A�G�L�X�������Ō��߂���ƍl���Ă�������Ⴂ�܂����Ⴂ�܂��B���̂悤�Ȍ�������������Ƃ͎��̂悤�ȗ��R���l�����܂��B
�Â��́A�u���������v�ƍ�������邱�Ƃ����X�ɂ��Ă���܂��B�H�������قǖL���ł͂Ȃ������s�풼��́A���ɂ��̌X���������ł������ƍl�����܂��B�܂��ɁA�Â���A���܂��A�Ƃ������ゾ�����悤�ł��B�������Â����ł���Δ��ꂽ����ł����B���̎���̐����́A�Ö����_�������|���Ă���A�Ö������ŊÐh���\���ł������̂Ɛ��@����܂��B�������A���j�I�ɊÐh�̎ړx�Ƃ��ē��{��x�����Łg�Â��h���h��\�����Ă������Ƃ�����ł͂���Ǝv���܂����B���������w�i�̉��ŁA�N�z�̐���}�̈ꕔ�͐����̊Ðh�����{��x�����ŕ\�����Ǝv���Ă�����������\���܂��B
���x�������ɓ��萴���͐h�������čs���܂��B�h������������x�i�s�����i�K�œ��{��x�����ŊÐh��\�����邱�Ƃɖ����������Ă��܂����B�����ŁA���̍��Œ������������i���݂̓Ɨ��s���@�l��ޑ����������j�̌̍����M���m��̃O���[�v���u�Ðh�x�v����A���̐��l���A�������ŕ\�������g�Â��h���̎ړx�h�ƈ�v���邱�Ƃ������ŏؖ����܂����B�Ðh�x�́A�Ö��ɔ�Ⴗ�鐴���̔�d�ɌW�����|�����l�ƁA�_�x�ɌW�����|�����l�̍��Ƃ��ĕ\����܂��B���̎ړx�͂R�O�N�O�Ɋ��ɒ���Ă��܂������L�������ƊE�Z�������̂͂����Q�O�N���炢�ł��傤���B
�������m��͂�����̖��o�̎ړx�Ƃ��āu�Z�W�x�v����܂����B�Z�W�x�́A�����̔Z����\�����邽�߂̎ړx�ł���A�Ðh�x�Ɠ��l�ɁA�Ö��Ǝ_�����\���镪�͒l�ɌW�����|���Ă���Z�o����̂ł����A�Ðh�x�Ƃ͔��ɁA�Ö��̍��Ǝ_���̍��̘a�ŕ\����܂��B���̘a���������ŕ\�������g�Z���h�ƈ�v���邱�Ƃ������ŏؖ����ꂽ�̂ł��B�Ö��Ǝ_���͊Ðh�ł͑��������p�������܂����A�R�N�ƌ����܂��傤���Z���ł͋������Ă���̂ł��B�����P�X�N�x�ɍ��Œ��������������P�ʂł̑S���̐����̊Ðh�x�ƔZ�W�x�����Œ��̃z�[���y�[�W�̒���PDF�t�@�C���P�W�y�[�W�ɕ\������Ă��܂��B�䋻���̕��͉��L�̃A�h���X�Ɉړ����Ă݂Ă��������B�݂Ȃ��W���Ă���s���{���͂ǂ̈ʒu�ɂ���܂����B���������Ă����H�c���̊Ðh�͂��������Â����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����̂ł����B
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/seibun/h19pdf/01.pdf
�Ö��Ǝ_�����A�Ðh�͂��Ƃ��Z�W���S���Ă��萴���̖��킢�ɑ傫���e������d�v�Ȗ��o�ł��邱�Ƃ����킩�肢�������܂����ł��傤���B���̗l�ȗ��R�ŁA������ƍ��ݓ������b�ɂȂ�܂������ŏ��Ɏ��グ�܂����B
���łɊÖ��Ǝ_���̓m���A���R�[�������ł��d�v�ȓ��������Ă��邱�Ƃ����b���Ă����܂��傤�B
�^����������ɂ́A�Â�������~���܂����A�_�̏��Ȃ��Â������̂��̂͑�ʂɂ͈��߂܂���B���ݖO�����Ă��܂��܂��B�_�i�����ς��j������A�̊����������ꂽ��ł����ނ��Ƃ��ł��܂��B�W���[�X���v�������ׂĂ��������B�ʕ��̉��l�ƌ�����A�������Ⓧ�Ȃǂ̃W���[�X�͂߂����ɂ��ڂɂ�����܂���ł��傤�B�����̉ʎ��́A�����Ȃ��Ƃ�����Ǝv���܂����A�_�����Ȃ����ߑ�ʂɈ��߂Ȃ��̂Ŏ��v��������̂ł��B�����ɗD�ꂽ������L���Ă��Ă��_�����Ȃ��ƈ��ݖO���A�H�זO�����邩��ł��B�����ɂ͎_���ς����K�{�Ȃ̂ł��B�����S��u�h�E�͓K���Ɏ_������܂�������������W���[�X���ł��܂��B����ɁA���������W���[�X���ł���Ƃ������Ƃ͔����������ł���K�v�����ł�����܂��B�������A�\�������ł͂���܂���B���ނ����̗�ł��傤���B
�Ö��Ɋ֘A���Ă̘b��Ƃ��āA�����X�̐����̔���𑝂₷���@���ЂƂ��������܂��傤�B���Ȃ̍ŏ��͏����Ì��̐��������̂ł��B�Â����̂͌������肪�ǂ��ł�����A�����������߂܂��B���̂܂܂ł͓����̉e���ŖO�����Ă��܂��\��������܂��̂ŁA�^�C�~���O���v���Đh���̐����ɑւ���̂ł��B�Ⴂ�����Ȃǂ͊Â��܂܂ł��ǂ���������܂��B��l������̈���ʂ͑�����Ǝv���܂��B�������A���炩�ɓ�Ƃ����O���[�v�ɂ͓K�p�ł��܂���̂ł����ӂ��B���̏ꍇ�͍ŏ�����h�������o���ׂ��ł��傤�B���闿���̓��e�ɂ��Ǝv���܂����A�����̏��Ȃ����̕�������ʂ͑����Ȃ�X���������܂��B�����Ŕ��グ�����˂炤�̂ł�����h�����������߂ł��B
�����Ðh�̘b�肩��͂���܂����A�́A�Ƃ��闿��������ʼn�H���Ă��܂����Ƃ���A�r�����琴���̖����ς�������ƂɋC�Â��܂����B��������ɂ��̎|�����₷��Ɛ����ɓ����Ă���܂����B���̒n��ŕ]���̗ǂ�������������ɕς����Ă����̂ł��B���炭�����Ă���A���̗��������p�Ƃ��ꂽ���Ƃ̕ւ�Œm��܂����B���̂悤�ȁu��ւ��v�͖��ł����A���������̊Ì��Ɛh�����g�������邱�Ƃ͗���������̉c�Ɛ��тɌ��т��Ǝv���܂��B�����Đ��̗l�ɐ�������Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�u���{�����̃v���͐����̃v���ł�����B�v�����������E�ɂȂ��Ăق����̂ł��B
���@�ꖡ
���x�́A�u�ꖡ�v���Ƃ肠���܂��傤�B
�ꖡ�́A�r�[���������Ǝ�ނ̖��o�Ƃ��Ă͌����܂��B�����ł��u���������Ă͂Ȃ�Ȃ����v�ł��B����ǂ��A�ꖡ���Ȃ��Ɛ����́u�{�P���v�A�u���̌��݂̂Ȃ��v���݂������̂��Ȃ��A������A�R�N�̂Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����͌ܖ��̒��a�ɂ��R�N������������̂ł������a�̑傫���ɋꖡ���֗^���Ă���̂ł��B�����̋ꖡ�����́A�Ă̒`��������������Đ��������A�~�m�_��y�v�`�h�ł���ƌ����Ă��܂��B�܂��A�ꕔ�̃~�l���������W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ��́A�l���Ă��܂��B
���R�E�ł͋ꖡ��悷����͓̂����ɂƂ��āu�L�Łv�����ł��邱�Ƃ������A�ꖡ�́A�l�ԂɂƂ��Ă��H���Ƃ��Đێ�\���ۂ��肷�閡�o�Ƃ��Ďg�p����Ă������̂ƍl�����܂��B�ꖡ�̂�����̂͐ێ悷�ׂ��炸�A�Ɩ{�\�������悤�ł��B�q���̋ꖡ�ɑ�������͌��������̂�����܂��B�Ƃ��낪���l�ɂȂ�l�X�ȐH�i��ێ悵�o����ς�Ŗ��o�����B���Ă���ƁA�������Ă����ꖡ���A���ɂ́u���v�ɂȂ邱�Ƃ𗝉����܂��B�ꖡ�́A�o�����d�˂邱�ƂŖ{�\�ɑł������āA�u���v�ɂȂ�A�������������������閡�o�ł���Ǝv���܂��B�ꖡ���B�����ɂȂ��Ă��鐴���͗c���Ɍ�������댯������܂����A�ꖡ�����o���\���Ă���r�[���ނ͂܂��������̐S�z���Ȃ��ƒf���ł��܂��B
�����g������d�˂邱�Ƃɂ��r�[���}���琴��}�ɂȂ����̂ł����A���͈������o�����ĊԂ��Ȃ����͐���}�ł����B���̌�A���N���o�ăr�[���}�ɂȂ�̂ł����A���̂��߂ɂ͎��̖��o�ɂ���ω����N�����悤�ł��B����́A�ꖡ�ɑ�����̂ł��B��ނ����ނ悤�ɂȂ��Ă��炭�̓r�[���̋ꖡ�������ʂ��肾�����̂ł����A���鎞����ꖡ��u���Ɗ�����悤�ɕϐg�����̂ł��B�Ƒ����܂ߕt�������̒����F�l����A���Ɠ����悤�Ȗ��o�̕ϑJ���o�������l�����l�����邱�Ƃ��킩��܂����B�݂Ȃ�������o�̕ϑJ���N���Ă��邩�v���N�����Ă݂Ă��������B���������Q�T���܂łɋN�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɂ́A�ꖡ�ɑ��Ă̖��o���ς�炸�A�u���ɂ܂Ŏ���Ȃ��l��������悤�Ɏv���܂��B�Ⴂ�����̐���}�ɂ͂��������������\�����悤�ɂ������܂��B�����͏����ɂƂ��Ĉ��݂₷����ނ̈�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�H�����̒��ł͊Ì��ł����A�e��̃A�~�m�_�������ܗL����Ă��܂��B�Ȃɂ��ꖡ����ނ̒��ł͏��Ȃ��̂ł��B�Ȋw�I�ɏؖ�����Ă���̂��킩��܂��A�告�o�̐��E�ł͐��������ނƔ������ꂢ�ɂȂ�ƌ����Ă��邻���ł��B���{���́u�{�v���Ƃ�u�|�����v�ƌĂ�Ő������������Ă��鏗��������������悤�ł��B
�n�@�a��
�a���ɂ��ẮA��{���Ƃ��Ẳ��l�����X����܂��B���Ȃ݂ɐH�i�̊�{������͊O��Ă��܂��B�����ꖡ�ƈꏏ�ɂ��Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����鎞������܂����A�����ł͓`���P���Ċ�{���Ƃ��ċL�q���܂��B�����̏a�݂́A�a�`�̏a���Ǝ��Ă��܂��B������ʂ�����悤�ȍ�p������܂��B�ꖡ�Ɠ����悤�ɁA�����ł́u���������Ă͂Ȃ�Ȃ����v�ŁA�B�����Ƃ����ׂ����i��L���Ă��܂��B�܂��A�ܖ��̒��a�̑傫���A�R�N�Ɋւ���Ă��邱�Ƃ��ꖡ�Ɨǂ����Ă��܂��B�t�ɋꖡ�Ƃ̑���́A�a�����A�������n������Ǝ���ɉB����Ă����悤�Ɋ�����̂ɑ��A�ꖡ�͏n������Ƒ�������悤�Ɋ�������_�ł��B�o����A�V���̓��́A�a���Ɋւ��錇�_���A�n�����ł͋ꖡ�Ɋւ��錇�_���w�E���邱�Ƃ������Ȃ�悤�Ɏv���܂��B
�t��ɁA���̓~�ɏ������ꂽ�V���̂ł��f����]�����邫������̐R�����߂���A�a���̂��߂ɐオ���ߕt�����~����ɕω������悤�Ɋ����邱�Ƃ���������܂����B�a�`�������Ƃ͒m�炸�������ς��ɖj����v�킸�f���o������̐�̏�̊��o�Ɏ��Ă��܂��B
�a�������̎�̂͏�������܂����A�L�@�_�̈��ł�����_�̊��n�t�����ɂ��܂��Ɛ����̏a����A�z��������Ƃ��납��A���́A�L�@�_�Ɗ֘A������Ɛ������Ă��܂��B
�j�@�h���ƃA���R�[��
��قǁA�h���͎_�����S���Ă��閡�o�Ȃ̂ł��Ƃ����b�����܂������A�ܖ��̒��̐h���́A�A���R�[���́g�h���h���w�������̂ł��B�ł�����A�����̐h���Ƃ����ꍇ�́A�_������̂��̂ƁA�A���R�[������̂��̂ƂQ�����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�Ðh�x���A�A���R�[���x���ɊW���Ă��܂���Q�����킳���Đh�����`�����Ă���Ƃ͍l������̂ł��B���������āA�Q��ނ̐h�����������Ă��邱�ƂɂȂ萴���ƊE�́A�h���Ɋւ��Ė���������Ă���ƌ����܂��B���ɒf�肪�Ȃ���A�h���͎_����̐h�����w���Ă�����̂Ƃ��l���������B�A���R�[���̐h���́A���̎h�����ł���ƍl�����܂��B
���������A�A���R�[���̐h�����A��{���Ƃ��Ă̎��i������̂��Ƃ������Ƃł����A�A���R�[�����������閡�����������邽�߂̕K�{�v���ł���Ǝv���܂�����A��{���Ƃ��ׂ��ł���ƍl���܂��B�i�����I�ɂ��P�T������߂Ă���̂ł�����j�A���R�[���̐h���́A���o�I�ɂ͐V���̎��͍r�X�����Ƃ��Ċ����A�n�����邱�Ƃɂ��}�C���h�Ȋ����ɕω����Ă��܂��B�n���ɂ����������ɊW���Ă���Ǝv���܂��B
�����̎��v��������Ă��錻�݂ł́A�V���i�Ƃ��ăA���R�[���x����}�����g��Z�x���h���b��ɂȂ�܂��B�������Ȃ��ƂɃA���R�[���́A�����ƊE�̌����҂Ȃ̂ł��B���������Ɍg����Ă��邷�ׂĂ̋Z�p�҂��u��Z�x���̊J�����������Ă���B�v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�������A�s�ꂩ��]�����Ă����Z�x���͂ق�̈ꈬ��ɂ����܂���B������j�b�`���i�ł��B���W���[���i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B�����̃A���R�[���x���͂P�T�����ł��K���Ă���Ɗ����Ă��邩��ł��B�P�R�������̐����́A�����Ƃ͈قȂ����W�������̎�ނ̂悤�Ɏv���܂����A�����A���R�[���x���̎������ނ̂ł���ΐ����ȊO�̎�ނ�I���������������x�͍����Ǝv���܂��B�P�R�������̐����ł͑��̎�ނɁu���������v�ŕ�����A�Ǝv���܂��B�e��ނɂ͍ł����ӂȃA���R�[���x���͈̔͂����݂��Ă���悤�Ɋ����܂��B�����ł͂P�T���}�P���ł͂Ȃ����Ƃ����̂����̎��_�ł��B
�i�R�j���Ɛ����̊W
���́A�ܖ��ȊO�Ő����̖��ɉe����^���Ă��閡�o������܂��B�u�����v�ł��B�u���͐H��̏��v�Ƃ������t���������ł��傤���B�`���Ō��N�ɂ��Ę_���A�����̒��́u���͕S��̒��v�̘b�����グ�܂������A�u���͕S��̒��A���͐H��̏��v�ƌq�����Ă���̂ł��B���́A�H�����A�������̒��̏��R�ł���A�H���̂��܂݂������o���A���N�̗v�ł���A���炢�̈Ӗ��ł��傤���B�ǂ����̎�������̐�`�ɁA�����������ꏡ�e�̈���ɐ���������A�����̑Ίp�ɂ���������e�̐��������݂͂��߂�l���B�������̂�����܂����B���ɐ��������܂����Ɍ����܂��B�{���ɉ��͐����ɍ����̂ł��B�g���ɂ̎��̂����ȁh�́g���h�ƌ����Ă������߂��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�H���ێ�ʂ��������Ƃ���A���{�l�͍D�������ƌĂ�܂����A���̍D�������̎��ł��鐴�������ɍ����̂͋ɂ߂Ď��R�Ȃ��ƂƎv���܂��B
���̎��͂�����ƈꖡ����Ȃ��ȁA�Ɗ��������Ɏ����Ă��锢�̐���ق�̏������ɂ��܂��B�������Ă����Ă��̔������i�O���^�~���_�Ȃǂ̎|�����������a����Ă��Ȃ����̂��ǂ��ł��B�j�ɂ����ƐG��Ă��A���̐�[�ɏ�������t�������A�ꖡ����Ȃ��Ɗ��������ɂ��̔���Z�����a���ĉ������S�ɗn��������̂ł��B�������Ă���Ăт��̎��𖡂���Ă݂Ă��������B�����ς�������������܂��B�R�N���������悤�ɁA���̕����L�������悤�Ɋ������܂���ł��傤���B���ɂق�̏�������������ƊÂ�����w���������Ƃ͂����m�̂��ƂƎv���܂��B�����Ɖ����܂��ɂ��Ɖ��̊W�����藧���Ă���悤�Ȃ̂ł��B��قǁA�Ö��Ǝ_�������a����ƊÂ����_���ς����Ȃ��A���̕����c��悤�Ɋ�������Ɛ\���܂������A���Ɩ��Ƃ��d�ˍ��킹�邱�Ƃɂ���Ă��D�܂������ւƓ������A���̐��E�ł͂��̂悤�Ȃ������낢���Ƃ��N�����Ă���悤�ł��B�H�i�̐��E�ł́A�����͊�{���Ƃ��Ď�舵���Ă��܂����A�����̐��E�ł́A���������邱�Ƃ͂ł��܂���̂ʼn��͊�{���ɓ���Ȃ������A�ƍl�����܂����A�����͂����Ă�������͊�{�����̂��̂Ǝv���ĂȂ�܂���B
�������A���𐴎��ɉ����鎞�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B��ɂ͌��ʂ��Ȃ���������܂����A�܂��A���R���ꂷ���Ă��܂����炵����ς��Ĉ��߂܂���B�����łȂ��Ƃ������ɕq���Ȑl�����܂��B�����o���������Ɛ����ɊW����d����̃G�s�\�[�h����Љ�܂��傤�B�������́A�d����m�肦�����Ƃ͑ސE���Ă��ނ�݂Ɍ��\���Ă͂Ȃ�Ȃ��`�����ۂ����Ă���̂ł����A���̌��̏d�v���͊��Ɏ����Ă���Ǝv���܂��̂ł��b���Ă��������ł��傤�B���́A���Ċ̑��Ɛt�����ɕa��œ��@���Ă������Ƃ�����܂��B���̎��́A�ɒ[�Ȍ������������܂����B�s�K���̍K���ŁA���o�͎d���Œb�����Ă��܂�������A�������ꂽ�H��������قǖ��������Ɗ��������Ƃ͂���܂���ł����B�炢���@�������甲���o���Ă�������炭�͌��������H�����Ƃ��Ă��܂����B�����ɍ��h���̗ނ��ɒ[�Ɍ��炵�܂����B����ȐH�����Ƃ��Ă����Ԃ͂�����\�͂����ɍ��܂��Ă����悤�ɋL�����Ă��܂��B����Ȏ��̘b�ł��B
�݂Ȃ���́A�����ɋ��ʐ��x�����������Ƃ����L���ł��傤���B�����́A�����A�ꋉ�y�ѓɃ����N��������Ă���A�����������܂��͈ꋉ�ŏo�ׂ������ꍇ�͊e�n�̍��ŋǂ��J�Â���n����ސR�c��ɂ��̎|��\�������ʐR���ɍ��i���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�i�������ꂽ����̐����͂��ׂēɃ����N����Ă��܂����B�j�R�c��̍��ۂ́A�قƂ�ǂ̕������������̐��тŌ��܂�܂����B���������s���͎̂��ǂ����ŋǂ̊Ӓ芯�Ɛ����̖��ɐ��ʂ������X���s���Ă���܂����B����n����ސR�c��ł̂��Ƃł����A�a�C�̂��A�ł�����\�͂����܂������́A������ς����𐔓_�����u�s���i�v�̔���������܂����B�������ł̕]�����ʂ́A�R�����s�����ψ��̑������Ō��߂��܂��B�s���i�Ɣ��肵���͎̂���l�ł������炻�̎��͍��i���ꋉ�ɂȂ�܂����B���āu������ς����v�̏o�i�҂ׂ܂��ƁA�S�Ă����������o�i����Ă������Ƃ��킩��܂����B�����ƊE�ł͐����Ɖ��̊W�͂قƂ�ǂ̕����m���Ă��܂��B���̎Ђ̏o�גS���҂͂ǂ����Ă��ꋉ�ɍ��i�������������̂ł��傤�B�H���̊ܗL�ʂ͊ȒP�ȕ��͂ő���܂�����A�����N���[���������Ƃ����炠�̎��͎��i�����\��������܂����B�������A�������܂���ł����B�������Ȃ��Ƃ����i����ɒl��������ł������Ǝv��������ł��B�ꋉ�̏��i���o�ׂł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�S�z���āA���̎Ђ̏o�גS���҂͖��ʂȓw�͂������̂ł��B
�@���̂悤�ɁA�H���Ɋւ��銴�x�͐l���ꂼ��ł��B�����ɐH��������ꍇ�͂��ꂮ������~�����Ȃ��悤�ɋC�����Ă��������B
�i�S�j�����̍���
����͐����̓������ł��ǂ��\���܂��B����́A���̐����̎��f����\�����Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�������Ŏ����肵�]������ꍇ�͍��肪�d�v�ȕ]�����ڂɂȂ�܂��B����ȑ�Ȑ����̍���Ȃ̂ł����A���͈���i�K�ł͂��܂�d�_���u����Ă��Ȃ��̂ł��B���Ɋւ��ẮA��ɂ��b���܂����Ƃ����{���Ƃ��Ă̌ܖ����Â�����m������Ă��܂����A����Ɋւ��Ắu��{���v�Ȃ���̂͑��݂��܂���B�����ł��������͓`���I�ɍ���Ɋւ��Ă͌y��������Ȃ��������R������Ǝv���܂��B����͖؉��𐴎��̗e��Ƃ��Ďg�p������Ȃ��������߂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B����^���N���o�ꂷ��ȑO�A�吳�̏��ߍ��܂ł̖؉��̎���́A�Η��ۂƂ��������s�����Ă��܂��L�Q�ۂ��E�ۂ���ړI�ŁA���X�A�����̎������M���Ă���܂����B�t�����X�̃p�X�c�[�������C���̒ቷ�E�ۂ�����y���ȑO�A��������ɂ͂��łɍs�Ȃ��Ă������Ƃ������ɂ���܂��B�N�ɍŒ�P��͉��M���ꂽ�������؉��ɓ�����Ă��܂����B�`�a���h��ꂽ��A�g�����܂ꂽ�؉����g�p���Ă������Ƃ��l�����Ă��A���R�A���ׂĂ̐������؍��Ə̂��鐙�̖̍���ɖ�������Ă������Ƃł��傤�B�����̗��j���n�܂��Ĉȗ��A�����̍���C�R�[�����̖̍��肾�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����^���N�������ƊE�ɓ�������ď��߂Đ���{���̍��肪�y���߂�悤�ɂȂ����ƍl�����܂��B�����āA���a�P�O�N�ɍ���̊v�����N���܂����B�H�c���̐V���i���j�̂���݂��番�����ꂽ�D�ǂȍy�ꂪ�A����U���y��Ƃ��Đ����ƊE�ōL���g�p����n�߂��̂ł��B����܂ł͈ꕔ�̋�����������A�����́A���{�l�̑@�ׂȊ��o�������Ă��Ă�������y���߂���ł͂Ȃ������ƍl�����܂��B���{���̍���͗��j���̂ł��B�����ł��A�������Ĕ����������߂鐴���̍�������ɕ\���ł��錾�t���Ȃ��̂ł��B�����̈���i�K�ł̍���́A������������Ƃ܂������ƌ����ėǂ��قǏd�v������Ă��܂���B����Ɠ����Ɋ�������Ɍ��_���������Ƃ��Ă����\�����������߂邱�Ƃ�����܂��B�m���Ɉꕔ�̈������肪����Ɓg�@�ɕt���h���߂܂��B���悤�Ɉ������ɍ�����d�����Ȃ��`���́A�������Ĉ�������K���ɂ���Ă���悤�ɂ��v���܂����A�܂��A��������Ɍ��ɂ���H�i�̍���ɐ����̂₳�������肪�B����Ă������߂��A�͂��܂��A�H�i�̖��ƂƂ��ɂ��̍���܂ł��������ĂĂ��邽�߂Ȃ̂��A�킩��܂��B������ɂ��܂��Ă��H�����Ƃ��ď����鎞�ɐ����̍���͓�̎��ɂ���Ă���̂ł��B
���̂悤�Ȃ킯�ŁA�s�̎��ɗǂ������鍁��ɂ��ĊȒP�ɐ������A����̘b�Ƃ������܂��B
�C�@�����
�@�����̍���̒��ŗB��D�܂����Ƃ���鍁��ł��B��������`�����Ă����̂́A��������̃G�X�e���⍂���A���R�[���ł���A����炪�ӑR��̂ƂȂ��ĉʎ��p�̍��C��������ɕt�^���Ă��܂��B�����I�ɂȂ�܂����A�听���́A�J�v�����_�G�`���i�����S�l�̍���j��|�_�C�\�A�~���i�o�i�i�l�̍���j�ł��B�J�v�����_�G�`����������̎�̂ɂȂ��Ă�����͍ŋ߂̋�����ŁA�o�C�I�e�N�m���W�[�̐��ʂƂ��Ēa�������y�ꂪ�g����悤�ɂȂ��ďo�����܂����B���̃^�C�v�́A���ɉ₩�ȍ�����������ӕ]��Ƃ��������̃R���N�[���̎���߂Ă��܂����A���́A�n�����ɂ͌����Ă��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�t���b�V������ۂ悤�ɒ������A�������ɂ͗�₵�Ă��̉₩�ȍ���ƁA�_�炩�Ȗ��킢���y���ނׂ��ł���Ɗ����Ă��܂��B����A�|�_�C�\�A�~����������̎�̂ɂȂ��Ă�����́A�ꎞ��O�̊ӕ]��̎���ł��������݂̓J�v�����_�G�`���n�̋�����ɂ��̍��������Ă��܂��B�g����y��͋���X���y��ƌĂ�A����͉₩�ƌ������͑u�₩�Ȋ��������܂��B������̃^�C�v�̋����������������ł��^��������̂͏n���������ł��B�ʏ�͒ቷ�ŏn������邱�Ƃ������̂ł����A���́A�ď�͂Q�O�����炢�ɂ͎������グ�{���̏n����������ׂ��ł���ƍl���܂��B�l�I�ɂ͂��̃^�C�v�̋������L�����������D���ł��B
���@���_�L�i�I�t�t���[�o�[�j
�����̍���́A������̑��͂��ׂČ��_�L�ƌ����Ă������x���Ȃ��Ǝv���܂��B�����ɂ��Ă܂Ƃ߂Đ������܂��B������̍�������y�������ɍs�Ȃ��A�����Ǘ����K�ɍs�Ȃ�ꂽ�Ƃ���Δ������Ȃ�����ł��B
(�C)�V���i�Ђ˂��j
�������n�����邱�Ƃɂ�蔭������n�����ŁA�����Ȃ�ƍ������A�����̘V����A�z�����鍁��ɂȂ�̂ł����A���r���[�ł��ƌ����邱�Ƃ���������ł��B�������x�������ꍇ��A���ĕ��������������Ă��g�p����Ɣ������₷�����Ƃ���A�������ŘV������������ƕ]���_����������܂��B�n�x���i�݂����ߏn�ɂȂ��Ă���Ɣ��肳���̂ł��B�s�̎��ł͎��X�������܂����A�������Ĉ��ނƂ��܂�C�ɂȂ�܂���B�V���͌��_�L�ł����A����}�́A��T�A�V�����C�ɂ��܂���B
���������͂�������Ă���Ă��܂����A�ł����������ɑ��݂���\�g�����Ƃ������n�����Ƃ����L�͂Ȍ��ɂȂ��Ă��܂��B
(��)���L�܂��͂�ߏL
���Ƃ��āA���������ɓ��ꂽ�悤�ȍ���̂��鐴��������܂��B����̌��������͉𖾂���Ă��܂��A���ɂƂ��Ắg�@�ɕt���h�L���ł��̂ŁA�ǂ�Ȃ��炵�����������������ł����̏L����������͈̂��݂�������܂���B�����𐴐������邽���h�����g�����h�߂��邱�Ƃ�����A�����h���̏L���ł���Ƃ���l�����܂����A���̑��ɂ�����������悤�Ɏv���܂��B������k�������Ɋ�����ꍇ�ƁA�����Ɋ܂��Ɋ�����ꍇ�Ƃ�����܂��B
(�n)�؍��܂��͖؍��l�L
����^���N���o������ȑO�̐����͐����ŏ����E�������ꂽ���߂��ׂĂ̐����ɖ؍����������Ɛ��肳��܂��B���́A���܂�D���ł͂���܂��A���D���������������������悤�ł��B�M���Ȃǂ͂��̍�����̈ӂɕt���������̂ŁA���������́A�A���f�q�h�ނł���ƌ����Ă���܂��B�y��̔��y�͂��\���g�����炸���������邤���ɂ���݂�����Ă��܂����ꍇ�ɂ���݂��甭�����邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���y�͂̋����A�����g�n�̎����g�p�������ɂ������Ȗ؍��������Ɉڍs���邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�́A���ł��C�ɂȂ炸�����������߂܂��B
(��)���V��
�����̐��E���t���b�V���A���h�t���[�e�B������邱�Ƃ�����A��ߋZ�p�̐i�����琴�����ŏo�ׂł���悤�ɂȂ�܂����B��߂ɂ�萴���点��Η��ۂ��h����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł��B
�Γ���E�ۂ��s��Ȃ��ƒ`�������M�ϐ����܂���A�����ł͂������ƍy��R���̍y�f�̊������ۂ���Ă��܂��B���̌��ʁA���𒆂ōy�f�����ɂ��F�X�ȉ��w�ω��������N������邱�ƂɂȂ�܂����A���̈�Ƃ��ăC�\�o�����A���f�q�h�Ə̂���镨�����`������A�Ɠ��̍��C�����ɕt�^���邱�Ƃ�����܂��B���ꂪ���V���Ə̂���鍁��̐��̂ł��B
�����Z�p�҂̊Ԃł́A�C�\�o�����A���f�q�h�̍���͌��_�L�ł����A����҂́A���C�����̈��ł���ƑO�����ɑ����Ă���l���吨���܂��B���������̎s�̐����ɂ��̍��肪����܂��̂ŏ����オ��ۂ͒��ӂ��Ă��ܖ�����������A�ǂ̂悤�ȍ��肩���킩��Ǝv���܂��B�������A������ߋZ�p�ɂ��A�Η��ۂƂƂ��ɂ������ƍy��R���̍y�f�܂ł��������h���Ƃ��Ă��܂��A�܂��������V�����Ȃ�����������܂��B���鎞�A�����ƒʏ�̎���������ׂ�@��ɑ������Ԉ������������Ēp��~�������Ƃ�����܂����B���̎��͐��V�����܂������������Ȃ������̂Œ��J�ɂ�߂����̂ł��낤�ƍl���A�����W�������Ƃ����̂ł����B��߂J�ɂ���Ǝ��̖��������X��������̂ł��B
����ȗ��A���Ȃ��āA����ɂ�邫����\�͌��ޑ�Ƃ��č��h���̐����A��w�̌����y�ѓK��������S�����Ă���̂ł����E�E�E�B
(�z)�c������
�s�̂̐����ł��̂悤�ȍ��肪������͖̂����Ƃ͎v���܂����A���O���ʔ����̂Ŏ��グ�Ă݂܂����B���̗̂R���͒肩�ł͂���܂��A�k���Ɠf���C���Â��قLj����L���A�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��B�_�C�A�Z�`���Ƃ��������������鍁��ł��B����ݒ��ʼn��炩�̌����ŃA���R�[�����y�������ɍs���Ȃ������ꍇ�ɔ������邱�Ƃ�����܂��B�܂��A�������Η��ۂɊ��������s�����ꍇ���������邱�Ƃ�����܂��B������ɂ��܂��Ă����̍���̂��鐴���͐�������o�ׂ܂ł̒i�K�ɏd��ȃ~�X���N�������̂ł��B
�Ȃ��A�H�i�̒��ɂ����[�O���g��ꕔ�̔[���̂悤�Ƀ_�C�A�Z�`�����ܗL���鏤�i������܂��B���Ƀv���[�����[�O���g�̍���́A�c�������ɂ��Ȃ�߂��ł��B
�n�@����̕s�v�c
�����ł́A������Ă͂Ȃ�Ȃ��c��������ł����A�����������ł��郏�C���ɂ͊܂܂�Ă��Ă��]���͉�����܂���B���ۂɍ������C���̒��ɂ́A���ʊܗL���Ă�����̂�����܂��B�������A�r�[���ɂ͐����Ɠ������A������Ă͂Ȃ�Ȃ�����ł��B�ł�����r�[����Ђ͗D�ꂽ�c�������i�_�C�A�Z�`���j���͖@���J�����܂����B�����ł͐����ƊE���g�p�����Ă��������Ă���܂��B���̂悤�Ɏ�ފԂőS���]����������鍁�肪����܂����A�������Ƃ�������ɑ��A�����ƃr�[���̊Ԃɑ��݂��܂��B�����ł́A�m���������K���ɂȂ��Đ��𒆂Ɏc�������Ɠ����J���Ă����������A�r�[���ł͍D�܂��ǂ��납�A���n�L�ƕ\�����ꌙ����̂ł��B
����Ɋւ���l�Ԃ̊����͕��G�Ȃ̂ł��ˁB���o�ɂ���ؓ�ł͂����Ȃ��Ƃ��낪����܂����A�u���[�`�[�Y�A������A�h���A�A�����i���A����Ɋւ��Ă͘_���Ő����ł��Ȃ������������悤�Ɏv���܂��B�H�i�ȊO�ł́A�����Ȃǂ̒����ɂ��P�̂ł͂Ђǂ����L����������A���̉B�����I�ɏ��ʂ��킦�邱�Ƃ�����ƕ����܂����B�������邱�Ƃł܂��܂����肪�ǂ��Ȃ�̂������ł��B�l�Ԃ̊��o�Ƃ͖{���ɕs�v�c�Ȃ��̂Ȃ̂ł��ˁB
�T�@������
����܂ł͐����̖��ƍ���ɂ��Ă��b���Ă��܂����������ł́A�ǂ̂悤�ɂ���ΐ����𖡂킢�A�]���ł��邩�A�����ƊE�p��ŕ\������u�����v���Ƃ��ł��邩�ɂ��Ă��b���܂��傤�B�������ւ̃`�������W�ł��B
�����������ꍇ�́u�����v�͉p���listen to�ɋ߂��Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�A�����Ă���͉̂��ł͂���܂��A���������Ă���ƁA���X�A�����������Ō�肩���Ă���悤�ȋC�ɂ������鎞������܂��B�L�����Łu�����v�ׂ܂��Ɓu���������߂����ׂ�B�v�A�u���킢���݂�B�v�Ƃ���܂��B�����u�����v�́A���Ɂu���v�������܂����AJIS�̑���ɂ������Ă��Ȃ������������Ȃ̂ŁA�u�����v�ł��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����������܂��B
�i�P�j�������̕��@
���������߂��鐴���̂����������Љ�����܂��傤�B�g�����o�튯�͐�ƕ@�A�����Ėڂł��B�g������́A���������i�`���R�j�ł��B���X�A����������ŐF�̉~���Q�d�ɒ�ɕ`����Ă��邮�����݂��o����܂����A�����������������������̂ł��B�����b�N�X��������ŁA�d�������Ă���悤�ȋC���ɂȂ�܂�����A���̂������݂������ł��B���ۂ̂��������́A�F���S�~���ւ̖ڂɌ����邽�߂��A�P�̖͗l�Ɏ��Ă��邩�炩�ւ̖ڒ����ƌĂ�܂��B�e�ʂ���Q�T�Oml����܂��̂ŁA����������̂T�{���炢�̑傫���ł��傤���B���̂��������ɂV�����炢���������܂��B�c�O�Ȃ����ʉƒ�ɂ͂��������͂���܂���A��������������̃R�b�v�≺���𔒂����ŕ������K���X�R�b�v�ő�p���ĉ������B�v���̐��E�ł́A������̊ӕ]��̂悤�ɐ����̐F�����Ă��������s���ꍇ������܂��B���̎��́A�A���o�[�O���X�Ə̂������ߐF�̃O���X���g�p�����̐F�����ʂł��Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂��B
�C�@����������
�����̐F�����Ă��������B���������ꍇ�́A���o����̏����d�v�ł��B�ő��ɂ��ڂɂ�����܂��A�Ⴆ�Ə̂��Đ��������čႦ�Ă�����̂��ō��ł���ƌ����Ă��܂��B���́A���F���炤�������F���ǂ��ł��B���F�������Ȃ�Ɗ��S���܂���B������p��Ƃ��ẮA�u�F�Z���v�ƕ\�����܂��B�������A�n�����̒��ɂ͉����F��тт����̂�����������Ɗ�����������̂�����܂��B�ň��͊��F�ł��B���̒��ɂ����������n����������Ƃ͎v���܂����ɂ߂Ċ�ł��B�S�������������ꍇ�͂����Ί��F��悵�A����������܂��B�����́A�S���ɒ[�Ɍ����A���R�[�������Ȃ̂ł��B���𒆂̓S���̊ܗL�ʂ͐����P���b�g��������O.�P�����ȉ��i�O.�P�������ȉ��j�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�S���̑����y�������Ƃ����Ă����𐴎��̊�ɂ���ꍇ���֖��p�����������S�ł��B�������A�S�������𒆂ɗn�����ނɂ͎��Ԃ�������܂������֖���g��Ȃ��Ƃ������Ⓐ�q�Ȃ�Ζ��͂���܂���B
�Ⴆ����ԗǂ��ƌ����܂������A�s�̎��ł́A�������ڂɂ��������L�����Ȃ��̂ł��B�����Ⴆ�������̂́A����݂���萴���ɂȂ�������̂Ƃ�����^���N�Ɉړ����ォ��̂��������ł����B�c�O�Ȃ������o�Ƃ��������F�ɕω����Ă��܂����B�_������Ă���̂ł��傤�B�Ⴆ�͒Z���Ȃ̂ł��B�^���悯��Ύ𑠊J���Ȃǂ̋@��ɁA�ł����Ă̐������������ł���ΐႦ�ɏo��邩������܂���B
�{���́A�u�����̐F�����Ċy����ł��������B�v�Ə������������̂ł����A���C���̂悤�ɂ͂����܂���B�����̐F�͊y���ނƂ���܂ł܂����W���Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂩ��D�ǂȏn��������������Ηe������傱����O���X�ɕς��F���y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł��傤���A���͂܂����W�r��ł��B
�F������Ɠ����ɐ����̓x�������m�F���܂��B�����x�����́A���������ɕ`���ꂽ�F���S�~�Ƃ���ɋ��܂ꂽ���������̔�r���犴���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B���݂����Ă��鎞�́A�u�e�����ǂ��v�A�u�Ⴆ�Ă���v�Ȃǂƕ\������܂��B���āA���A�Ɏg�p���鎆�R�b�v�ɐF�~���������Ă�����̂�����܂������A�����̗L���肷�邽�߂Ɏg���Ă����̂ł��傤�B�O���X�ł������x��c���ł��܂��B���̏ꍇ�́A�O���X�ɐ����𒍂��A�Ɩ����������Ƃ��āA�����d�����O���X�ɉ�������̂ł��B�����������ꍇ�́A���������̗��q�Ɍ����U�������H����������Ɗώ@�ł��܂��B���Ȃ̎��ƂŃ`���_�����ۂƂ��ċ�����ꂽ���̂ł��B
�����x���Ⴂ�ꍇ�͌����𐄎@���܂��B�ʏ�A�����̎�̂́A�n�����邱�Ƃɂ�萴�𒆂̒`���������݂Ɍ������ċ��剻���āA�s�n���������̂ł����獬�����Ă���قǁA�܂��́A���H���悭������قǁu�R�N�̂�����v�̉\��������܂��B�������A�ɂ߂ċH�ɉΗ��ۂ��ɐB�����ꍇ������܂��B�Η��ۂ����B���������́A�c������������Ă�����A�_�x�������Ȃ�_���ς���������悤�ɂȂ�܂��̂ŁA���̓_�ɒ��ӂ��č����������Ă��������B���݂́A�������Η����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���̂ŁA�����A�Η��ł���M�d�Ȍo�������ꂽ���ƂɂȂ�܂����A�w���������X�ɐ\���o�Ď��͎��ւ��Ă��������ׂ��ł��B
�i�O�̂��ߐ\���グ�܂����A���i�R���Z�v�g�Ƃ��Ĕ����ɂ��点������������܂����A���̎�̎��̏ꍇ�͑O�q�̂��Ƃ͓��Ă͂܂�܂���B�j
���@�㗧������k���i�g�b�v�m�[�g�j
�F�Ɛ����x������]��������́A�������������ɋ߂Â��܂��B�������O�ɐG��钼�O�Ŏ~�߂�Ƃ��傤�ǒ����̏㕔��Ԃɕ@���ʒu���܂�����A���̋�Ԃ̍����k���܂��B���̍�����㗧�����i�g�b�v�m�[�g�j�Ə̂��܂��B�������Ɋ���Ȃ����́A�ʏ�̎s�̐����ł́A�S�n�悢�����F�����邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B��ʂɐ����̍���͒Ⴍ�A��������̂Ȃ̂ł��B�ł����獁��������Ȃ��Ƃ��ߊς��Ȃ��ł��������B�����s�̐����̓x�ɂP�O�O�_���炢�����܂������A���肪�Ⴍ�ĂQ�O�_���炢�͓K�ɕ\���ł��܂���ł����B��ɋL�q�������_�L�������Ȃ������̓_�ł͍��i�ł���Ɣ��f���Ă��������B
�������A�������ƕ\�����Ă��鏤�i�́A�������L���Ă���͂��ł�����T���Ă��������B�������Ə̂��Ȃ����������R�������������\����܂��B���̏ꍇ�́A���C�̓łł����A����Ɋւ��Ă͊O�ꂽ�A�ƍl���Ă��������B
�V���͌��_�Ȃ̂ł����A����Ȋ������Ȃ���Ε]���������Ȃ��ł��������B���������Ĉ��ގ��͋C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��B
�܂��A�����ŁA�Ɠ��̍����������ꂽ�炻��͐��V���ł��B���������Ȋ������Ȃ���ΐ����̍���Ƃ��ĕ]�����Ă��������B
���́A���̒i�K�ŁA�ߋ��ɖ�������������玗���悤�Ȑ�����I�яo�������ɓ����O�ɂ��炩���߂ǂ̂悤�Ȗ��킢�ł��邩�z�����Ă���悤�ł��B��́A������悤�Ɏv���܂����A�ӊO�Ȏ�������܂��B�㗧������k�����ƂƏ��Ζʂ̐l�Ƃ�����邱�ƂƂ͎��Ă���Ƃ��낪����܂��B�܂�A�㗧�����͐l�ԂŌ����Α���ۂɑ�������̂ł��傤�B
�㗧�����̂�����p��Ƃ��ẮA�u������v�A�u�V���v�A�u���L�v�A�u�؍��v�A�u���V���v�A�u�c�������v�Ȃǂ�����܂����A�����́A���ɐ�������܂ݍ��̗p��Ƃ��Ă��g���܂��B
�n�@���Ɗ܂ݍ�
������m�F�����琴���������ɓ���Ă��������B�����̋��ȏ��ɂ͂Tml���܂ނ悤�ɋL�q���Ă���܂��B���x�͂���܂����A��������܂����ǂ����킦�܂��B�������A���o�̔�J���������Ȃ�܂����犵�ꂽ��ł��邾�����Ȃ����ׂ��ł��B�܂�A��C���z�����ݐ������̏�ɖ��ՂȂ��L���Ă��܂��B���̂Ƃ��Y���Y���ƕs���ȉ������܂����C�ɂ��Ȃ��ł��������B�z������C�͕@�ɔ�����悤�ɂ��܂��B�������̏�ɍL���闝�R�́A�ܖ���������̈悪��̏�ŁA�Ö��͐�A�ꖡ�͉��A�h���͗����̐�[�A�_���͗����ł����A�a���͗����S�̂ɋ敪����Ă��Ė��Ȃ��L���Ȃ��ƌܖ���K�Ɋ������Ȃ�����ł��B�L���Ȃ���ܖ��𖡂���Ă��������B�ܖ��̂ǂ�������Ȃ���Β��a���Ă���ǂ������Ɣ��f���܂��B���������������Ă���͂��ł��B�ܖ��̂����ꂩ���������ꍇ�́A���̖��̂��߂Ƀo�����X������Ă���Ɣ��f���܂��B�������A�Ö��Ǝ_���������Ɗ�����ꂽ���͕]�����ɒ[�ɉ����Ȃ��ł��������B�����Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��������������オ���ꍇ�����邩��ł��B���́A���a���Ă���Ɣ��f�������́u���ꂢ�v�ƕ\�����܂��B���ꂢ�̒��ɂ��_�炩���������鎞�́u�_�炩���v��u�\�t�g�v�ƕ\�����邱�Ƃ�����܂��B�u���ꂢ�v����ʂɃ����N�t���������Ƃ��Ӗ����܂��B�ܖ��ɕs���a�����������́A�u�Â����v�A�u�_�����v�A�u�ꂢ�v�A�u�a���v�ȂǁA�s���a��\�����܂��B�܂��A�ܖ��̂ǂ�Ƃ͓���͂ł��Ȃ�����ǂ��ז��Ȗ�������ꍇ�́A�u�G���v�ƕ\���������N�������܂��B���́u�G���v�͕s���a��\�����鎞�ɂ͕֗��Ȍ��t�ł����A�ꂢ�̂��A�a���̂����̉�͓I�ȕ\���ł͂Ȃ��̂ő��p���ׂ��ł͂Ȃ��̂ł����A���x�̐�������N�ԍۂ͂悭�g���Ă��܂����B
��̏�ł̔��f���I������A�����̍���������܂��B�i���ۂ́A�������Ɋ����Ă���͂��ł����B�j�������̏�S�̂ɍL���邽�߂ɋ�C���z�����ݕ@����o���܂������A���̎��̍����k���̂ł��B������������܂��͊܂ݍ��Ə̂��܂��B����͋��ȏ��I�\���ł���A�����M�́A��������Ă��܂���B�s��p�Ȃ̂ŋz������C��@�Ɏ����čs�������A���܂��k���Ȃ��̂ł��B�������A�����Ŕ������Ă��鍁��͉��ƂȂ��k�����Ƃ��ł���悤�ł��B�܂ݍ��́A�㗧���������肵�Ēm�o�ł��܂��B�㗧���������܂芴���Ȃ������������܂ݍ��ł��̌���F���ł���Ǝv���܂��B�����̉t�����Ⴂ�Ƃǂ����Ă��㗧�����͒Ⴍ�������Ă��܂��܂����A�܂ݍ��̏ꍇ�͌����Ő����̉��x���オ��܂�����B���������s�����̎��̉��x�ŕ]�����ʂ��ς�邱�Ƃ�����܂��B�����r����ꍇ�͓������x�ŁA������Q�O���t�߂ōs���ׂ��ł��B����́A�����̎��f����[�I�ɕ\�����Ƃ�����܂��̂ŁA��������A�����Ă���Ă��������B���́A���̐����͂ǂ̂悤�ɑ����āA�ǂ̂悤�ɒ������ꍡ�����ɂ���̂��z�����܂��B
���ƍ����]��������������琴����r�o�����܂��傤�B�����́A�r�[���̂悤�ɍA������]�����܂���A�f���o���Ă��ǂ��ł����A���ݍ���ł��ł��B��������̐����������ꍇ�͂�ނ������f���o���܂��B
�j�@�㖡
���o���������Ƃ���ŁA�u�㖡�̐�v������Ɛ\���܂����B��̏ォ�琴�����������������x�A��̏�Ɏc���Ă��閡�o��T���Ă��������B�����c���Ă��Ȃ���u�㖡�̐�v���ǂ������ł��B�P�Ɂu�ꂪ�ǂ��v�ƕ\������ꍇ������܂��B��ɉ����c���Ă��Ȃ��̂Ŏ��Ɏ������Ɋ܂�ł��ŏ��̊������߂��Ă��܂��B���̂悤�Ȑ����͈��݉߂��Ȃ��悤�ɗp�S���K�v�ł��B���炩�̖����c���Ă���Ƃ��́A������p��Ƃ��ẮA�u�㖡�c��v�Ȃǂŕ\�����܂��B�Ⴆ�ꖡ���킸���Ɏc��Ƃ��܂��B���̎��͈��ݐi�߂Ă䂭�����Ɍ������ꂭ�Ȃ���߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ł��B���̂悤�ɂ������͏��ʂ̎��ő�ʂɈ���̌�����z�������̕]�����s�����Ƃ���̖ړI�ɂ��Ă���̂ł��B���̂��߂Ɂu�㖡�v����Ȃ̂ł��B
��A�̎���A�����Ă����ꍇ�́A���O�̎��̉e�����Ȃ��悤�ɑ��t�Ő��悤�ɂ��Ă��܂��B�悭�A���ł����������Ȃ��炫�������s���Ă���l�����܂����A���t�Ő悤�ɂ��Ȃ��ƕ]�����ʂ�����Ă��܂����ꂪ����܂��B���Ȃ݂ɂ����𒆁A���ł�������������Ƃ͋��܂���B��x�ɂ�������̎��������ꍇ�́A�T�O�_���炢��ڈ��ɁA�������̓r���Ő㒼���ɂ����������������t���b�V�����Ă��܂��B�����̑��ɁA�������ŗ��A���z���A�ʕ��Ȃǂ��o����܂����A�ł��邾���H�ׂȂ��悤�ɂ��Ă��܂��B�H�ׂ��O��Ŏ��̕]�����ς���Ă��܂��悤�ŐS�z�Ȃ̂ł��B
�z�@�����̂������̓����i�_�ߌ��t�����Ȃ��B�j
�ȏ�ł������̕��@�̐������I���܂����A���ގ��͂���قǏڍׂɂ����K�v�͖����Ǝv���܂��B�y����ł���������Ǝv���܂��B�������A���������Ɋ�����������A�t�Ɍ��ɍ���Ȃ��������͂��̗��R��\���ł���悤�ɂȂ��Ă����������낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���āA������p��̒��Ɏ���_�߂錾�t�����Ȃ����Ƃɂ��C�Â��ł��傤���B���C���̐��E�ł́A�����ɔ����������������������S���Ă�����X����������Ⴂ�܂��B�\�����G����ł��B����܂ł͐����̐��E�ɂ̓\�����G�͂��܂���ł�������A�Z�p�҂̕]�����X�g���[�g�ɏ���҂ɕ������Ă��܂����B���ʋƊE�̊W�҂���́A�������������Ȃ�悤�ɂ������̌��ʂ�\�����Ăق����Ɨv�����ꑱ���܂����B�������A��X�Z�p�҂́A�����̌��_�������悤�Ƃ��Ă��������܂�����ǂ����Ă����_��\�����t�̗���ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�������Ō��_���������N�x�̎�ɐ���������A�o���̂�߂Ō��_���C�����悤�ƍl���Ă��邩��Ȃ̂ł��B�������A�����g�������������̎��������\��������ǂ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂����B�ߍ��͏��X�ɂ��̕����ł������̌��ʂ�\������悤�ɂȂ��Ă��Ă���܂��B
�܂��A�����ł͈��̎��i��L����u�����v��u�������t�v�Ƃ�������ΐ����̃\�����G����Ƃ����ׂ����X�����������悤�ɂȂ�܂����B�����̎��v�J��ɂ����̕��X�̂���������҂��������̂ł��B
�i�Q�j���ƍ���̐��E�ւ̂��U��
���������\�͂��l������Ƃǂ̂悤�Ȑ��E���J����̂ł��傤���B���́A���o����o�y�ѐG�o�Ɠ����悤�ɖ��o�ƚk�o���s�q�ɂ��邱�Ƃɂ��A������H���̍ۂ̉���������ɍ��߂���ƍl���܂��B�����g�̂��Ƃŋ��k�ł����A�������Ƃ̈�Ƃ��Ă��܂�������A���̐l��菭�����薡�o�ƚk�o���q���ɂȂ����̂ł��傤�A�O�x�̐H�����y�����Ďd������܂���B�H������邱�Ƃ��瑽���̊�������悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B�N�����H���ɂ��u�H�~�v�Ƃ����{�\���������Ă���Ǝv���܂����A���́A���[���u���������v�������K���ȋC���ɐZ���Ă���悤�ȋC�����܂��B���傤�ǃv���̌|�p�Ƃ��A���Ƃ���|�p������X�傫�Ȋ����Ă��邱�ƂƎ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�K���A���o�E�k�o�̐��E�́A�|�p�̐��E�ƈقȂ�v���ƃA�}�̍��͂���قǑ傫������܂���B�ǂȂ��ł�������ƌP����������ɁA���Ȃ��Ƃ������̎��̃��x���܂ł͓��B�ł���Ǝv���܂��B�g���C���Ă݂܂��B���́A�����A���ʂɖ��o�E�L�o�ɗD��Ă����킯�ł͂���܂��A���Œ��ɍ̗p����鎞�ɂ����o�Ɋւ���e�X�g�͂���܂���ł����B�������߂邩�ۂ���q�˂�ꂽ�L���͂���܂����A����́A���݂̗̍p�����ł������悤�ł��B�܂�A���{�l�ł�����ׂĂ̐l�Ԃ��A���������ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B���ĐV�l����W�����Ă������ɂ������̌P���������Ă��܂������A����R�O���A�T�ɂQ�`�R��A�R�����Ԃ��炢�P������ΊӒ芯�Ƃ��Ďg���鉺�n�͌`�������悤�Ɋ����܂����B���ׂP�O�l�قNj��炵�܂������������ڂ�͋��܂���ł����B�����g�̐V�l����ɂ��V�l����͂���܂������A�������̌P���͂���܂���ł����̂ŃI���W���u�g���[�j���O���������܂����B��y�̂������̌��ʂƎ����ōs�����]�����ׂ閈���ł����B�����āA������A�u�킩�����B�v�悤�ȋC�����܂����B����͋l�ߌ��l�ߏ����A���邢�͎Z���̓������u�킩�����B�v�Ƃ��̊��o�Ɏ��Ă����悤�ɋL�����Ă��܂��B��y�̍̓_�ɂ��킹����悤�ɂȂ����Ƃ����킯�ł͂���܂���B�Ȃ�قǁA���ʓI�ɐ�y�Ɠ����悤�ɕ]������悤�ɂȂ�܂������A����́A��y�̕]�����܂˂����킯�ł͂Ȃ���y�Ɠ����\�͂��l���ł����̂ł��B�������A�u�킩�����B�v�Ɗ�����܂ł́A���Ȃ�^���ł����B�ł��Ȃ��Ǝd���ɂȂ�܂���A���l����Ƃ��̕K���ɂȂ������Ƃ���������B�̍ő�̃|�C���g�ł͂Ȃ��������Ɗ����Ă��܂��B
�݂Ȃ�����̖��o���P��������@�Ƃ��Ă����߂ł��邱�Ƃ́A���������ދ@��ƂɁA�ǂ����키���Ƃł��B�����čŌ�܂ŁA���킢�Ȃ������ł������������̂ł��B�����Ԃ�����������A�����̎��𒍕����č����ׁA�ӌ����q�����̂ł��B�킩���Ă��铯�m�ł����瓚�����߂��Ȃ�͂��ł��B�����s���Ă����A�I���W���u�g���[�j���O�́A�A�}�`���A�݂̂Ȃ���ɂ͂ł��Ȃ����k�ł��B
������́A���퐶���ɂ����Ă����o�ƚk�o���ł��邾���g���悤�ɓw�߂邱�Ƃł��B�H���̎��ɂǂ�ȐH�ނ��ǂ̂悤�ɒ��������̂��ȁA���~�͂ǂ����ȁA�Ƃ悭���킢�Ȃ���H������邱�Ƃł��B�O�H���鎞�Ȃǂ͓��ɒ��ӂ��Ė�����Ă��������B��ʂ̕��́A����ŏ\���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�v�́A���H�ɋ����������Ē�������̂��Ɩ��o�E�k�o���s�q�ɂȂ邱�Ƃ�\���グ�����̂ł��B�������Ċ��o���s�q�ɂȂ�Ȃ�قǐH���̓x���Ƃɂ��K�����𖡂킦�܂��B
�k�o�Ɋւ��ẮA�����Ȃǂ̒������s���Ă��钲���t�Ƃ����E�Ƃ�����܂����A���̕��̌����Ă��邱�Ƃ��Q�l�ɂ��Ă��܂����B���̕�����͂�A�u�k�o��b���邽�߂ɂ́A�ł��邾���g�p���邱�Ƃł���A���̏L����k�����ƂȂǂ͗ǂ��P���ɂȂ�B�v�ƋL�q����Ă��܂����B
�������A�P���̕K�v�̖���������������Ⴂ�܂��B�f�l�̕���Ώۂɂ�����������Ȃǂł́A���炩�Ɏ����D�ꂽ������\�͂��������̕����������܂����A���������邱�ƂƂƂ��Ă�������̒��ɂ͎����D�ꂽ���͂�������������͂��ł��B�ł����A������I�m�ɕ]�����邽�߂ɂ͒����Ă��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��o���A�����������܂��B����ɂ��܂��Ă͌�قǂ��b���܂��B
�i�R�j����������������ނ��߂�
�����������ɂł��Ȃ��Ƃ��������������𖡂키���@�͂Ȃ��̂ł��傤���B�����̖{���𖡂키�Ƃ���܂ŋ��߂Ȃ���A�����������������ނ��Ƃ͉\�ł��B���̈���A���ޕ��͋C�ɍH�v���Â炷���Ƃł��B�����̔��������́A�q�ϓI�ɕ]�����������̕��������Ō��߂���킯�ł͂���܂���B�������������Ȃ̂ł��B��i�F��������I�V���C�ɓ����Ă��鎞��z�����Ă��������B���D�̒��ɂ��~�������Ă��āA���ɐ����̓����������Ƃ��������u����Ă��܂��B���̏ł����琴���̒��g�͂ǂ��ł��ǂ��A�Ƃ͐\���܂��A���͋C�����Ŕ����������߂܂��ł��傤�B���������������������]�܂����̂ł����A���炭�A���i�͎����݂̂ŕ]�����鎄�ł��A�E�Ƃ̂��Ƃ͖Y��ĒɈ����Ă��܂������ł��B�܂��A�j���ł���A�������炨�ނ����Ē����������ł���Δ�����������������Ɗm�M���܂��B
���̋Z�p�҂Ƃ��Ă͔F�߂����͂Ȃ��̂ł����A�����͈���������ɕ����邱�Ƃ��x�X����̂ł��B���̂��Ƃ́A�����̔̔��ƂƂ���Ă�����ɂ́A��������Ƃ��������������������Ƃł��B
�i�S�j���̉��x
����������������ނ��߂ɂ͂�������@������܂��B���̉��x�ɗ��ӂ���̂ł��B�����͉������Ĉ��ނƂ������E�̎�ނ̒��ł����قȏK���������Ă��܂��B�������������炨������Ĉ��܂��悤�ɂȂ������킩��܂��A���R�͐����ł��܂��B���������邱�ƂŊ������͑̂����܂�܂����A�Ȃɂ����������̂ł��B�ǂ����Ăł��傤���B�l���������̌��ʂ́A�����̉��x���オ�邱�ƂŁA�ܖ��������銴�o�������݂��Ȃ邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�Ⴆ�A���܂ŏ����ꂢ�Ɗ����Ă������������ɂ��ꖡ�������Ȃ��Ȃ�R�N��������悤�ɂȂ����肷��\��������܂��B
�ʏ�́A�����̉��x�͂S�O�`�T�O�����炢���ł��ǂ��ƌ����܂����A�����ɂ����܂��B���݂ɂ������ɏo������Ƃ��́A�M���ɂ��Ă��炢�܂����A�W��Ȏ��ł������߂����̕������������Ǝv���܂��B�ܖ��̒��a�̂Ƃꂽ��i�Ȑ����قǒႢ���x�Ŗ��키�ׂ��Ȃ̂ł��傤�B������̍����������Ȃǂ́A��������Ƌ�������@�ɂ��܂�����ނ����₵�ď����オ���邱�Ƃ������߂��܂��B�ċG�ɂ̓N�[���[�𗘂����ĔM�������������ł����A���������Ȏ����₵�ď����オ����̈�@���Ƒ����܂��B
�������͒ʏ�Q�O�����炢�ōs���܂��B���̉��x����ԕ]�����₷���Ƃ���Ă��邩��ł��B���炭�A�ܖ��ɑ����o����ԉs�q�ɂȂ鉷�x�Ȃ̂ł��傤�B�������������Ĉ�������邩�炻�̉��x�ł��������s���]�����ׂ����Ƃ����ӌ�������܂��B�������A���x���グ�������̎������s����ɂȂ邱�Ƃ�ܖ��ւ̊��x�̕ω����l����ƂQ�O���t�߂ł��������ׂ��ł���ƍl���܂��B
�i�T�j����}�Ƃ�
�@�����̘b�肪�o���Ƃ���ŏ��������ɊO��܂����A����}�ƌĂ����X�̂��b�����܂��傤�B����܂ő����̐l�Ǝ����ނ��킷�@��Ɍb�܂�Ă��܂����B���̂��߁A���̕��́A�{���ɐ������D���Ȃ̂��A�����U�镑���Ă��邾���Ȃ̂��A�킩��悤�ɂȂ�܂����B���̔��ʕ��@�ɂ������ւ���Ă���̂ł��B���ꂩ�玄���A����}�̔��f��������܂��̂ŁA�����g������}���A�ۂ��A�l���Ă݂Ă��������B
����}������������̎�i���u�����v���D�ނ��ۂ��Ȃ̂ł��B����}���������D�݂܂��B����}�𖼏��Ȃ���u����̍���������v���D�����A�Ƃ�����������܂����A���̕��͋��炭���C���̕�����肨�D���ȕ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ʂ�����قǑ����Ȃ��͂��ł��B����}�́A�w�r�[�h�����J�[�ł��B���́A����}�̒��ł͎ア�����Ǝv���܂����A��ʂ̊�ł̓w�r�[�h�����J�[�ɕ��ނ����Ǝv���܂��B
��V���ɑ��銴���ł��B����}�͘V�������܂�C�ɂ��܂���B�����V���͂ނ���D�܂����Ɗ����鎞������܂��B���������N���o����Î��ɂȂ�ƘV���������Ȃ��ĘV���ɋ߂��Ȃ�A�ނ���A�ǂ�����������������悤�ɂȂ�܂��B�������錴���ƒ��������ɂ���Ď����͑傫���ω����܂����A��ʂɌ����Ă��āA�Ă̒��S���݂̂��g�p���ď������������͒������Ԃ������ق������������������܂��B
��O�͔[�����������Ȃ���������܂��A����}�͏��Ď����������{�������ɋ�����Ă�����x�ɃA���Y�����������D�ނ��Ƃł��B���Ď����D���ȕ��̓w�r�[�h�����J�[�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B���������āA����}�ł͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B���̗��R���ɂ��܂��Ă͌�قǂ��������܂��B
��l�ɐ���}�ł����ݎn�߂̓r�[���ނ������l�������悤�ł��B�u�̂ǂ������B�v�ƌ����܂��傤���A���ꂩ��A���R�[�������ނƂ����V�O�i�����ݒ��ɒm�点��s�ׂł���A�Ɖ��߂��Ă��܂��B�������邱�Ƃɂ��A�ݒ����A���R�[���ɑ��h��p�������A�����Ȃ�Z�������𒍓����鎞�����̂ɗD�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�����܂ߑ����̐���}�͂���Ȉ����s�����Ƃ��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B
�i�U�j�Ӓ芯�Ƒf�l�i�������ɂ�����A���R�[���ϐ��j
��X�Ӓ芯�Ƃ݂Ȃ���Ƃ̂�����\�͂́A���܂荷�������A�Ɛ\���グ�܂����B�������A�݂Ȃ���ƊӒ芯�ł܂������قȂ�Ƃ��낪����܂��B����́A�Ӓ芯�̓A���R�[���Ŗ��o��k�o����Ⴢ��ɂ����A�Ƃ������Ƃł��B�f�l�̕��̏ꍇ�͂���������Ƃ����ɐオ��Ⴢ��Ă��܂��悤�ł��B���𐳊m�ɕ]���ł��邽�߂̍Œ���v�������\�͂́A�u�A���R�[���Ő�ƕ@����Ⴢ��Ȃ��B�v�Ƃ����\�͂ł��B���̂��߂̒b�B���K�v�Ȃ̂�������܂��A�������̌P�����s���Ă���Ύ��R�Ɋl���ł���Ǝv���܂��B�������A�C�y�ɖ��키�ꍇ�͂��̌���ł͂���܂��A����ł��A��Ⴢ��Ȃ��悤�ɂȂ�Ύ��̔����������Ō�܂Ŗ��i���邱�Ƃ��ł��܂��B
�������̌P�����n�߂��V�l������v���N�����ƁA�������̃A���R�[���ϐ��͕��ʂł���Ǝv���Ă����̂ł����T�O�_�قǂ��������됌�������͂��߁A�|�ꂻ���ɂȂ������Ƃ��L�����Ă��܂��B���S�҂̎��ɂ́A������p�̃A���R�[���ϐ��͂قƂ�ǂȂ������̂ł��B���́A�������̕��@�ɂ����܂����P�O�O�_���炢�����������A�]�����ʂ����肵�Ă��܂��B�ŏ��́A���x���ǂ��̂ł����m�C�Y���傫���悤�ł��������ƕ]�����ʂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������̂ł��B�܂��A�L�o�́A���������ɂ͂ނ�����サ�܂��B�������̉��ƐR�����̍T�����͗���Ă��邱�Ƃ������̂ł����A�ŏ��̂����������āA�T�����ɋA���Ă������ɂ́A������O�ɂ͊������Ȃ������T�����̓����������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��邩��ł��B
�ł́A�ǂ̂��炢�̓_�����Č����ǂ��������Ƃ��ł���̂ł��傤���B�V�����]�ƈ��g���A����Ƃ����g�D������܂��ĐV�����o�g�̂قƂ�ǂ̓m��������ɂȂ��Ă����܂��B�����Ŗ��N�A�t�ɂ��̓~�̐V���̂ł��h���������V���ӕ]����J�Â��Ă��܂��B�����P�O�N���P�P�N�������Ǝv���̂ł����R�����Ƃ��ĎQ�������Ă��������܂����B���̎��ɂ������_��������ɂ������ō��_���łV�O�O�_���炢�������ƋL�����Ă��܂��B�o�i�_���́A4�O�O�_���炢�������̂ł����A��ʂQ�O�_���炢�̏��ʕt�����������ōs�����߂P�R�A�Q�R������R�ƐR�����J��Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���R�ł����_�̏ꍇ�́A����ɂ��������s���A���ʂ����߂܂��B���̂悤�ȕ��@�ł��Ɠ������������ƂɂȂ�܂����炫����_�����A�啝�ɏo�i�_�������邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�P�R��Q�R���Ȃǂł́A�͂�����ƌ��_�̂����������܂�����]������̂͊y�ł����A�R�����i�s����ɂꗱ���낢�̎����肪�R����ɕ���ł��܂��B����ɉ����āA�r�R�̂���́A�R�����S�������Ȃ萌������Ԃł����������邱�ƂɂȂ�܂��B���ɓ��ꂽ���͓f���o���܂����A���̔S������A���R�[�����̂̒��ɐZ�����܂����A���������ɋ�C���z�����݂܂��̂ŏ��������A���R�[�����x���璼�ڌ��t���ɋz�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ă���A�킸�������Ȃ������̈Ⴂ�Ŏ��������N��������̂͐h�����̂�����܂��B
�m����������A�ꐶ�����A����ꂽ����������ȏ�Ԃł��������Ď���ł͂Ȃ��̂��ȁA�Ȃǂƍl���܂������A���ɕ��@���Ȃ��̂ł��B���ԓI�ɂ͂P�O�����납�璋�H�����łQ������܂ł��������s�����Ǝv���܂��B���ׂĂ̕]�����I���A�R���̗������߂Ă����l�ɓ��܂������Ɋe�X�̐R���i�K�łǂ̂悤�Ɏ����]�������̂��A�����Ă��������܂����B����i�K�ł͈����]�������Ă����Ȃ��玟�̒i�K�ł͂悢�]�������Ă��Ȃ����S�z�����̂ł��B�i�t�̏ꍇ�́A�R���̉��オ��قnj������̓_���邱�ƂɂȂ�̂ŋ�����܂��B�j���ʂ���������́A�����S�z�����قǁA��_���I�ȍ̓_�͂��Ă��܂���ł����B�������A�S���Ȃ��Ƃ͌�����܂���ł����B�m�����߂�Ȃ����B
���̂悤�ɁA�v���ƃA�}�̍��́A���o�k�o�̃A���R�[���ϐ��ɂ���悤�ł��B���������āA�s�������������u���Ă��Ȃ�����������ɓ����Ă��܂��Ǝ��ǂ��́A���������߂܂���B�����X�ł����畡���̖����̐�����u���Ă��������A����҂��I���ł���悤�ɂ��Ă��������������̂ł��B���Ȃ萌���ς���Ă��s�������͈��߂܂���B
���������̃A���R�[���ϐ��������Ă��Ă��A��������̓_����������������́A���ǂ��c��܂��B�V�����̎����������Ђǂ��r��Ă��y����O�ɂ��Ă��H�~���N���܂���ł����B�����̔S�����A���R�[���ŗn�����ꂽ�����ɂȂ�̂ł��B���������̐����́A���������I���������̃A���R�[������ӂ����Ίo�߂܂����A�����̍r��́u��������v���邱�Ƃ�����܂��B�A���A����������ꍇ�́A�y�[�X�z�����l���Ă����A�����ɔ����Ă����˂Ȃ�܂���B�t��́A�~�G�ɏ��������V���̂ł��h���������ӕ]��e�n�ŊJ�Â���܂��̂ł�����������@������Ȃ�܂��B���ē�������Ċӕ]��̐R�����߂����Ƃ�����܂������A�y�[�X�z�����ԈႦ�A�����ɑS�͓����������ߗ����̂������͖����킩�炸����𒆐S�ɕ]��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����o��������܂��B�L�o�͖��o���͂�����悤�ł��B
�i�V�j�v�����̃v��
�������Ɋ��\�ȊӒ芯�́A�ǂ̂��炢�[�������������Ƃ��ł���̂ł��傤���B�O�q���܂����悤�ɑ�a�����������̎������\�A��������ł͂Ȃ������̂��ȁA�Ǝv���܂�����肪����悤�ł��B���̕��͊Ӓ芯�ł͂Ȃ��A���̎�������̏o�גS���ҁi�`�[�t�u�����_�[�j�ł��B���͉����̑������肵�������o�ׂ���Ă��܂����A�����A�������Ɏ��M�����������́A���Ƃ����ǂ��s�̎��̎����Ƀo���c�L������܂����B�S���ɔ̔����Ă���̂ł������ނȂ������������Ǝv���܂��B�������A��Ђ����ǂ�Ȏ��Ɉ���ł����肵�Ă��܂����B���������Ă����͎̂������ł͂Ȃ������̊Ӓ芯������������z�������Ƃ�����܂����B�ŋ߁A���̎Ђ̋Z�p�ӔC�҂Ƃ��b��������@��܂����̂ŁA���N�̋^������q�˂��܂����B���̕��͂��炭�l���Ă����܂������A���炭����̓`�[�t�u�����_�[�̔\�͂ɂ��̂ł͂Ȃ����A�Ɠ������܂����B���̎�������ł͈��̕r�l�߂ɂ�������̌������u�����h���Ȃ���Ȃ�܂���B�����̌����錴�����u�����h����Ђ̎����ɍ��v�����A�Ȃ����A���̎������ʋƎ҂̎�őS���ɔz������Ă�������ێ����Ă���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�ނ̘b�ł����A�`�[�t�u�����_�[�ɂȂ�ƌ������킸��ςȋ`�����ۂ�����̂������ł��B�������̒��Ǘ��ƕa�ݏオ��̎����s���Ă����悤�ȐH����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����܂ł��Ȃ��ƁA�ψ�Ȏ�����S���̔��ł��Ȃ��̂ł��ˁB�ŋ߂̑��̎����̈��芴���琄�����āA���ł͂���Ȍ������d��������Ă�����������Ȃ��Ƃ����{�ɂQ�O���͂���������̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B
�U�@���ɂ̐���
�����𖡂키���@��������܂����̂Ŕ������������ɂ��ċq�ϓI�ɂ���������������悤�ɂȂ����Ɛ��@���܂��B�����ŁA���l���^���鋆�ɂ̐����͑��݂���̂��A�܂��A�݂�Ƃ���ǂ̂悤�Ȑ����Ȃ̂��l���Ă݂܂��傤�B
�i�P�j
���ɂ̐����͑��݂��Ȃ��H
�����̏����Ɍg���l���ׂĂ����l�Ɉ�����鐴���肽���Ɗ���Ă��܂��B�������A�S�Ă̐l�Ɂu�ق�Ƃ��ɂ��܂��v�Ɗ��������邱�Ƃ��ł�����͂���̂ł��傤���B���b���Ă��܂����ܖ��̒��a�������������̏����ł���Ƃ���Ƃ��Ȃ�ے�I�Ȍ��_�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�ܖ��̊��x���l�ɂ���ĈقȂ邩��ł��B����l�͒��a���Ă���Ɗ����Ă����̐l�͊Â��A�Ƃ��h���Ƃ�������������܂���B���������܂��āA�ܖ��̒��a�C�R�[�����܂����ł͋��ɂ̐����͑��݂������ɖ����̂ł��B
�i�Q�j
�W��h����
�ꕔ�̒W��h�����̒��ɋ��ɂ̐����ɋ߂���������̂ł͂Ȃ��낤���Ɛ��@�ł��܂��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł��B
�h�����邽�߂ɂ́A�Ö����������������Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���̌��ʁA�Î_�̃o�����X������A�����_���ς���������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���x�́A�_�x�����������Ȃ���Ȃ�܂���B����{���̐������ቺ���܂����瓖�R�ꖡ�y�яa���̐��������������Ȃ���Ȃ�܂���B��a���Ĉ��߂Ȃ��Ȃ�܂����硂��̂悤�ɊÖ��̍팸���A�斡�����S�̂̌����ɂȂ���܂��̂ŁA�h�����́A�斡���������Ȃ������ł��邱�Ƃ��킩��܂��B�ꕔ�̒W��h�����́A�斡�������A���Ƃ��Ċ�������Z�x�܂ŒB�����g�B�����h�Ƃ��č�p���Ă�����̂�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��_�ł��܂��B�����������͌ܖ������a���Ă���Ηǂ��̂ł�����A�ܖ����B�����̑O��܂Œቺ�������W��h�����͂قƂ�ǂ̕��ɒ��a������ۂ�^����͂��ł��B���������܂��ċ��ɂ̐����Ƃ��Ă̎��i������Ɛ����ł���킯�ł��B
�������A�W��h�����ɂ��ǂ����Ƃ���͂���܂���B�ܖ��̐��������Ȃ��̂ŁA���Ƃ��́u���܂��v�̓x�������������Ă��܂��̂ł��B�R�N�����Ȃ��̂ł��B���_��\���A���̒W��h�����ł͋��ɂ̐����ƌĂԂɂ̓R�N�̓_�Ŗ�肪���肻���Ȃ̂ł��B
�i�R�j
���ɂ̐����͑��݂���H
�C�@�ӕ]�����
�����̑��肪�I���ɋ߂Â�3�����{����S���e�n�ł��̔N�̐����̂ł��h��������������������̂�������J�Â���܂����A���̑������ӕ]��ƌĂ�Ă��܂��B�ӕ]��́A�����������������Ƃɂ������Z�p�̌����ڎw���ĊJ�Â���Ă��܂����B�n�߂ɊJ�Â����ӕ]��́A��Ђ̋ߗׂɐV�����ł������Ƃ��`����Ӗ������߂Ďs�����P�ʂŊJ�Â������̂ł���A�s�{���P�ʂŊJ�Â����ӕ]��ƂR�`�U���̒P�ʂŊJ�Â����ӕ]��i���ŋǒP�ʂ̊ӕ]��j������ɑ����A�t�̍Ō�̊ӕ]��Ƃ��Ă͓Ɨ��s���@�l��ޑ�������������Â��T���Ɍ��ʂ����J�����S���V���ӕ]��ň�U�t�B�i�[�����}���܂��B
�܂��A�P�O�����납��͐����̎��v�����}����ɓ�����A����҂ɐ������A�s�[������ړI�Ō��P�ʂ̊ӕ]��⍑�ŋǒP�ʂ̊ӕ]��J�Â���Ă��܂��B�����̊ӕ]��I������ƐV���̎d�����n�܂�܂��B�ł�����d�����ԂƉċG�������ƑS���ǂ����Ő����̂�������A�ӕ]��J�Â���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���悤�ɁA�����ƊE�͑��ЂƋ������������̌���ɔM�S�Ȃ̂ł��B
�ӕ]��ւ̏o�i��\�肵�Ă�����͑��̊Ŕ̎��A���Ȃ킿�������ł����瑢��ɓ������Ă͓m���_�Ƃ��鑠�l�W�c�́A��v�c�������܂�ڎw���đ�ςȓw�͂��������܂��B�ӕ]����܂́A��������̖��_����łȂ��m���①�l�̌M�݂͂����Ȃ��̂ł����A�ނ�̒����ɂ��ӕ]��̐��т����f���邱�Ƃ�����̂ł��B�����ɖ��������ȏ�f�Ƃ������Ă������Ƃ��āA����������ɐQ�H��Y��A���Ƃ���݂̊Ǘ��ɐ_�o�����茸�炵����A���l�S���̌����̓w�̖͂��ɂł��オ��������͐��Ɍ|�p�i�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̍���́A�₩�ʼnʎ���A�z�����A���킢�͏_�炩�ł����܂ł����炩�ł��B�ł����琴���Z�p�҂ɋ��ɂ̐����́A�Ɩ₦�Α���̐l���ӕ]��œ��܂���������Ɠ�����ł��傤�B
�������A�ӕ]��������ܖ��̗��_�ɂ͏��ĂȂ��̂ł��B�Ȃ�قǁA�Ӓ芯���тɊӕ]��̕]���ψ��S���ɂƂ��Ă͋��ɂ̐�����������Ȃ��A�������A�ܖ��ɑ��銴�x���قȂ��ʂ̕��������悤�ɋ��ɂ̐����Ɗ�������̂ł��傤���A�Ɩ���Ă��܂��ƕԓ��ɋ�����̂ł��B
���@�l�Ԃ̖��o�ɂ͑卷������
�����̊�{�����_����l�ɂ���{���̊��x���قȂ邩�疜�l���鐴���͑��݂��Ȃ����A�W��h�������S�N�����s������̂ŋ��ɂ̐����Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��b���܂����B�ł́A���l������A���ɂ̐����͑��݂��Ȃ��̂ł��傤���B�����g�̌o�����狆�ɂ̐����͂���悤�Ɏv���܂��B
�Ӓ芯�͎d���̑啔�������ɊW���Ă��܂��̂ŁA�ǂ������ނ��킵�܂������A���̍D�݂����Ă���̂ł��B���ɂ́A�r�[���}�������̂ł����A�قƂ�ǂ͐���}�ł��B�ŏ��̓r�[������������ŁA���ꂩ�琴���Ɉڍs����Ƃ��������p�^�[�����Ƃ��Ă���l�������̂ł��B��`�I�ɂ�������������Ȃ�Ⴄ�Ǝv���̂ł����A�����̍D�݂͎��Ă��܂��B�Ӓ芯���D�ގ����́A������W��h�����̃W�������ɓ�����ł��B������x�A�������̌P�����d�˂邱�Ƃɂ��ܖ��̊��x�����ʂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����l���Ȃ��ƊӒ芯�̚n�D�����Ă���Ƃ��������͐����ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�������������ʂ��o���悤�ɊӒ芯�͌P������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƌ���ꂻ���ł����A�����ł͂Ȃ����Ƃ͐�قǐ\���グ�܂����B
�Ӓ芯�̚n�D�����Ă���Ƃ����l���𗠑ł����邽�߂ɁA�����������ł��郏�C���̐��E���_�Ԍ��Ă݂܂��傤�B���C���̕]���ړx�́A�t�����X�l�����������̂ł����A�Ӓ芯�S�����^���ł��܂��B�t�����X�l���ō��ł���Ƃ���O�����N�����[�N���X�̃��C���́A�Ӓ芯���ō��ł���ƔF�߂���܂���B�������C���́A��͂肻��Ȃ�̖��ł��B���o�͐l��Ɉ��炸�A����]�����邱�Ƃ�E�Ƃɂ��Ă���l�Ԃł���Ύ��Ɋւ���g�n�D�h�͂���قǕς��Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B�t�����X�̊���m�炸�m�炸�̂����ɍ��荞�܂ꂽ�̂��ƁA���̐߂Ɉ٘_��������Ӓ芯�����܂����A���ɂ͂����͎v���܂���B��͐��܂�Ȃ���ɂ��Ď����Ă��āA�P���ɂ��ڊo�߂���̂Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl����ׂ��ł��B
�܂��A���키�Ƃ����s�ׂ͐������ێ����邽�߂̉h�{�f���o�����X�悭�z�����邽�߂̐H���I���s�ׂ̈�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�K�v�ȉh�{�f��������Ɗ����Ȃ����Q��L���Đ��܂ꂽ�l�͐����̉ߒ��Ō��N�ɖ�肪������Ɨ\���ł��܂�����Q�̎����\�́A�S�l�ނɋ��ʂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂悤�ɍl����A���ׂĂ̐l�ɋɏ�Ɗ��������閡�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł���t�����X�ł̓��X�g�����̊i�t�����s���Ă��čL���F�߂��Ă��܂��B���{�ł��]���ǂ�����������́A��͂���҂ɂ�����Ȃ�����������������Ă��܂��B
�l�Ԃ̚n�D�����Ă��邱�Ƃ����i�f�ނł�������ɂƂ��čl���Č��܂��傤�B�H�i�f�ނƂ��Ă̖��́A�قƂ�ǂ̐l�ɍD�܂����̂̈�ł��B�����H�ނł��鑚�~��̋�����܂���̃g���́A�ŏ㋉�ɏグ����H�ނł����A�ǂ���������قǂ悭�`�����ɍ�������Ă��܂��B�H�c���ɂ͗L���Ȕ���n�{������܂����A����n�{�̔��������̓X�[�v�ɂ���A���̂��܂��̌��̓X�[�v�Ɋ܂܂����ł���ƌ����܂��B���́A�ł������̗ǂ��G�l���M�[���ɂȂ�܂��B������l�͂��܂��Ɗ�����̂ł��傤�B���͐H�i�̊�{���ł͂���܂��d�v�Ȃ��܂݂̐����̈�ł���ƍl�����܂��B�́A���́A�����ԑg��ǂ��������Ă��܂����B���Ă���Ƃ₽��Ɩ��𑽗p���闿���l�����܂������A�����̐l�����܂�]���ł��܂���B���𑽗p����Ɩ��̎|���ŗ����̖����������Ă��܂����A��߂����͂ƂĂ��H�ׂ��Ȃ������ɂȂ�\��������܂�����B�a�C�������Ō�����������ꂽ���ɁA�Ō�w����h�{�w��������A�������炢���͖��𑽗p����悤�Ɋ��߂��܂����B���̔�����������̔��������ő�ւ��Ȃ����ƌ������Ƃ������̂ł��B�K���A���ɂ͕K�v����܂���ł������A����ǂ��ۂ鉢�Đl�́A���̐ێ�ʂ����Ȃ��A���̐ێ�ʂ̏��Ȃ����{�l���D�������ƌĂ��ɂ͂���Ȃ�̗��R�����݂���̂��Ɗ����܂����B���X�A�����Z�x�������A���������Ղ�������������������܂��B���[�����Ȃǂɂ����̎�̌X�����������܂��B���������̂ł����A���������l�̘r�͂ǂ��ɔ�������Ă���̂ł��傤���B
�܂��A�|���������g�̂ɕK�{�Ȑ����ł��B�C�m�V���_�͈�`�q�̌����ɂȂ鎑�i������܂����A�O���^�~���_�́A�`�����̌����ł���Ɠ����ɔ]���ŏ��`�B�ɂ��ւ��K�{�A�~�m�_�̈�ł��B�ǂ�����l�ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł��B�������ܗL����H�i���D��Őێ悷��悤�ɉ�X�̓v���O���~���O����Ă���̂ł��傤�B������Ƃ��Ė��Ɠ��l�Ɏ|���������L���ł���Ƌ������܂����B�_�V�������Ă���Ό����ł���̂ł��B
�ʂ̊p�x������l�Ԃ̐H�i�ɑ���n�D�����Ă��邱�Ƃ������ł��܂��B�~�g�R���h���A�E�C�u�ƌ������t������܂��B�������̂悤�ɃC�u�Ƃ͋����̒��ɂ���l�ލŏ��̏����ł��B�~�g�R���h���A�́A�זE���̒��ɕ����Ă��Ď�Ƃ��čזE�̃G�l���M�[���ł���`�s�o�i�A�f�m�V���O�ӎ_�j�̐����Ɋւ���Ă���d�v�Ȉ�`�q�ł��B�זE�j�̈�`�q�͗��e����p���܂����A�~�g�R���h���A�͗��q����̂ݎp���܂��B���������āA�~�g�R���h���A�����ǂ�Ɛl�ދ��ʂ̕�e�ɍs��������̂ł��B���݂́A�A�t���J�̈�l�̏����ɂ��ǂ蒅���Ƃ����̂������Ƃ��L�͂Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��B��l�̕�e���������Ă��Ȃ��l�ނ��ǂ����Ė��o�����ɑ��l�������Ă�̂ł��傤���B��`�I�ɂ́A�l�ނ̖��o�̑��l���͔ے肳��Ă���ƍl����ׂ��ł��B
���������āA���o�E�L�o��b�����l�ԂɂƂ��Ă͋��ʂ̔��������A�܂�A�u���ɂ̐����v�͑��݂��邩������Ȃ��̂ł��B����A�͂�����Ƒ��݂���ƌ��_�������܂��傤�B�l�́A�����ܖ��̊��x�͈قȂ邪�A�b���グ��Ƃ���قǍ��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�����v���܂��B
�i�S�j���ɂ̐���
���ǁA���ɂ̐����́A�ӕ]��̏o�i���̒��ɑ��݂���̂ł��傤�B�������A���݂̊ӕ]��̏o�i���ł͂Ȃ��A�ꎞ��O�̊ӕ]��ɏo�i���ꂽ�������̃^�C�v�ɒ��ɍ݂�悤�Ɏv���܂��B�Ȃ�قǁA���݂̊ӕ]��ɏo�i�����������́A�₩�ȋ�����ƃt���b�V�����ʼnߋ��̑����������|���嗬�̒n�ʂ�z���܂����B�������A�ő�̌��_�́A�ǂ̂悤�ɒ������Ă������̌��オ�����߂Ȃ����ƂȂ̂ł��B�ǂ����Ă��T���ȉ��̒ቷ�������s��Ȃ��Ƌ����������ĉ₩���������A�t���b�V�������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�n�����Ɍ����Ă��Ȃ��̂ł��B����ɑ��A�ꎞ��O�̑������͏n���ɂ����������サ�܂��B����ɂ͘V�����o�邱�Ƃ�����ł��傤���i�i���������o����Ă���Ǝv���܂��B����薡���܂�₩�ɂȂ�ØI�ƌĂԂɂӂ��킵�����ɕϐg����͂��ł��B�������A�傫�Ȗ��_������܂��B���݂̑������͉₩�ȋ�������o�����Ƃ͂���قǓ�����Ƃł͂���܂��A�ꎞ��O�̑������ł́A���m���̎�ɂ�����Ȃ��Ƒu�₩�ƌ�����قǂ܂ŋ�����������Ă��Ȃ��̂ł��B���������āA���ɂ̐����͓��{�ɂ�������͑��݂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���ɁA���݂̑��������A�ӕ]��o�i���̎嗬�ɂȂ��Ă���Ԃ͋M�d�i�ł��葱����ł��傤�B
���́A���ċ��ɂ̐����ɏo������Ǝv���Ă��܂��B�L�����肩�ł͂Ȃ��̂ł����A�y���V���Ƃق̂��ȋ����������������Î��ł������A���ɓ����Ǝ��R�Ɛ�̏�ōL����A�u���܂��ȁv�u�y���Đオ���̏d���������Ȃ��ȁv�Ǝv���Ă��邤���ɏ����Ă��܂��A����Ȗ��킢�̎��ł����B�����͕s�v�ŁA���̎����������ݑ����邱�Ƃ��ł���A������ł����߂���ł����B�������������߂��A�D���Ȃ������߂܂���ł������A���ꂪ�K���ł����B�����A�D���Ȃ������߂��̂Ȃ炫���ƂЂǂ���������ɂȂ��Ă����ł��傤����B
�������A���̎�̑����n�����ɍ����������v�����Ȃ��̂ł��B���������������͐H�����ł͂Ȃ��̂ł����A�n���ɂ��A��������ˏo���Ȃ��Ȃ�Η����ɂ���Ă͑��������܂�Ă�����̂ƍl����ꂽ�̂ł����P�Ȃ�v�����݂ł����B�ł�����A���ɂ̐����́A�H�����Ƃ͌����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B���������A���́A����ȋM�d�Ȏ��ɏo����Ƃ��ł���̂��^��ł�����ǂ��B
�ł́A�H�����Ƃ��Ă̋��ɂ̐����́A����̂ł��傤���B�����Ƃ̑������l���Ȃ���Ȃ�܂���A�H�����ł͂��ׂĂ̐l��������ƌ����Ƃ���܂ł͓��B�ł��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B���ɂ̐����̈����O�Ƃ������̂ł���A�����ɂ���ĈقȂ��Ă���Ƃ͎v���܂����A�������̎�������ɕ����т܂��B����̊Ӓ芯�����̖����Ɏ^�ӂ�\���Ă���邩���M�͂���܂��A�������������������X�ɑ����Ă���悤�ȋC�����܂��B�݂Ȃ���̐g�߂ɂ������Ƃ���Ǝv���܂��B�h���ł���K�v�͂���܂��W��Ȏ��̒��ɑ��݂���悤�Ɏv���܂��̂ŁA�������ƂɎ����ɍ�������T����Ă͂������ł��傤���B�L�[���[�h�͓�������ł��B�������ł̓�������͘_�O�ł����A�ߋ��ɓ�������ɂȂ������Ɉ����ƁA�ł���Η������A���ׂ�̂ł��B�y�����������ɂЂǂ���������������o����������́A���Ȃ��̋��ɂ̐����ɏ��荇�����̂ł��B
�V�@�����̐h����
�������������������Ă���Ɛ\���グ�܂������A�����͖{���I�Ɏ����W�����邱�Ƃ��ł�����Ȃ̂ł��B�R��ނ̔���������g�����G�ȍH�����o�ď�������܂�����A�����Z�p��ݔ��E�@�B�̔��W�����������コ���܂��B���̓_�́A�����������ł��郏�C���Ƃ͒������قȂ�܂��B���C���́A�����u�h�E�̕i���ɑ傫���ˑ����܂��B�ǂ�Ȃɔ��y�Z�p���i�����Ă��A�����Ԃǂ��������Ă���|�e���V�����ȏ�Ɏ������グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�u�h�E�̂ł����������Ɖ��肷��ƁA�Ԃǂ����Ŋi�t�����Ȃ���Ă���t�����X�̃��C���͂P�O�O�N�O�ƍ����ł���قǖ����ς��Ȃ��Ǝv���܂��B����A�����̎����́A�����P�O�O�N�Ԃő傫���ϑJ���Ă��܂����B���ɁA���߂̂R�O�N�Ԃɋ}���ɐh�������i�s���܂����B�ǂ̂��炢�h�������Ă������Q�l�܂łɍ��Œ����z�[���y�[�W�Œ��Ă��镽���P�X�N�x�̑S���s�̐������ʂ����܂��Ə��a�T�X�N�́[�Q.�S�������S�����ϒl�������P�X�N�x�ɂ́{�R�D�Q�ɂȂ��Ă��܂��B
�ihttp://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/seibun/h19pdf/01.pdf�̂P�S�y�[�W�������������B�j
�R�O�N�Ԃœ��{��x���U�߂��h���ɕω����Ă��܂��B���̂���Ȃɑ傫�ȕω����������̂ł��傤���B�i�{���ł���ΊÐh�̎ړx�Ƃ��ĊÐh�x���g�p���ׂ��ł����A�Â��f�[�^�ɂ͊Ðh�x�������̂ł�ނ����{��x�ŕ\�����܂����B�j
���a�S�O�N��́A�Ì����̑S�����ł����B���ꂩ�炵�炭���Đh�������i�s���܂����A���̓]���_�Ƃ��ē��{�l�̐H�������L���ɂȂ������Ƃ��w�i�ɂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�I���̐H�Ɠ�̎���́A�Ö��Ǝ|������������Ă����ƍl�����܂��B���ꂪ�A�悤�₭���ʂ����悤�ɂȂ萴���̊Â����ۗ����Ă����̂ł��傤�B���̌�A���ʐ��x���p�~����s�̎��ɋ�����⏃�Ď����o�ꂷ��Ƃ���܂ł͓m�������̏����Z�p�̗����̏�Ƃ���Ă����ӕ]����ʋƊE������r���𗁂т邱�ƂɂȂ����̂ł��B������̃u�[�����N�������ƌ����Ă��ǂ��ł��傤�B�h�����̓�����ݎn�߂��������A�W��h�����̑�\�ł���ӕ]��o�i�����i�D�̖ڕW�ɐ������Ƃ��Ă����������͂���܂���B�ł�����A�ӕ]��h�����Ɉ��̖�����S���Ă����ƍl������̂ł��B
�������A���ꂾ���ł́A�h����������ł��܂���B�ł��L�͂Ȑ��́A�h������n�D���鐴���̃w�r�[���[�U�[�ɂ���Ƃ�����̂ł��B�Ö������������������ݑ�����Ƃ�葁�����������N���Ă��܂��A���ݖO�����Ă��܂��܂��̂Ńw�r�[���[�U�[�͊Â��������h������X���ɂ���܂��B�܂��A�����A���ʂɈ�������Ǝ��͊Â�������悤�ɂȂ�A�ƌ����Ă���܂��B����\���ѕɊÂ��Ə����u�Łv�́A���̈ꎚ�Łu�����Ȃ�v�Ɠǂ݂܂��B����ō����ɒB���A���J���ɂ��鎞�ɂ́A�u���łł����A�v�Ƃ悭�\���܂��B�܂�A�����łɂȂ�ƌ������Ƃ́A�����Â���������A�������͏\�����݂܂����A�Ƃ����Ӗ��������Ă���̂ł��B�Q�`�R�S�_���炢�̂������ł���A���ł��Ō�܂Ő��m�ɕ]���ł��鎩�M�͂���܂����A�[�������������v���N�����Ă݂�ƁA�m���ɊÖ������������Ă���悤�ɂ��v���܂��B�����̃w�r�[���[�U�[�͈����̋@��ƂɓK�ʂ���X��������܂�����A���������ޓx�ɐ����͊Â��Ƃ�����ۂ��Ă���̂�������܂���B�����āA���h���̎����]�܂ꂻ��Ɍĉ����Đ����͐h�������Ă����̂ł��傤�B���ۂ̂Ƃ���́A�����̗v���ɉ����A�Ö���ڂ̓G�ɂ��錒�N�u�[����������ʂ������炵�h�����̗���ɔ��Ԃ������������̂Ǝv���܂��B
�������A�h�����ɂ��A����{���̃R�N���]���ɂ��Ă��܂����悤�ɂ������܂��B���̂��߁A�W��h�����������̔̔��ʌ��ނ̈���𐬂��Ă���悤�ɂ��v���܂��B�W��Ƃ́u���킭�A����킵���v�͂��ł����A�ꕔ�Ɂu����킵���v�Ɍ����Ă��āu�����������E�h���v�����̎��ɂȂ��Ă��܂��Ă�����̂�����悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B�킵���͌ܖ��̒��a�����ł͎�������Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B
�������ɋߔN�͐h�����Ƀu���[�L���������Ă���悤�ł����A����Ȃɑ傫���h������i�߂Ă��܂����̂ŁA�R�O�N�O�ɊÌ��̐������������Ē��������[�U�[�̕��X�́A�������痣��Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���������A�����͐H�����Ƃ��Ă͊Â�������L���Ă���̂ł�������Ì��̎����������������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����Ō�ɃT�����[�}�������𑗂����H�c���́A��N�����������H�i�X�[�p�[�̓X���ɒ��悤�Ȃ������̍��ł��B�H�����̍���ɂ����������݂��Ă��Č����̚n�D���Ì��X���̂��߂��A�ق�̂�Â��������������������키���Ƃ��ł��܂����B
�����̏������@�ɂ��Ă͐F�X�ȋ@��ɏЉ��Ă��܂��̂ō��X�Ƃ�������������܂����A�����̂��������s�������Ƒ����܂��B����ƂƂ��ɁA����܂ł������������g�p���Ă��������Ɋւ�����p��������ł܂Ƃ߂Ă������������ƍl���܂����B
�i�P�j
�����̌���
�����́A�������ہA�����y��y�ѓ��_�ۂƂ����R��ނ̔������𗘗p���Ă��Ă��瑢���܂��B��܂��Ȍ����́A���Ă̂ł�Ղ���������ۂ����Y�����y�f�œ������Ԃǂ�����A���̂Ԃǂ������y��ɑ�ӂ����A���R�[���ɕς��Ă����ɂ���A�ƌ������̂ł��B���_�ۂ͗��p����ꍇ�Ƃ��Ȃ��ꍇ������܂��B�ŏ��ɁA�����̔������ɂ��Ă������������܂��B
�C�@��������
�������Ō��܂��Ǝ��̂悤�ȋۑ̂����Ă���̂ŕ��ފw��͎���ۂƌĂ���Q�ɑ����Ă��܂��B�������������Ă��D�ރJ�r�̈��ł��B���݂ɐ�����J�r�Ɏ��Ă��܂��B���Ẳh�{��H�ׂĐ����Ă���킯�ł����A�ۑ̓��ɉh�{����荞�ނ��߂ɂ��Ă̓b��������K�v������܂��B���̂��߂ɋۑ̊O�ɂł�Ղ�����邽�߂̏����y�f��ɕ��o���܂��B���������̉ߒ��ł́A���̏����y�f�̂������ŕĂ���y��̉h�{�ł���A���A���R�[���̌����ł�����Ԃǂ����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�ɁA���Ă�n�����ĂԂǂ����ɂ��邱�Ƃ��Ə̂��܂��B
�������ۂ́A�J�r�ł����獂���������D�݂܂��B�������āi���āj�ɖE�q��U�肩���ĂQ���Ԃ��������i�ނ�j�Ƃ������������̊��ɒu���܂��Ə��Ă̕\�ʂɔɐB���܂��B���ꂪ�������ł��B�ق�̂�Ɖ��F����ттĂ��܂��B�ʖ������������ۂƌ����̂͂��̂��߂ł��B�������A���ɂ͗����邱�Ƃ�����܂��B�E�q��A���̖E�q���ΐF��悷�邽�߂ł��B
���@�y��
���N�r�[�{�[���^�̌`������Ă���A�����̒����͂T��m���x�̑傫���̔������ł��B���肵�đ��B���A�����ɂ��܂����������ݒ��ɂ����ĂP���łQ�`�R�{�ɑ��B����ƌ����Ă��܂��B�h�{���Ƃ��܂��ẮA�Ԃǂ����Ƒ��B���ɋۑ̂邽�߂ɒ`���������ʕK�v�Ƃ��܂��B�Ԃǂ������Ӂi�H�ׂāj���ăA���R�[���ƒY�_�K�X���o���܂��B�����Ɍ��炸���y�ŃA���R�[�������鎞�ɂ͎�̓I�Ȗ������ʂ����܂��B
����p�ɂ�������̍y�ꂪ����܂����A���ʂ̐����Ƃ��āA�@�P�O�����炢�̒ቷ�ł��A���R�[�����y����\�͂������A�A�A���R�[�����y�Ɠ����ɍD�܂�������Y����A�B�_���̊��ɋ����A�C�A���R�[���ɑϐ�������Z�x���Q�O�����炢�܂ŃA���R�[���邱�Ƃ��ł���A���̐����������Ă��܂��B�������A�L�Q�ȍy������݂��܂��B�����ƊE�ł͂�����쐶�y��ƌĂт܂����A���Ƃ��āA���������ݒ��ɕ��ꍞ�ݕs���ȍ���Y������A�A���R�[�����y��x�点���肷����҂ł��B�쐶�y�������ݒ��ɐN�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ������Z�p�̈�ł��B
�n�@���_��
�����ɊW������_�ۂ́A���`�≔�M�̂悤�Ȍ`�����Ă���A�傫���͍y���菬�U��ł��B�y��ƈقȂ�Ԃǂ��������ł͂Ȃ��Ă̓b�������ڐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�傽���Ӑ��Y�������_�Ȃ̂Ŏ_���ɋ����ł����A�y��قǂł͂���܂���B���������ɊW������_�ۂ͎����̐��Y�������_�ɂ���Ď������I����h���ɂ�����̂��قƂ�ǂł��B�A���R�[���ɂ��ϐ��������Ă��܂����A���_�ۂ̈��ł���Η��ۂ́A���ɃA���R�[���ϐ��������܂����A���R�[�����Q�O���ł����B�ł�����̂����݂��܂��B�����y����Q�O���Ő����Ă䂭���Ƃ͂ł��܂����A�ƂĂ����B�܂ł͂ł��܂���B�Η��ۂ̓A���R�[�����h�{�ɂ��Ă��邭�炢�ł�����A�l�Ԃ��܂ߑS�Ă̐����̒��ōł����ɋ����������ƌ����܂��B�傫�ȃn�[�h��������Ƃ͎v���܂����A���̋�������`�q�I�ɉ𖾂����p�ł���A�o�C�I�G�^�m�[���̐��Y�R�X�g��啝�Ɉ��������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ɛ����ł��܂��B
�����̐����H���œ��_�ۂ𗘗p����̂́A���̍H���ł��B���ʂ̔������͎_���Ɏア�̂œ��_�ۂɓ��_�点�đ��̔����������̒��ɐN�����邱�Ƃ�h���̂ł��B���|���g�����H�i�����s���ɂ����̂͂��|�̎_���̂��߂ł����A���ł����������˂���ē��_���g�p����̂ł��B
�������A���_�ۂ���������ݒ��ŔɐB����ƃA���R�[�����y���j�Q���ꂨ���ɂȂ�Ȃ����Ƃ��Ɋ�ɋN����܂����A�Η��ۂ����𒆂ɑ��B����ƁA����܂����|�ɂ��Ă��܂��܂��B���������āA���_�ۂ��A�L�v�Ȃ��̂ƗL�Q�Ȃ��̂Ƃ����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�L�p�ȓ��_�ۂł����Ă���������͍w�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B���_�ۂ͂ǂ��ɂł����܂��̂ő��B���Ă�����𐮂��邾���Ŏ��R�ɐ����Ă��܂��B
�i�Q�j��������
���ɐ����̐����H�������Ԃɐ������܂��B�ŏ��́A���������ł����A�����ł́A�Ȍ�̍H���Ŏg������Ă邱�Ƃ��ړI�ł��B
�����̕ẮA���Ă̂܂܂ł͂ł��������������̖����Z�����܂����A�������ۂ�y��̉h�{���݂�߂��Ĕ��y���}�i�����䂷��̂ɑ�ςȋ�J���������܂����琸�Ă��܂��B�H�p�̔��Ă͐��ĕ����X�O�����炢�ł����A�p�̔��Ă͂U�O�����炢�ɐ��Ă��܂��B�i��́A��H�p���g���܂����A�g���Ղ��͎̂p�D�K�ĂƌĂ����̂Ŏ�H�p�Ɣ�r����ƈꗱ������̏d�����R�����炢�d���嗱�ĂŁA�^���ɐS���ƌĂ������F�̕���������܂��B��ԗL���Ȃ̂����Ɍ��ŊJ�����ꂽ�R�c�тł��B�H�c���ł��R�c�т������������D�ꂽ�H�c�����܂��Ƃ����i����J�����܂�������A���ꂩ��̔��W���y���݂ł��B
���Ă������Ă��Ƃ��ŐZ�Ђ��A�����z�킹�A�����傫�Ȃ�����i�������ƌ����܂��B�j�ŏ����܂��B����ŏ��Ă̂ł�������ł��B���т̂悤�ɐ����̂ł͂���܂���B�ԔтƓ����悤�ɏ������̂ł��B���������ɁA���S�ɎE�ۂ���܂�������Ă͖��ۏ�ԂŊe�H���ɒ���܂��B
�i�R�j��������
���Ă��炱������H�����Ə̂��܂��B�����̖��́A�قƂ�ǂ������Ō��܂�܂����炱�����̑���ł��̑��̎��������肳���ƌ����Ă��悢�ł��傤�B�������A�������Ɛ������������̊Ԃ̊W�͖��m�ɂ͉𖾂���Ă��Ȃ��̂ł��B���͑�����p�̂������̗D��͔���ł���Ǝv���܂����A�ʏ�̂������Ɋւ��Ă͎��M������܂���B���̂������ł��ꂾ���̎��ɂ����Ȃ�Ȃ��̂��ȁA�ȂǂƎv�����Ƃ�����܂����A�t�ɂ���ȕςȂ������łǂ����Ă���ȗ��h�Ȏ����ł���̂��ȁA�Ǝv���Y�܂����邱�Ƃ�����܂����B�܂��܂��A�����̐��E�͌������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ���������܂��B
��������܂��傤�B�K�v�Ȃ��̂͏��ĂƎ킱�����ۂł��B����́B�킱����������Ŕ̔����Ă�����̂��w�����܂��B���Ă��R�O���ɗ�܂��Ă���킱�����ۂ�U�肩���S�W���Ԑ^�Ă̊��ɒu���Ă����܂��B�������ۂ͐^�Ă̊����ŁA���Ă̕\�ʏ�Ő��炵�A���Ă��������ɕω������܂��B���������͓~���ԍs���܂����A�~�ɐ^�Ă̊����������邽�߂ɂ����������g���܂��B���������͒f�M�ނŕ���ꂽ�����ŁA�e�Ղɍ����A�����̊��������ł���悤�ɑ����Ă��܂��B�~�G�Ɏ��s����̂ɂ͗��R������܂��B�~�G�́A�������̐�ΐ������Ȃ��������A���y�т���݂��q���I�ɑ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B���āA�����͂P�N�������Ă��܂������A�~�G�ȊO�͗L�Q�Ȕ������̐N�����A���R�[�����y�������ɐi�s���Ȃ����Ƃ������A���̊Ԃɂ��~�G�ɏW������Ă����̂ł��B�������A���������肾���́A�^�Ă��œK�Ȃ̂ł��B���������͂���ȗ��R�ő����܂����B
�i�S�j���i���g�Ƃ������܂��j��
�����ʂ���́A���邽�߂̂��ꂳ��A�y��̋������Ȃ̂ł��B���̎d���́A���ɁA�������Ə��Ă���ꂳ��ɍy��Ɠ��_��Y�����܂��B���_�͍y��ȊO�̔����������ɐi������̂�h�����߂ɓY�����܂��B�R�p���g����g�ƌĂ����́A�y���Y������O�ɓ��_�ۂɓ��_���Ă��炢�܂��B���_�ۂ́A���R�ɑ��B���A���_��A�s���̗ǂ����ƂɎ����ő��������_�̂��߂Ɏ��ł��Ă��܂��̂ł��B�R�p���g����g�ł͓��_�ۂ����ł������Ƃ��m�F���Ă���y���Y�����܂��B
�Y�����ꂽ�y��́A�����������������g����Ăɍ�p���Đ������Ԃǂ������a�ɂǂ�ǂB���܂��B�ŏI�I�ɂ͎��Pml������T�`�P�O�����炢�܂ő�����ƌ����Ă���܂��B�d���ݒ���̎��́A�����Ö��Ɠ��_�̎_�����}�b�`�����܂��ɏ����Y�_�K�X������J���s�X�̂悤�Ȕ��������ł��B���̖��̂܂��i���ł���A�Ǝ��̖��������x�Ɏv���܂������A�����ł��܂���ł����B�i�������ɕs���肾����ł��B�������A�y��̑��B���i�݃A���R�[�����y������ɂȂ�ɂ��������Ö��͏����čs���A���������Ȃ��Ȃ�܂��B�ł��オ�������́A����͋����������Ă��܂����A���́A�_���A�ꖡ�y�яa�����������߂܂���B�������A�ꖡ��a�݂������قǎ�ꒆ�̍y��͔��y�͂��������݂ł̃A���R�[�����y�����S�ɐi�s�����邱�Ƃ��ł��܂��B
���_��Y������^�C�v�̎��́A�d����ł���Q�T�Ԃ��炢�Ŏg�p�ł��܂����A���_����_�ۂɑ��点�鐶���g��R�p���g�ł͂R�T�Ԉȏォ���邱�Ƃ�����܂��B
�y��́A���{���������w�����܂����A�Ŗ��������ސ�����Ƌ�����Ă��Ȃ��l�y�і@�l�ɂ͔̔����Ă���܂���B
�i�T�j����݂�
����݂̍H���͂S�i�K�ɕ�����Ă��܂��B��������x�ɏ�������ꍇ�ɔ�ׂ�菬�����\�͂̐ݔ��Ŏd�����ł��܂����A�d�������邱�ƂŗL�Q�ۂ̑��B�]�n�����߂邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�C�@�Y�i���Y�Ƃ������j
���i�K�̎d����Y�Ə̂��A���ɁA���A�������y�я��Ă������������܂��B�Y�d���̌��ʁA�ł�������݂̂��Ƃ��u�Y�v�Ə̂��܂��B���R���̍y��͖�S���̈�ɔ��܂�܂����A�������Ə��Ă��狟�������Ԃǂ�����H�ׂČ��C�ɑ��B���܂��B��ꂩ�狟�������_�������܂�܂����A�L�Q�ۂ̑��B��}����ɂ͂܂��\���ł��B�Y�̕i���͂P�T�`�Q�O���ɂ��܂��B
���@�x��
�Y�d�����I����������̂��ƂŁA�Y�ɉ����������A�Ђ�����Y�̒��̍y��̑��B�𑣂����Ԃł��B���ꂩ�璇�d���ōy��̐������ɁA���d�����s���Ƃ܂������ɍy�ꂪ���܂�A�_�������ł͗L�Q�������̑��B��}������Ȃ��Ȃ�̂ł����ł�������y��B�����A�y��̊��͂ő��B���悤�Ƃ���L�Q�ۂ���������̂ł��B���̂��߂ɒ��̎d���܂ň���x�݂����̂ł��B�x��Ƃ������������ӂ�錾�t������ł͋x�݂��Ӗ�����̂ł��B��x�݂Ƃ������Ƃł͊K�i�̗x���Ƃ�����Ǝ��Ă��܂��ˁB�������A�y��͊����Ɋ������A����݂̕\�ʂ͏o������A�ɂ�肠�������x���Ă���悤�Ɍ����܂��B�x��̕i���͂P�T���t�߂ł��B
�n�@���Y
�x��̗����ɁA�Y�ɁA���A�������y�я��Ă��������̎d���Ƃ��܂��B�ł�������݂̂��Ƃ��u���v�Ə̂��܂��B�����ŁA����݂̑S���ʂ̖��܂ł��d���܂�܂����B���́A�����ʂ�A�O�i�d���̐^�̎d���ł��B�ǂ������A���Ă銿���͐l���t���ꂽ���ł��B�����̐��E�ł͒��ł͂Ȃ����������Ύg�p���Ă��܂��B���R�͂킩��܂���B���Y�̕i���͂P�O�`�P�T�����炢�ł��B
�j�@���Y
���d���̗����A���ɁA���A�������y�я��Ă��������̎d���Ƃ��܂��B����ł���ݎd�����������܂��B�Y�ƒ��̖��̂��琄�_����Ɨ��d����̂���݂��u���v�ƌĂт����ł����A�d�����̓������u���v�Ŏ��̓�����͒P�Ɂu����݁v�ƌĂт܂��B
���d���ŐV���ɂ���݂ɉ����A���A���ċy�т������́A������������݂̖����߂܂��B�e�d���݂̏��ĂƂ������Ă̍��v�d�ʂ́A�Y���P�Ƃ���Ƃ����悻���͂Q�A���͂R�̔䗦�ɂȂ�܂��B�Y�ƒ��̍��v�͂R�ŗ��R�Ɠ��������Ƃ��痯������݂̔����̕��ʂ��߂邱�Ƃ͗������������邱�ƂƎv���܂��B���d���̕i���͂W�`�P�O�����炢�ɂ��܂��B
�i�U�j����݂̏n���A�A���R�[���Y���ƂS�i�̓Y��
���d�����I�����ĂQ�O���O��ŁA�A���R�[�����y���������A����݂͏n�����܂��B���̊ԁA�A���R�[�����y�������ɐi�s����悤�ɑ��l�͂���݂̟D����Ɖ��x�Ǘ����s���܂��B���y���x�͂P�O�`�P�T���ł��B������͂P�O���t�߂Ŕ��y�����A���������̎��ł͂P�T���O��̔��y���x���W���I�ł��B�n����������݂̐����́A�A���R�[���x���͂P�W���O��A���{��x�̓[���t�߂ɂȂ��Ă��܂��B���Ď��ɂ���ꍇ�́A���̂܂܁A�㑅�Ƃ����ʼnt�����H���Ɉڍs���܂����A�ʏ�́A�������邽�ߏ��ʂ̃A���R�[����Y�����܂��B�܂��A�Â݂�t�^����ړI�łS�i�i���܂ł��R�i�ł��̌�ɉ����邽�߂S�i�ƌ����܂��B�j�Ə̂��ď��Ă��y�f�܂œ��������Ԃǂ����Z�x���R�O���ȏ�����铜���t��Y�����邱�Ƃ�����܂��B
�i�V�j�㑅�i���傤�����A�����ӂˁj
���n��������݂𐴎��Ǝ𔔂Ɍʼnt�������鑀����㑅�Ƃ����܂����A�����ӂ˂Ƃ��Ă�܂��B�R�O�N�ȏ�O�́A�����A���n��������݂𐔕S���̎�܂ɏ��������A�������D�ƌĂ�钼���̂̑��ɓ���㕔���爳�͂��|���Đ������h�����A�c�����𔔂͈ꖇ����܂�����o���Ă��܂����B���̎�D�ƌĂ��e��́A�D��H���D��Z�p�ʼnt�̂��R��Ȃ��悤�ɑ����Ă���������ƂɈ���ł���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B���~�̒��A����݂���܂ɋl�߂���A���I����Ď𔔂���܂�����o���㑅��Ƃ́A��ςȏd�J���ł����B���ł́A�����������C���𗘗p���Ă���݂��琴�����h������Ă��܂��B�����ƊE�Œa�������̋Ǝ�Ŏg���Ă��鐔���Ȃ����u�����̎��������ꂽ����݈���@�ł��B����݂Ƃ��������h���ɂ������̂����Ƃ��ȒP�Ɍʼnt�������邷�炵���\�͂ɔp�������ƊE�����ڂ��A���D�̌ʼnt�����Ɋ��p����Ă��邻���ł��B
�ʼnt�������s���Ɛ������a������̂ł����A��܂��g�p���Ă�������͂ł��オ�������������������Ă��܂������琴�������Ƃ��K�v�ɂȂ�܂����B����͓����Ƃł͂���܂���B��T�Ԃ��炢����̕����i�I���Ə̂��܂��B�j�����~����̂�҂��Ă���悢�̂ł��B���ɂ���قƂ�ǂ̃^���N�ɏ�ۂ݁i����̂݁j�Ɖ��ۂ݁i�����̂݁j�Ə̂�����̏o�������㉺�ɂQ�t�����Ă���̂������ɂȂ������Ƃ͂���܂��B�I�����������Ă��āA��ۂ݈ȉ��ɂȂ�����I���������s���܂��B�I�������́A��ۂ݂���������Ɛ��������o�����̃^���N�Ɉڂ�����������܂��B�Ō�Ɏc�����I���̕����͉��ۂ݂�����o���A�X�ɁA�I�����m���������ăI������������s���܂��B�Ō�́A�I����������x��܂ɓ���㑅������s�����S�ɐ��������܂����B
�]�k�ł����A�𔔒��̃A���R�[���͂ǂ̂��炢����̂ł��傤���B�𔔒��̉t�̕����͏d�ʂ̖����߂Ă��܂����A�t�̕����͐����Ɠ��������g���ł���Ɛ��@�ł��܂��B�㑅����̐����̃A���R�[���x���͂P�W�`�Q�O���ł��傤����A�O.�T�~�P�X�~�O.�W���W���A���Ȃ킿�A�d�ʕS�����łW�����炢�̃A���R�[�����܂�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�i�O.�W�̓A���R�[���̔�d�ł��B�j�z�����Ă����ȏ�ɂ���܂��ˁB�Ă�����A�Î��└�`�ɂ���ꍇ�A�A���R�[���͔�U���܂����A�M�������Ȃ��ŐH���鎞�͐����\��������܂��B
�i�W�j�Γ���Ɠ��{�l�̕�����i���ق��������������H�j
�I��������A�����͉��M�E�ۂ���Ē�������܂��B�����ƊE�ł́A���M�E�ۍH�����Γ���Ə̂��Ă��܂��B�H�i�ƊE�ł́A���M�E�ۂ̂��Ƃ��҂ł���A�t�����X�̐����w�҃��C��p�X�c�[���̖��ɂ��Ȃ�Ńp�X�g���[�[�V�����ƌ����܂����A�����̉Γ���͂�����ꡂ��T�O�O�N�O�A��������ɂ́A���ɍs���Ă����Ƃ����L�q������܂��B�o����A���M����Ɛ����͕����Ȃ邱�Ƃ͂킩���Ă����̂ł����A���̌����ɂ��Ă͗������Ă��Ȃ������悤�ł��B�������{���p�����珵�ق����O���l���ق������̃A�g�L���\�������́A�r�[���������ΏۂƂ��Ă��܂������A�ɓ��̂���ȓ����ŁA���h����p�X�c�[���搶�̔������ꡂ��ȑO�Ɏ��̉��M�E�ۂ����H����Ă��āA����ɁA�������Ƃ�������ȊO�̓����ނ��g�p����A�r�[���̂R�{�ȏ�A�P�T������A���R�[�����y���H�ƋK�͂ōs���Ă������Ƃ�m��ǂ�Ȃɋ��������͑z���ɓ�Ȃ��ł��傤�B���Ɍ���ׂ��Y�Ƃ̂Ȃ�������������̐����ƊE�́A�܂��ɐ��E�̍Ő�[�Y�Ƃ������̂ł��B��ł́A�Z�b�R�n�̐����𗘗p�����Ԃ��A�ĂĂ��A�������ہA�y��y�ѓ��_�ۂƂ����O��ނ̔���������g���ĕĂ��琴�����A���Ȃ킿�A�ł�Ղ�A���R�[�����Ă����̂ł�����B���̓`���́A���y�Ƃ����L�[���[�h�Ō���̓��{�ɐ����Ă��܂��B
�����̎�������A���{�l�͕��邱�Ƃɂ͒����������ł��邪�A������̒ꗬ�ɂ��錴�������ɂ͖��ڒ��ȍ�����������̂��ȁA�Ȃǂƍl���������Ă��܂����B���邱�ƂɊւ��ăA�g�L���\���������������������ƊE�ł����A������̊�b�ɂ��闝�_�Ɋւ��Ă͔ނɑ傢�Ɋw�т܂����B�ނ͋A����A���{�؍ݒ��̋Ɛт�_���ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B���������ƂɁA���̘_���́A�C���^�[�l�b�g�Ō��J����Ă��܂��B�_���̕W��́uThe Chemistry of Sake Brewing�v�ł��B�A�h���X�@�́Ahttp://brewery.org/library/sake/cover.htm�ł��B�p�ꂪ���\�ł������̂�����͈�x�A�K��Ă݂Ă͂������ł����B��������̎�łɂ��Ă�A�����̎�̎��ԁA�A�g�L���\�����������{�ň�Ԕ��������Ǝv�������͔~���ł������炵�����Ƃ��L�ڂ���Ă��܂��B�������A�����̖��ɂ��Đ搶�̓R�����g���c����Ă��܂���B���ɍ���Ȃ������̂�������܂���B�P�O�O�N�ȏ�o�߂����A�ɂ킸���Ȑl�݂̂������������ł��낤�_�����C���^�[�l�b�g�Ō��邱�Ƃ��ł���̂͑�p�鍑�̒�͂ƌ����ׂ��ł��傤���B
�i�X�j��������o��
�~�G�ɑ���ꂽ�����́A�Γ���E�ۂ��^���N�Œ�������Ă��z���A�n�����Ď|�����܂��ďH�����珤�i������܂��B���̍��͐������t���b�V���Ȏ������D�܂��悤�ɂȂ�P�O���ȉ��̒ቷ�Œ�����������������܂������A�K�x�ȏn���𑣂����߂ɂ͓K�x�ȉ��x���K�v�ł���ƍl���܂��B���܂�ቷ�����ɂ͂�����炸�A�^�ĂłR�O�����Ȃ���Ύ��R�ɂ܂����Ē��������ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������ɂ͓ۂݐ�Ə̂����X,�^���N�̎������o���n���x��������������A�Η��ۂɉ�������Ă��Ȃ����m�F���܂��B�ŏ��̓ۂݐ�́A���ɏ��ۂݐ�ƌĂ�A�Γ����A�R�������炢�o�߂����V�����{�ɍs���邱�Ƃ�����ł����B�V���̂ł��h���͏t��̊ӕ]��Ŕc�����Ă���̂ł����A�n���ɂ����̐^�̉��l���킩��̂͂��̎����Ȃ̂ł��B�܂��A���̎����́A�Η��ۂɉ������ꂽ���̎������ω����n�߂鎞���ł�����܂��B�؉����^���N�Ɏg�p������Ȃ���������͉Η������邱�Ƃ��������Ȃ��A���ۂݐ�͎�������̑厖�ȍs���ł������̂ł��B����^���N�ɂȂ������݂ł��Ӓ芯����������̈˗��ŏ��ۂݐ�ɗՏꂵ�A���̔N�̎��̏n���x���ƉΗ��ۂ̗L�������邱�Ƃ�����܂��B
�i10�j�����̕���
��������ł́A���y�������ɐi�s���Ă��邩�A�K�i�ǂ���̏��i�ɂȂ��Ă��邩���ׂ邽�߂Ɉ�N�����͂��s���Ă��܂��B���͂̑Ώۂ́A�d���̊��Ԓ��ɂ́A�����A���y�т���݂ł����A����ȊO�̎����ł͐��������ł��B���͍��ڂ́A�A���R�[���x���A���{��x�A�_�x�y�уA�~�m�_�x�ł��B����܂ł������̌��t���g�p���Ă��܂������A�����ŏ����������������Ǝv���܂��B�A���R�[���x���Ƃ̓A���R�[���̗e�ʕS������\���Ă���A�����P�O�O�����Ɋ܂܂��A���R�[���̂������ł��B�P�T�x�͂P�T���̂��Ƃł���A�����P�O�O�������ɂP�T�����̃A���R�[�������݂��邱�Ƃ�\�����Ă��܂��B���{��x�́A�����̔�d����Z�o�����l�ŁA�v���X�̗̈�ł͔�d���P.�O��菬�����A�[������d�̂P.�O�A�}�C�i�X�̈�ł͔�d�͂P.�O���傫�Ȓl�����܂��B�G�L�X���������قǁA���Ȃ킿�����������قǔ�d���d���Ȃ�܂�����A���{��x�́A�������A�}�C�i�X���ɂȂ�܂��B�_�x�͂���܂ł����b���܂����Ƃ���_���ς��̎ړx�ł��B�����P�O�����𒆘a���邽�߂ɗv����O.�P�����̉Ր��\�[�_���n�t�̗e�ʂŕ\����܂��B�_�x�P.�O�́A�����P�O�����𒆘a���邽�߂ɂO.�P�����̉Ր��\�[�_���n�t���P.�O�����K�v�Ȃ��Ƃ�\���Ă��܂��B�A�~�m�_�x�́A�A�~�m�_�̊ܗL�ʂ̎ړx�Ƃ��l���������B�����Ɩ��̔Z���A�R�N�������܂����A�G���Ƒ������鋰�ꂪ�����܂��B���̍D�ސ����̃A�~�m�_�x�́A�_�x�Ɠ������A�_�x������邱�Ƃ������ł��B
(11)�Q�̔���
���͂Ɋ֘A���������ŁA�����ւ�ȋ�J���������܂������A�����ƊE�ւ����₩�ȍv�����ł������Ƃɂ��Ă��b���܂��傤�B����́A�A���R�[���x���Ɠ��{��x�̕��͂Ɋւ��ĂQ�̔������s�������Ƃł��B
�C�@�A���R�[���x���Ɋւ���
�Q�O�O�P�N�ɓ����Ζ����Ă������Œ����������������̏Ȓ��ĕ҂̈�Ƃ��ēƗ��s���@�l��ޑ����������ƂȂ�܂����B����Ɠ����ɋƖ��̑啝�Ȍ��������s���A�A���R�[���x���̑���Ɏg�p�����v�ƌĂ��u�����v���Z������d���������A���͂��̐ӔC��C����邱�ƂɂȂ����̂ł��B�A���R�[���̔�d�́A�O.�W�ł���A���̂���͂P.�O�ł�����A���R�[���Ɛ��̍������ł���A���R�[�����n�t�͔�d�𑪒肷�邱�Ƃɂ��A���R�[���x�����킩��܂��B�A���R�[�����n�t�Ɏv���ׂ܂��ƃA���R�[���x���������قǔ�d�͌y���Ȃ蕂�͂��������Ȃ�܂�����A���L���f�X�̌����ɂ��A�v�͂�蒾�݂܂��B�x�����Ⴂ�ꍇ�͋t�ɂȂ�܂����A������ɂ��܂��Ă��v�̒���Ɛ\���܂��傤�����������A���R�[���x��������ł��܂��B�������A�v�͐������ꂽ�܂܂ł͐��m�Ȓl�������ƌ����ۏ�͂���܂���B�����A�唼�̎v�́A����l���������l���������Ƃ͋H�Ő^�̒l��菭���Y���Ă��܂��B�Z���Ɛ\���܂��̂́A���̃Y���i��j�𑪒肷�邱�Ƃ�\���܂��B����@�́A�������l���������Ƃ��킩���Ă���v�i�W����ƌĂ�ł��܂����B�j�ƍZ�����悤�Ƃ���v���A���R�[�����n�t���ɓ����ɕ����ׂ��̍����r���邱�Ƃɂ��s���܂��B
���ۂɎ�ނ̃A���R�[���x���𑪒肷�邽�߂ɂ́A������������������A���R�[�����n�t�Ƃ����̒��Ɏv���ׂ܂��B�����͎𒆂̃G�L�X�����������߂ɍs���܂��B�G�L�X���͔�d�Ɋւ��ăA���R�[�����Ƌt�̍�p�����܂��̂ŏ����Ȃ��Ɛ��m�ȑ��肪�ł��Ȃ��̂ł��B��d����A���R�[���x���ɕϊ����邽�߂ɕϊ��\���K�v�ɂȂ�܂����A���{�ł̓Q�C�E���T�b�N�̕\�ƌĂ����̂��g�p���Ă��܂��B��P�T�O�N�O�ɃQ�C�E���T�b�N����ƌ��������P�x�i���j����P�O�O�x�i���j�܂ň�x���Ƃ̃A���R�[�����n�t�肻�̔�d���������č�������̂ł��B�v�ɂ́A��d�̑���ɃQ�C�E���T�b�N�̕\�Ŋ��Z���ꂽ�A���R�[���x�������܂�Ă��܂�����A����҂͎�������d�𑪒肵�Ă���Ƃ͎v���Ă��܂���B�������A�����I�ɂ͔�d�𑪒肵���̒l���Q�C�E���T�b�N�̕\�Ŋ��Z����ăA���R�[���x���Ƃ��ĕ\������Ă���̂ł��B
���͐V�����������ւ̔z�����߂��Ɩ��̂ЂƂł���Z�����Ƃɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B�����ĊJ���������ǂ���܂���ł����B�h�r�n���擾���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ł��B�悭�m���Ă���h�r�n�͂X�O�O�O�Ƃ��P�S�O�O�O�Ƃ��ł����A���ǂ����擾���Ȃ���Ȃ�Ȃ������h�r�n�͍Z���@�����̂P�V�O�Q�T�ł����B�������A�擾�܂ł̍���͓������ނ���A��荂�x�ȗv�����҂��Ă��܂����B�������\���グ�܂��Ƃh�r�n�X�O�O�O�ɁA�ǂ̂��炢�̐��m���ŃY���̑��肪�ł��邩��t�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ł��B�X�O�O�O���擾���邽�߂ɂ����l�̐��`�[�����Q����R�N�����čs�����炢�̎d���ʂ�����܂��B�������A���ɉۂ���ꂽ�C���́A���̋Ɩ��ƕ��s���ĂS�l�̃X�^�b�t�ŁA�P�N�łh�r�n�P�V�O�Q�T���擾���邱�Ƃ������̂ł��B�Ɨ��s���@�l�͔N�x�ڕW�������Ă��莄���C���ꂽ�������̔N�x�ڕW�Ɉ�N��ɍZ���Ɩ����J�n���邱�Ƃ����L����Ă��܂����B���̌������̖ڕW���쐬����ɂ�����\���Ȍ������Ȃ���Ȃ��������Ƃ͖����ł�������ڕW�̉��������肢���܂������p������܂����B���ǁA�Q�N��Ɏ擾�ł����̂ł����A�x���͖������@���ł����B�����ł������Ȃ��������̓����͂قƂ�ǎ����܂����B�����āA�������ނƌ��܂��ē����ɓ���U�炵�Ă��܂����B�����́A���Ȃ�����ł������A����Ȏd�������Ă���Ƃ��̓��A���������Ŗ����N�������E������Ȃ��ɂȂ�̂ł͂ƁA�S�z���閈���ł����B�^�悭����Ȏ��������߂������Ƃ��ł��܂������A����ȗ��A���̏�ŕs�ˎ����N�������ɂ͓����悤�ɂȂ�܂����B
�Z���Ɩ��ɂh�r�n���K�v�ȗ��R�́A�v�̃Y���𑪒肷��\�͂����邱�Ƃ��O�҂ɏؖ����Ă��炤�K�v�����邩��ł��B�������ޑ��������������̐��@�ւł���\���ȍZ���\�͂������Ă���ƌ����Ă��ꖯ�Ԋ�Ƃ������咣���Ă��邾���ł���A�ƌ����Ă��܂�����܂łł��B��O�ҋ@�ցA���̏ꍇ�͂h�r�n�̔F��c�̂ł����A����\�͂���ƔF�߂Ă��������˂Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̂��߂̂h�r�n�ł��B�����Ō�ɋΖ����Ă����H�c�����͂��߂������̒n�������̂łh�r�n���擾���čs�����s���Ă��܂����A�{���ɕK�v�Ȃ̂������^��������Ă��܂��B�h�r�n�͎擾�����c�̂����߂�ꂽ���Ƃ����炵�ċƖ����s���Ă��邱�Ƃ��O�҂ł���F��c�̂��ۏႷ����̂ł��B�Z������M�p����Ă���Βn�������̂��h�r�n�Ȃǎ擾����Ӌ`�͂���̂ł��傤���B�h�r�n�͎擾�ƈێ��Ɍ��\�Ȕ�p��v���܂��B�n�������̂��h�r�n���擾���邱�Ƃɂ͋^��������Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ��擾��͈ێ�����K�v�͖����Ǝv���܂��B
���������ɂ���܂����B�h�r�n�P�V�O�Q�T�̎擾�̍ŏI�i�K�Ɍ��n�����Ƃ������̂�����܂��B����́A�h�r�n�̔F��@�ւ���E�����h������\�����ꂽ�Ƃ���ɍZ���Ɩ������s����Ă��邩�������̂ł��B���̒��ōł��̐S�ȓ_�́A�u�v�̃Y����\�����ꂽ���x�ő���ł���B�v���Ƃł��B���̎����́A�N���A�ł���ƌ�����̎��M�̊�ɐӔC�҂ł��鎄���s���܂����B�������A���ʂ́A�P�T�x����Q�O�x���N���A�ł��܂���ł����B���̂��߁A�\���������x�����������A�Ȃ�Ƃ����n������ʉ߂ł��܂����B���Ƃ��Ă͔[���ł��Ȃ������̂ł����A�h�r�n�P�V�O�Q�T�̎擾�͐�Ζ��߂ł��B���ɍ�N�͖ڕW��B���ł��Ȃ������̂ł��B�����č��N�॥���A�Ɠ����悬�����̂ł��B
���n�����̌W���̒��ɔF��@�ւ���Z���̐��ƂƂ��Č��������Ϗ����ꂽ�Ɨ��s���@�l�Y�ƋZ�p�����������i�ȉ��A�Y�����Ɨ����܂��B�j�̐E������������Ⴂ�܂����B���̕��̏������Ă��镔�傩��̓A���R�[���x������ɂ��ĐF�X�A�h�o�C�X�����������Ă��܂������A��̈˗����Ă��܂����B��قǃQ�C�E���T�b�N�̊��Z�\�ɂӂ�܂������A���݁A���E�I�ɂ́A�A���R�[�����n�t�̔Z�x�Ɣ�d�̊��Z�͍��ۃA���R�[���\���g���Ă��܂��B�Y�����Ƃ��ẮA���ۊԂŎ�ނ̎�����s���Ă��錻����l�������{�����ۃA���R�[���\�����Ƃ��č̗p���ׂ��ł���ƍl���Ă��܂����B�������A���Z�\�̑I��͍��Œ��̏��������ɂȂ��Ă��܂�����A���Œ������ǂ���Ɨ��s���@�l�ł����ޑ����������̐E���ł��鎄���獑�Œ��֊��Z�\�̕ύX�������Ă���ƈ˗�����Ă����̂ł��B��ނ̍��ێ���Ɏ����邱�Ƃł�����A�������������������Ƃ�����A���傤�NJ֘A���鍐���̉������v�悳��Ă��܂����̂ō��Œ������ۃA���R�[���\���̗p����悤�ɓ��������邱�Ƃ���܂����B�������A���ۂɂQ�̕\�̍�����������ƍ��������Ƃ����������̂ł��B���x�O.�X�V�T�S�Q�i���x�Ɣ�d�͓����ł���ƍl���Ă��������B�j�̎��A�Q�C�E���T�b�N�̕\�ł͂Q�O.�O�O�x�ɂȂ�̂ł����A���ۃA���R�[���\�ł͂P�X.�V�S�x�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����̂��傤���イ���[�J�[�ł͂Q�O�x�̏��i�������o�ׂ���Ă��܂��B���̂܂܁A���ۃA���R�[���\���̗p����Ǝ��́A���傤���イ���[�J�[���炽���ւ�Ȕ��𗁂т邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�O�x�̏��i��̂ɂ���܂ł��������̌������K�v�ɂȂ邩��ł��B�����̂��߂��l������̂܂ܐi�ނׂ��Ȃ̂ł��傤���A����l�̎��ɂ͂ł��Ȃ����k�ł����B�ύX�͂ł��Ȃ����Ƃ�m�点���e�͂����������߂ɎY�����ɏo�����܂����B���R���������ƎY�����̐ӔC�҂́A����Ȃ��Ƃ͖����Ɛ\����āA�����g�Ŋ��Z�����l��������܂����B�Ȃ�قǁA���ۃA���R�[���\���Q�C�E���T�b�N�̕\��������Ɏ������悤�ȍ��͂���܂���ł����B�ǂ������������B�v�Z�̍����ƂȂ邨�݂��̊��Z�\���r���Č��܂����B����قǏՌ��������Ƃ͂���܂���ł����B�P�V�x����Q�Q�x�̕t�߂̔�d���قȂ��Ă����̂ł��B�\�\�@�����Ă��������B���͍ł������̍��Œ��ł̃Q�C�E���T�b�N�Ŋ��Z���Ă����̂ł����A�Y�����ł͓��R�A�^���̗��̎Y�����łŌv�Z����Ă����̂ł��B�ő�łO.�R�x�i���j�Y�����ł��Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B
����ȊO�̔Z�x�ł͂قڊ����ɂQ�̃Q�C�E���T�b�N�̕\�͍��v���Ă��܂����B����ŁA���́A���n�����̎��ɐ\���������x�ő���ł��Ȃ����������������܂����B��������̊�Ƃ������͍̂��Œ��ł̃Q�C�E���T�b�N�ł����A�������̕W���͎Y�����ł̂���ł������̂ł�����B���̖��_�͉��܂������A�h�r�n�P�V�O�Q�T�̑��萸�x�͕ς����܂���ł����B�܂��Ȃ��A�V�����Z�����@�ɂȂ邱�Ƃ��킩���Ă��܂����̂Ō����Ȃ���������ł��B�Q�̃Q�C�E���T�b�N�̕\�����܂ꂽ�����ł����A�����̎Y�����̒S���҂����̔Z�x�͈͂������l�ƈقȂ邱�ƂɋC�Â��C�����������̂ł��낤�ƍl�����܂��B���͈̔͂��A���R�[���P�x������̔�d�ω������������肪������Ƃ������������̂ł��B�����̘r�O���V�˓I�ł������ƌ�����Q�C�E���T�b�N�ł��P�T�O�N�O�̐ݔ��⎎����g�킴��Ȃ��������߁A�������ɂ��͈̔͂ł͌덷���傫���Ȃ��Ă��܂����悤�ł��B���Œ��ł̏C���́A���Ȃ�ȑO�ɍs��ꂽ�悤�ł����B�S���҂��C���������ɍ��Œ��ɘA�����Ă�����������Ǝv���܂������A�Ȓ��̏c����̕��Q�Ƃł��\���܂��傤���A�����Ȃ�Ȃ������̂͂��b�����Ƃ���ł��B�v�̍Z���Ɏg�p����W����́A�Y���������̑O�i�ł���v�ʌ��������ォ�炸�[�ƑS���������Ă��܂������炢�܂��獑�Œ��łɕς���Ƃ͌����܂���B��ދƊE���������邾���ł����A�Y�����ł̕����^�̒l�ɋ߂��̂ł�����B���������܂��āA�������Y�����ł̃Q�C�E���T�b�N�̕\�Ŋ��Z���ꂽ�A���R�[���x�����\������Ă��܂��B�߂������A��ނ̃A���R�[���x���́A���ۃA���R�[���\�Ŋ��Z���ꂽ���̂ɂȂ�Ǝv���܂����A�ύX�����\����Ȃ�����W�҈ȊO�ŋC�Â��l�͊F���ł���Ɗm�M���Ă��܂��B
�\�[�P�@���Œ��ŋy�юY�����ŃQ�C�E���T�b�N�ƍ��ۃA���R�[���\�ɂ��A���R�[���x��
|
�@���x |
���Œ��ŃQ�C�E���T�b�N |
�Y�����ŃQ�C�E���T�b�N |
���۱ٺ�ٕ\ |
|
0.97832 |
17.00 |
16.90 |
16.86 |
|
0.97732 |
18.00 |
17.90 |
17.85 |
|
0.97642 |
19.00 |
18.80 |
18.74 |
|
0.97542 |
20.00 |
19.73 |
19.74 |
|
0.97442 |
21.00 |
20.70 |
20.74 |
|
0.97332 |
22.00 |
21.80 |
21.84 |
���@���{��x�Ɋւ���
�Z�p�͓��i�����ł��B�����̐��E�ɂ��V�����Z�p�����ꍞ��ł��܂��B���̒��̈���U�������x�v�ł��B���j�I�ɓ��{��x�́A�v�Ɠ������悤�ɓ��{��x�v�ƌĂ�镂���ő��肳��Ă��܂������A���i���育��ɂȂ����U�������x�v�����p�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�ŐV�̐U�������x�v�́A�����̖��x�𑪒肵���{��x�Ɋ��Z���ĕ\���ł���悤�ɑ����Ă��܂��B�������A�����A���{��x�v�̑���l�ƐU�������x�v�ł̒l�Ƃ��ꗂ������Ă��邱�ƂɋC�t������Ă��܂����B�ꗂ������錴���ɂ��ẮA����\�����t���Ă��܂����B���{��x�v�͎v�Ɠ��l�ɃY���������Ă������Ďg�p���Ă���̂ł����A����邽�߂̍Z�����@�ɖ�肪�������̂ł��B�����܂ł͎�ޑ����������ɋΖ����Ă��鎞�ɔc�����Ă��܂����B�h�r�n�P�V�O�Q�T�̎擾�ŐS�g�Ƃ��ɔ��ʂĂ����́A�]��]�ݏ��F����܂����B�D�y���ŋNJӒ芯�����V�����Ζ��n�ɂȂ肻���ŁA���̖��̉��������݂܂����B
�ŏ��ɍs�������Ƃ́A�{�����ꗂ�������̂��A������ǂ̒��x���m�邱�Ƃł����B�s�̐����̒������ɁA�U�O�_���܂�̐�������{��x�v�œ��{��x�𑪒肷��Ɠ����ɐU�������x�v�ł����x�𑪒肵���{��x�Ɋ��Z���Ĕ�r���Ă݂܂����B���ς��ĂP.�T�A�U�������x�v�̂ق��������l�������܂����B�قڗ��_����\�z�����l�ɋ߂����ʂł����B�����ɂ�茻�ۂ̑��݂��ؖ����A�����_�I�ɂ��̌��ۂ�����ł��܂����̂Œɉ��ȋC���𖡂킦�܂������w���ƊE�ł̕]���͍��ЂƂł����B�ꌏ�����A�_�����f�ڂ���Ă����ɖ₢���킹������܂����B�U�������x�v����������ɔ��荞�����Ƃ��Ă����Ǝ҂���ł����B����܂ł͔��荞��ł����{��x�v�Ƃ��ꗂ�����ł������荞�݂Ɏ��s���Ă����̂������ł��B�_�����R�s�[���Ĕ̔����i�̎����ɂ������Ƃ������Ƃł����B�_���̒��쌠�͌f�ڂ��Ă��ꂽ�����w��ɂ���܂��̂ŁA�������珳����悤�ɂ��b���܂����B���̘_�����_�@�ɂȂ��āA�U�������x�v�������ƊE�֕��y����Γ��{��x�v�̑��萸�x�͂������ł������l�ɔ�d�𑪒肷��A���R�[���x���̐��x�����シ�邱�Ƃ������߂܂�����A����҂̕��ɂ������ƊE�̂��߂ɂ������͍v���ł����̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ă��܂��B
�������A���̂��Ƃ͓��{��x�̑���ɂ����Đ����ƊE�ɍ�������������������܂���B�ǂ���̒l���̗p���ׂ��������������Ă��܂�����ł��B���_�I�ɂ͐U�������x�v�̑���l�̕����^�̒l�ɋ߂��̂ŐU�������x�v�̒l���̗p���ׂ��ł��낤�Ǝv���܂��B�������A���i�̃X�y�b�N�Ƃ��ē��{��x���g���Ă���ꍇ�͕\�����������K�v�����邩������܂���B�\����A�h�������������Ŗ��ɉe���͂���܂��A�܂��A�P.�T�̍��͐����قǑ傫���͖����̂ł��B�������łǂ��炪�Â����h�������������Ă�ꍇ�A�Q�̎��̓��{��x�́A�T�͂Ȃ�Ă��܂���Ɖ�X�v���ł��ԈႦ�鎖������܂�����B
���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��N���邩�Ɋւ��Ă̐����͂͂Ȃ͂�����̂ł����A�[�I�ɐ\���グ��A�\�ʒ��͂��W���Ă���̂ł��B�\�ʒ��͕͂����i���{��x�v�j���t�ʉ��Ɉ�������������ɓ����܂��B���̒��x���A���R�[���x���ɂ��قȂ邽�ߋN���������ۂȂ̂ł��B���R�A�A���R�[���x������ł��v�ɕ\�ʒ��͓͂����܂��B�����āA����Ă���ƕ\�ʒ��͂��ቺ���Ă��܂��܂��B�v�͒��ݍ����������A���R�[���x���������悤�ɖڐ����Ă��܂�����v������Ă���ƃA���R�[���x�����Ⴍ�\������Ă��܂��܂��B���́A�H�c���ɕ�E���A��������̎v���ĉ��܂����B�^�̒l�ɋ߂Â��悤�ɁA����������A�����ł��A���R�[���̕\���������Ȃ�悤�ɁA�ƍl��������Ȃ̂ł��B�m��������Ɍ��ʂ̂قǂ��@�����܂�������q�˂Ă݂܂������A�݂Ȃ���A����������Ă�������Ⴂ�܂����B�ڂɌ�������ʂ͖��������悤�ł��B�݂Ȃ��\�A�v�����ꂢ�ɂ���Ă����̂ł��傤�B
�X�@�����Ƃ�
�i�P�j�A���R�[���̗���
�����𐬕��ɕ������čl����A�A���R�[�������o�̒��S�ɂ���A���ӂɂ́A�Ă̎|���ƁA���̎|���A����ɃA���R�[���ȊO�̍y��̑�ӕ�������߂��Ă���A�Ƒ����邱�Ƃ��ł��܂��B�����悤�Ƀ��C���́A�A���R�[���𒆐S�ɉʎ��R���̍��������A�A���R�[���ȊO�̍y��̑�ӕ��y�ђ����M�̐����Ɉ͂܂�Ă���A�ƍl�����܂��B����A�r�[���ނ́A�z�b�v�Ɣ��A����̕��y�уA���R�[���ȊO�̍y��̑�ӕ������S�ɂ���A�A���R�[�������������x�����Ă���A�悤�ɍl�����܂��B
���̂悤�ɁA��ނɂ́A�A���R�[�������̕\����ɏo�Ă�����̂Ɨ����ɓO���Ă�����̂�����܂��B�A���R�[�����\����ɏo�Ă����ނ̑�\�́A�u�����f�[�A�E�C�X�L�[�y�яĒ��Ȃǂ̏������ł���Ǝv���܂��B�������̒��ł́A�����y�ё啔���̉ʎ���������Ǝv���܂��B�A���R�[���������ɓO���Ă����ނ́A�r�[���ށA��Z�x���L���[���ދy�шꕔ�̒�Z�x�ʎ������グ���܂��B���X�A�����̎�ނ́A���������ł͂Ȃ����A�Ǝv�����Ƃ͂���܂����A�A���R�[���͑厖�ȉB������S�����Ă��܂��B
�i�Q�j�A���R�[���x���̂����
���݂̎s�̐����̃A���R�[���x���͂P�T�������S�ł����A����́A���j�I�ɐ�����̐��猈�߂��Ă����悤�Ɏv���܂��B��������݂́A���݂̗D�ǐ����y����g�p���܂��ƃA���R�[���x�����Q�O�����邱�Ƃ��H�ł͂���܂��A��������D�ǐ����y�������ȑO�̎�ł́A���������P�V�`�P�W���������̂ł��傤�B���̎��𐔓x�A�؉��ɉΓ��ꂵ�Ă����̂ł��̓x�ɃA���R�[������U���s�̎��ɂȂ������͂P�T���ɂȂ��Ă��Ă����������͂���܂���B���{�l�͐�����̐���P�T�����炢�̐��������ݑ����A���̔Z�x�Ɋ���e����ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���C���̏ꍇ�́A�����̃u�h�E�����n����ƃu�h�E���Z�x���Q�S�`�Q�U���ɒB���܂�����A���R�[�����y�ɂ�蓜�Z�x�̖��A�P�Q�����炢�̃A���R�[���x���̎��ɂȂ�A���̔Z�x�����C���̕W���ɂȂ����̂ł��傤�B�r�[���́A�ʏ�A���Z�x�P�R�����炢�̔��`�������y�����܂�����T�`�U���̎��ɂȂ�킯�ł��B
�܂��A�E�C�X�L�[��u�����f�[�́A�A���R�[���x�����S�O�x�t�߂ɂ��Ă���̂́A�S�x���ӎ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�A���R�[�����n�t�̔S�x�́A���x�̉e���𑽏��܂����قƂ�ǃA���R�[���̔Z�x�Ō��܂�܂��B�A���R�[�����n�t�̔Z�x�ƔS�x�̊W�ׂČ��܂��ƂS�O�x�t�߂��ł��S�x�������Ȃ��Ă��܂��B�S�x�������Ȃ�Ǝ��Ƀg�����Ƃ������������܂�A�����ڂɔ����������ł���ˁB���̂悤�Ɏ�ނ̃A���R�[���x���͂���Ȃ�̈Ӗ��������Ă���̂ł��B
�i�R�j���Z�x�A���R�[���ɑ����i���炬���j
���ꂼ��̎�ނ̃A���R�[���x���ɂ͂����Ɏ��闈�������邱�Ƃ����������܂������A�����́A������ƃA���R�[���������Ĉ��������炢�Ƃ����������������Ǝv���܂��B���̂悤�Ȑ��ɓ����邽�߁A���{�g��������́u���炬���v�𐄏����Ă���܂��B�����̂��Ƃ��S�z�ȕ��̂��߂ɓ����̉��ɐ��������O���X��u���Ă����A�����ƂƂ��ɐ������ނ��Ƃ����߂��Ă���̂ł��B���̐����u���炬���v�Ə̂��Ă��܂��B�܂�A���Ȃ��̒��Œ�Z�x���ɂ���̂ł��B���ʂ������ł���A�����̑̒��ɂ͕ς�肪�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂����A���̌o���ł��ƈႢ�܂��B����ł���Ƃ��������S�n���ǂ��悤�Ɏv���܂����A���Ȃ�[�������������̒����������肵���C���ŋN���ł���悤�Ɋ����Ă��܂��B�[�������āA�钆�ɖڊo�߂��Ƃ��ɖ����ɍA�̊������o���A�Q�ڂ����������Ȃ���R�b�v�ɂQ�A�R�t�̐������݂܂��B�܂��ɊØI�ł����A���炬���͐��������݂Ȃ���ØI�𖡂���Ă���Ǝv���Ă��������B
���́A���炬���ɏ�����ꂽ�o��������܂��B�l���݂Ɉ��߂�Ǝv���Ă����̂ł����A�H�c���ɋΖ������Ă̍��͎����Ō��\��J���܂����B�H�c���l�̃A���R�[���ϐ��ɂ́A�͂邩�ɋy�Ȃ������̂ł��B����͓��v�I�ɏؖ�����Ă���܂��ē��{�l�̓s���{���ʃA���R�[���ϐ��͏H�c�����_���g�c�̈�ʂȂ̂ł��B����ȕ��X�Ƃ̎����ł�������ŏ��͑�ςł������A���炬�������߂����Ƃ������Ɛl���݂̂��t���������ł���悤�ɂȂ�܂����B
���炬���́A�����������ގ��ɂ����ʂ�����Ǝv���܂��B���͂��܂���܂Ȃ��̂ł����A���́A�u�����f�[���E�C�X�L�[����D���ł��B���ݕ��́A�X�����ꂸ�X�g���[�g�ň��ނ��Ƃ������ł��B�������邱�Ƃ��A�������l�ւ̗�V�̂悤�Ɏv���邱�Ƃ�����ł����A�������X�g���[�g�͂��̎��̎����������\�ł�����ݕ��ł���Ǝv���邩��ł��B�E�C�X�L�[�͐����肪���܂��ƌ���ꂽ���オ����܂����B���̗F�l�ŃE�C�X�L�[��Ђ̋Z�p�҂�����܂����A�ޞH���A�ǂ��E�C�X�L�[�͐��ł̂т�B�܂�A�ǂ��E�C�X�L�[�قlj����ʂ𑝂₵�Ă������������߂�A�ƌ����̂ł����A���ɂ͐���������܂������c�Ɛ헪�̂悤�Ɏv����̂ł��B�������͒Ⴍ�Ă��I���U���b�N���炢�̃A���R�[���Z�x�����������悤�Ɋ����܂��B���x�A���������E�C�X�L�[��u�����f�[�ɏ��荇������A���炬����F�ɒɈ����������̂ł��B
�������A�������̒��ł����炬�����K�������x�X�g�ł͂Ȃ���������܂��B�P���������傤���イ�ł��B���̒��ł��A�����傤���イ�ƖA���ɓ��ɂ���������܂��B�������A�X�g���[�g�ɂ��炬���̑g�ݍ��킹���ǂ��̂ł����A�苭���������肪�u��������v�ł��B��������́A�����������Ɏ����Ƃ��낪����A�X�g���[�g�ł͖��킦�Ȃ������������������܂��B�F���̍��W���J�ň��ވ����傤���イ�̂�������́A�����傤���イ�̗ǂ������ׂĈ����o�����悤�Ɏv���܂��B
�܂��A������ɂ�����_������܂��B����ł��B�ʏ�A�������̍���́A��������������{���̍����������������悤�ɂȂ�͂��ł��B����̂������낳�͑O�ɂ��b���܂������A���̌��ۂ����̈�ł��B�A���R�[���͔Z�x�������ꍇ�A���̍��C���������������Ȃ��Ȃ�����ɍ�p����̂ł��B��X�͂�����}�X�L���O��p�ƌĂ�ł���܂����A�����ɂ��A���R�[���̔Z�x��������}�X�N���O��܂��B
�i�S�j�����̕���
�����ƊE�̊ē����ł��鍑�Œ��ɂ�����҂̑I���Ɏ�����悤���������ނ���Ă��܂��B���̕��ނ̊�𐴎��̐��@�i���\����Ɛ\���܂��B����܂ł����̊�Œ�`����Ă��錾�t�������������Ɏg�p���Ă��܂������A�����ʼn��߂Ă��Љ�܂��傤�B
�C�@�����
������́A�u���ĕ����U�O���ȉ��̔��āA�Ă������y�ѐ��A���͂����Ə����p�A���R�[���������Ƃ��A�ᖡ���Đ������������ŁA�ŗL�̍����y�ѐF�ǍD�Ȃ��́v�ƒ�`����Ă��܂��B
��`�̓��e�ɂ��Ď�������܂��傤�B���ĕ����U�O���ȉ��̔��ĂƂ́A���ĂĂ��S�O���ȏ���f�Ƃ������Ă̂��Ƃł��B�܂��A���ĕ������T�O���ȉ��ɂ����ꍇ�́A����̑O�Ɂu��v��t���������ƌď̂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�����́A���āA�������A���y�я����p�A���R�[���ł��B�����p�A���R�[�������͕������Ɉʒu�Â�����Ă���A�g�p�ʂ̏�������ďd�ʂ̂P�O���ȉ��ɂ���悤�Ɍ��߂��Ă��܂��B�K�������g�p����K�v�͂���܂��A�g�p���Ȃ��ꍇ�́A���ċ�����A�܂��͋�����Ď��ƌď̂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�ᖡ���Đ������������Ƃ���܂��̂́A������������Ɛ\���܂��āA����݂̍ō����x���P�Q���ȉ��Ƃ��ቷ���y���s�����A�Ɖ��߂��ׂ��ł��傤�B
�ŗL�̍����y�ѐF�ǍD�Ȃ��́A�Ƃ́A�����ɗD��A���F���A�킸���ɉ��F���������������A�ƂƂ炦��ׂ��ł��B
���@����
��`�́A�u���āA�Ă������y�ѐ��������Ƃ��Đ������������ŁA�����y�ѐF�ǍD�Ȃ��́v�Ƃ���Ă��܂��B
������Ɣ�r����ƁA���ĕ����̋K�肪����܂���B�Ă̎|����Nj����鐴���ł��鏃�Ď��ɂ́A�F�X�Ȑ��������݂��Ăق����Ƃ̍l�������炩�A���ĕ����͋K�肵�Ȃ������ǂ��Ƃ̔��f���������̂ł��傤�B���ĕ������ɒ[�ɉ����A���đ������Ƃ��ĕĂ̎|���Ƌ�����̉₩�����ɖ��킦�����ł����A�t�ɁA������Ɛ��Ă��������̌��Ă̂悤�Ȕ��Ăŏ��Ď�������R�N�̂�������ł������ł��ˁB�������A���Ă̂悤�Ȕ��Ăő��������́A��������͈��߂Ȃ��Ǝv���܂��B�������������ł݂悤�Ƃ�������o���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�R�N���u�߂�����ΗP�y���邪���Ƃ��v�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B���ẮA�ł��������ĕ����łU�T���ȉ����A�������p�̔��ĂȂ�U�O���ȉ����]�܂����Ǝv���Ă��܂��B�����P�V�N�x�̐��ĕ����̑S�����ϒl�͂U�U�D�U���ł�����S�̂ł́A�����������鐸�ĕ����ɋ߂��Ȃ��Ă��܂��B�������A���ϒl�ł����琳�K���z�����肷��Δ����̌����Ă͂U�U�D�U���ȏ�̐��ĕ����ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�����ƊE�ł́A���ĕ������������Ă������āA�Ⴂ�Ă𔒂��Ăƕ\�����邱�Ƃ�����܂��B�����ɂƂ��āu�F�̔����͎���B���B�v�ƌ����܂����A�����̌����Ăɂ����Ă͂܂�܂��B���ĕ�����������ΐ�������鐴���́A��i���𑝂��čs���܂��B���Ď��́A�Z�p�͂Ő��ĕ����̍�����₦��ƍl���Ă��܂������A�ԈႦ�ł����B���v�I�ɐ����́A�g�p���Ă̕��ϐ��ĕ������V�Q�����Ă��镁�ʎ��̗������݂����������ߑS�̂̏���ʂ���������ł���ƌ����܂��B����ȊO�̃W�������̐����͂���قǗ�������ł��܂���B�������A�����̏���ʂ̗������݂͐��ĕ��������Ő����ł���قǒP���ł͂Ȃ��̂ł����A�����̃W�������̒��Ŕ�r�I���i�̈�����������҂̚n�D�Ƀ}�b�`���Ă��Ȃ��̂͊m���ł��B�����������Ď����������Ǝv����̂ł�����A���ĕ����͂U�O���ȉ��̏��i�������߂ɂȂ邱�Ƃ������߂��܂��B
������A���Ď����A������ƈقȂ��Ă���_�́A���������������Ă��Ȃ����Ƃł��B����݂̔��y���x�������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B����ɂ��A�o���G�e�B�L���ȏ��Ď��邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�܂��A�������������̏��Ď��̏��i�������Ă���ꍇ�A���̒��ŁA���ɁA�����̗D��Ă�����̂���ʏ��Ď��Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
���Ď��́A����S�̂̏�����ނ��钆�Ō������͈�ԏ������A�����̒��ł͍ł�����҂ɍD�܂�Ă���W�������ł��B�������A�����܂߁A�����̃v���ł���Ӓ芯�́A���Ď���菭�ʃA���R�[����Y�����������D�ނ̂ł��B���̌������킩��ΐ������v�̉̈ꏕ�ɂȂ肻���ł����H
�n�@�{������
��`�́A�u���ĕ����V�O���ȉ��̔��āA�Ă������A�����A���R�[���y�ѐ��������Ƃ��Đ������������ŁA�����y�ѐF�ǍD�Ȃ��́v�Ƃ���Ă��܂��B
������Ɣ�r����ƁA���ĕ����̏�����P�O�������A�������͋`���t�����Ă���܂���B���ʂ̐�������⍂���Ȏ��Ƃ����ʒu�t������Ă��܂��B�����p�A���R�[���̎g�p�ʂ͋�����Ɠ������������ďd�ʂ̂P�O���ȉ��ɐ�������Ă��܂��B
��قǐ\���グ�܂����悤�ɏ��ʂ̃A���R�[���Y���������������D�݂ł�����{�������͎��̍D�݂̃W�������ł�����ǂ�������⏃�Ď��Ɣ�r����Ǝs��ł̕]���́A��ԒႭ�Ȃ��Ă��܂��B��������Ɍ����A���i�Ɋ��������Ȃ��̂ł��傤���B���������Ĉ��ނɂ͍œK�ȃW�������ł���Ǝv���Ă���̂ł����B
�Ȃ��A���Ď��Ɠ��l�ɁA�������������̖{�������̏��i�������Ă���ꍇ�A���̒��ŁA���ɁA�����̗D��Ă�����̂���ʖ{�������Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�j�@���薼�̐���
����܂ŏq�ׂĂ���������A���Ď��y�і{�����������킹�ē��薼�̐����Ə̂��A���̑��̐����́A���ʎ��ƌĂ�ł��܂��B
���薼�̐����ɂ́A���ʂ̋`�����ۂ����Ă��܂��B��́A���ĕ��������x���ɕt�L���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA������́A�����ẮA�_�Y�������@�ł̂R���ȏ�̂��Ă��g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B
���������āA���Œ��̒�`�ɂ��A���đ������͍ł������Ȑ����ł���A�ȉ��A�������A���ċ�����A������A���ʏ��Ď��A���Ď��A���ʖ{�������A�{�������A���ʎ��̏��ɐ����̃����N�������m�����Ă��邱�Ƃ����������������邱�ƂƑ����܂��B
���̂悤�ɁA�����̐��@�i���\����ɂ��Ύ�������ɂ�炸���̎����̐����ł��邱�Ƃ��킩��܂�����A�w������ꍇ�̖ڈ��Ƃ��đ�ϖ��ɗ����܂��B������ɁA���̋�������������܂��̂Ŋ����Ƃ͌����܂��A�����N�Ȃ�̎����͕ۏ���Ă���A�Ƃ��l���������B
������A�w������ꍇ�̂����߃`�F�b�N���ڂ�����܂��B���t�ł��B����܂ŁA�����̎s�̐���������������@��܂������A�c�O�Ȃ���A���薼�̐����̒��ł������ɖ��L��Ƃ��鐴���Ɏ��X�o��܂����B�����ɋ��ʂ���_������܂��B���ŕr�l�߂���Ă���̓������啝�Ɍo�߂��Ă���̂ł��B��́A�r�l�ߌ�A�R�������߂��������肩��F�X�Ȗ�肪�����ė���悤�ł����B���́A�����͐��N�H�i�ł���A�ƍl���Ă��܂��̂ŁA�����̎����́A�𑠂��o�������ō��ł���Ǝv���Ă��܂��B�������A�̔��G�������S���ɍL������̎�������ł́A�������ω����Ȃ��悤�ɔz�����ďo�ׂ���Ă���悤�ł�����A���̏��i�͂���قǓ��t���C�ɂ��Ȃ��Ƃ��ǂ��ł��傤�B�`�[�t�u�����_�[����������Ǝ����̊Ǘ������Ă���ƍl�����邩��ł��B
���ɂ����t���C�ɂ��Ȃ��ėǂ���������܂��B���R�̂��Ƃł����n���蕨�ɂ��Ă��鐴���Ɋւ��ẮA�r�l���t�͂���قǏd�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�z�@���Ď��ƃA���Y���A�ǂ��炪�|��
��قǐ\���܂������Ď��ƃA���Y���̗D��ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B���Ď��͔Z�����̑�\�ƌ����܂��B�A���R�[���Y��������������A���Y���͂��������������ɂ�����ƌ����邱�Ƃ�����܂��B���͋t�ŁA�A���Y���̕������̃o�����X���Ƃ�Ă��ē����悤�ɏ������ꂽ���Ď��ƈ��ݔ�ׂ��ꍇ�A���Ď�������������������A�Ɛ\���܂����B�����������邽�߂ɍy�ꂪ����ݒ��łǂ̂��炢���𗬂��ăA���R�[�����y�������ׂĂ݂܂��傤�B���Œ������J���Ă���܂������P�U�N�x�S�����������̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA���Ď��̂���ݒ��ōy��́A���ĂP�g��������R�W�U���b�g���̃A���R�[���Y���A�A���R�[���Y�����̑�\�ł���{�������̂���݂ł́A�y��͂R�U�U���b�g���Y���Ă��܂��B���ĂP�g�������菃�Ď��̕����Q�O���b�g���]���ɃA���R�[���Y���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���������Ď���ۂɍy��ɂ�����X�g���X�͏��Ď��̕����A���Y�����傫���̂ł��B����݂̖����ɂȂ�ƁA�y��͔w���킳���X�g���X�ɂ�莀�ŗ����㏸���܂����A���ȂȂ��܂ł��X�g���X�ɂ�薡�Ɉ��e�����y�ڂ���������o���Ă��܂��\��������܂��B�ł�����A��������������ς��Ȃ���Βʏ�̓A���Y���̕������Ď������������͂��Ȃ̂ł��B���C���ł́A�t�ɃV���[���E���[�Ə̂��y������ł���������y�v�`�h���̎|�������Ŗ��̐[�݂�t�^���鐻�����@������܂����A�A�~�m�_�x�̍��������͂��łɏ\���ȃy�v�`�h���̎|���������ܗL���Ă���A�����̐����͏��Ȃ������������������ƕ]������܂��B
�܂��A�A���R�[��������݂ɓY�����܂��Ɠ��R�̂��ƂȂ���A���R�[���x�����オ��܂��B�オ�������Ƃɂ��A���Ď��ɂ����ꍇ�͏㑅���Ɏ𔔂ɋz������鍁�C�������A���𒆂ɒ��o�����\��������܂��B���̓_����������Ɋւ��ẮA�A���Y���ɊM�̂��オ��̂ł����A�����͈���Ă��܂��B
���łɐ\���グ�܂��ƁA���C�����A���Y���邱�Ƃ�����A�t�H�[�e�B�t�@�C�h�i�͂Â���̈Ӂj�Ə̂���A���R�[���x���̍������C����ꍇ�Ȃǂɍs���܂��B���̏ꍇ�A�Y�������A���R�[���̓u�����f�[�ł��B
�i�T�j�����A���J���g
���薼�̐����ȊO�ɂ������ɂ͐F�X�Ȏ�ށA���ޕ��@������܂��B�v�����܂܂ɂ����ɂ��ċL�q���Ă݂܂����B
�C�@�Î��ƐV��
��ʓI�ɂ́A�㑅�����Ă̐�����V���Ə̂��A�Ă��z�����悭�n�����������Î��Ə̂��܂��B�������A�Z�p�̐i���ł��̒�`���������Ȃ��Ă��܂����B�X���ɐV�����ł���悤�ɂȂ����̂ł��B���̎�������̒��ɂ͈ȑO�����N���������Ă���Ђ�����܂����A�ŋ߂ł́A��[�Z�p�����B���n���̏����Ȏ����������N�������悤�ɂȂ����̂ł��B
���ʂ��邢�͎�Ԃ������m�ł��傤���B���ẮA��������ł͐V�����ł������Ƃ�m�点�邽�߂ɓX���ɒ݂邵�����̂ł��B�����āA�݂邵�����ʂ����犌�F�ɕω�����ƈ��ݍ��ł��A�̃T�C���ɂȂ����̂ł��B�����ƊE�͌×��A����҂ɐ��ʂ̐F�ő����̎�����m�点�Ă����̂ł��B�������A�ŋ߂́A���N���݂邳��Ă���悤�Ȋ��F�̐��ʂ�����������A�݂邵�Ă����Ȃ�����������������肵�܂��B
�ł́A�����́A�ǂ̂��炢�n��������̂��ǂ��̂ł��傤���B����́A�n����������Ən�����ɂ��܂��B�������Ĕ��������{�����╁�ʎ��N���X�̐����ł́A�~�G�ɑ����Ă��퉷�ʼnz���ΏH�����痂�N�̂����������肪��Ԃ̈��ݍ��ł��傤���B����N���X�ʼnĂ��R�O���ȉ��Œ������ꂽ�̂ł���A�H����������������߂܂����A�ȍ~�́A�v�X�n���ɂ�����������������Ă䂭�ƍl�����܂��B���݂̑������́A�ӕ]��̂Ƃ���ŐG��܂����悤�Ƀt���b�V������ۂ悤�ɂT���ȉ��̒ቷ��������O��ł��B���̂悤�ɒ�������Ɣ����������������܂��B����X���n�̍y��ő���ꂽ���肪���₩�Ȉꎞ��O�̑������́A�ቷ�ł��퉷�ł�����Ȃ�ɏn���������������ނ��Ƃ��ł��܂��B��ɏ퉷���������ɂ�肻�̐^���������������̂�����܂��B���ɁA���ɂ̐��������̔��e�ɓ���ƍl���Ă���܂��B
���@�M����
�n�����i�ނƉv�X���������Ȃ鐴���̒��Œ��Ì��̎�������܂��B���ꂪ�M�����ł��B������͌×������̘V���ōs���Ă������@�𐴎������ɉ��ǂ������̂ł��B�ʏ�̐��������ł͐���p���Ă���݂�N�����܂����A�M�����ł͐��̈ꕔ�ɏ��Ď����g�p���܂��B���̂悤�Ɏd���݂܂��ƁA���d�����I���������_�ł���ݒ��ɑ����ʂ̃A���R�[�����ܗL����邱�ƂɂȂ�܂�����A�y��̔��y�͂���ቺ���܂��B���̌��ʁA�ł��オ���������́A���y���ɖ��Ȃ��߃A���R�[���x�����Ⴍ�A�Ԃǂ������c�����Â����ɂȂ�A����ݒ��̍y��͑����ȃX�g���X���邱�ƂɂȂ�̂Ŏ_�x��A�~�m�_�x���ʏ�̂���݂̔{���炢�ɂȂ�܂��B�V���̓��ł��Â����̔Z�������ŐH�O���Ƃ��Ă͍ō��ł����A��͂�A�퉷�łQ�N�ȏ�n�����������̂ɂ͂��Ȃ��܂���B���Œ�����������Ŕ�������܂������A���ł͂���قǔ̔��ʂ������Ƃ͌����Ȃ��ł��B�������A����͒ʏ�̐����Ɠ����R���Z�v�g�Ŕ̔�����Ă������ʂł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�M�����́A�Ì��̏n�����Ƃ��čō��ł��B���t�̎��̎��A�~�������܂�Ă���s�o�n�Ȃǂ���܂ł̐����̏���`�ԂƂ͈قȂ�@��Œ���j�b�`���i�ł���Ƃ͎v���܂����A�啝�ȏ���ʂ̊g�傪�����܂��Ƒz���ł��܂��B
�n�@���������Ƃɂ����
����݂̈ꕔ�������ɍ��������悤�ɔ�����������������ɂ�����Ȃǂ𐴎��̐V���i�Ƒ����܂��ƁA���ő�̃q�b�g���i�ƌ����܂��B����݂�]�����鎞�́A����݂����ɂ��܂��̂Ŏ��ɂ́A����������ɂ�����ɑΛ����܂��Ǝd�������Ă���悤�ȋC��������A����͔����i�ł���Ƃ����ӎ����N����܂��B���̂��߁A���������̗ނ͍D���ɂȂ�Ȃ��̂ł����A�ꕔ�̐���}�̕��X�ɂ́A�ǂԂ낭�ւ̃m�X�^���W�[���A���������F�����̂������낳���A���Ƃ��Ĕ��ʂȒY�_�K�X�̂���₩�Ȗ��킢���A�킩��܂����\�l�C������܂��B
�����܂ł����������́A���ݎ��Ƃ����Ӗ������������Ă��܂��B�܂��A�@����̐����̒�`���A�āA�Ă������A���������Ƃ��Ĕ��y�����āg���������́h�A�ł��B
�g���������́h�łȂ���ΐ����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA����������ɂ�����Ƃāg�����Ȃ���h�Ȃ�܂���B���̂��ߏ㑅����i�����j�ꍇ�́A�ʏ���ڂ̑e���z����ԂȂǂ𗘗p���܂��B�܂��A�㑅���O�ɂ͂���݂Ƀ~�L�T�[����̝��a�@�𓊓����Ĕ��y���ɗn���c�������ĂƂ������Ăӂ��Č����悭�g������h�悤�ɂ��Ă����܂��B���̂悤�ȏ㑅���@���Ƃ�܂�����Ă̗��q���܂݂Ȃ��犊�炩�Ȑ�G�肪�����ł��܂��B
����������ɂ�����́A�y�ꂪ�𒆂Ő����Ă��邩�ۂ��ɂ��Q��ނɑ�ʂ���܂��B������搂��Ă���ꍇ�́A�㑅�����܂܂̐��������̂܂��i�Ƃ������̂��唼�ł���ƍl�����܂��B���̏ꍇ�́A�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂��B�Ĕ��y�̉\�������邩��ł��B���Ɍo��������������������邩������܂��A�w�����������������J�������r�[�A�Y�_�K�X�ƂƂ��ɒ��g�����ӂ�o����A�������Ĕ��y�̂��߂ɕr���̈��͂����܂���������邱�Ƃ�����܂��B��������ɂ��������ӔC�@���K�p����܂��̂ł��̂悤�Ȏ��̂����������ꍇ�͑�ςł��B�ł�����A�������𒆂̍y��̊��͂�K�x�ɒቺ�����邱�Ƃ��K�v�ŁA���̂��߂̃m�E�n�E�����݂��܂��B�܂��A���̂悤�Ȏ��̂��܂������N�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�r�l�ߌ�A�Γ�����s�����𒆂̍y������S�ɎE�ۂ��Ă��܂��̂ł��B���̂悤�ɂ���Ύ��������肵�����Ԕ���������ۂ��Ƃ��ł��܂��B�ɂ�����͂��̗l�ɑ����Ă��鐴����������������܂���B�������A�Γ�������܂��ƁA�ǂ����Ă��t���b�V������������悤�Ɋ����܂��B����������ɂ�������w������O�ɂ́A�Γ��ꂵ�Ă��邩�ۂ������m�F���������A���D�݂ɂ��������i�������߂��������悤�ɂ����߂��܂��B
�j�@�����Ɛ�������
�ቷ�������h�ߋZ�p�̔��W�ɂ��Γ���E�ۂ����������̂܂܂ł̏o�ׂ��\�ɂȂ�܂����B�Γ���E�ۂ��s�킸�ቷ�Œ������܂�����t���b�V���������Ȃ�ꂸ�A�㑅�����Ắi�������ẮA�܂��́A���ڂ肽�Ắj���������킦�邽�ߑ����̐����t�@�����l�����邱�Ƃ��ł��܂����B����������ɂ�����Ɠ��l�ɁA�����ƊE�̐V���i�Ƃ��Ă͑�q�b�g�̈�ł��B�������A�����ŗ��ʂ�����ɂ͊댯�������܂��B�r�l�ߒi�K���h�߂ɂ�芮�S�ɉΗ��ۂ��h��������Ƃ��Ă���C�ł��������Ă���Ύ��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɑ��B�������Ȃ����ꂪ����̂ł��B����ȐS�z���������A�������̎��{���̖��킢���y����ł��炨���Ƃ����Ӑ}�ŊJ�����ꂽ�̂����������ł��B���t�̂Ƃ���A���Œ������܂����A�r�l�ߎ��ɉΓ���E�ۂ���̂ł��B�������邱�Ƃɂ��Η��ۍ����̉���Ɛ����̖��킢�𗼗������邱�Ƃɐ��������̂ł��B�������A����_������܂��B�Γ��ꂷ�邱�Ƃɂ��𒆂̒`�������M�ŕϐ����𒆂ɗn������Ȃ��Ă��܂��̂ł��B�ł�����A���������ɂ͂����I�����o�����邱�Ƃ�����܂��B�ɂ�����ƈقȂ�A���ݎ������҂��Ă���݂Ȃ���͌����邩������܂��A������̖�肪����킯�ł͂���܂���̂ŁA�ǂ����A�I���̂��Ƃ͋C�ɂȂ��炸�ɖ�����Ă��������B�ʏ�̐����ł���ΉΓ���̌�A�����Ԓ������܂����炱�̊ԂɃI����������A�r�l�߂̍ۂɂ�����邱�Ƃ��ł���̂ŏ��i�ɃI�����o�����邱�Ƃ͂���܂���B
�����ʼnΗ��ۂɊւ��邨�����낢���b����B��y�̊Ӓ芯�������Ă������Ƃł����A�Η��ۂɐN���ꂽ���Ȃ̂ɂ���������������������A�̂������ł��B���͂��܂�_���I�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A�^������Ӓ芯������܂��B���̎��́g���̓��������h�A�ƌ����A�Η��ۂ��ɐB���Ă���̂ł�������ō������m�F�ł���悤�ɂȂ钼�O�̐����̂��Ƃ�\���̂������ł��B�Ђ���Ƃ��Đ����t�@���̒��ɂ́g���̓��������h�ɂ߂��荇����݂��ɂȂ����������������邩������܂���B�m���ɁA�����Ȑ�����r���ƐU����r�[�A�����������Ƃ�����܂����B����́A�Η��ۂ��ڎ��ł��Ȃ����x�ɔɐB���Ă��ĐU���Ȃlj��炩�̎h�����������邱�Ƃɂ���C�ɂ��݂��ɂ����������ăI���ƂȂ錻�ۂł����A���̎��́g���̓��������h�ƌ�����̂ł��傤���B�������A���������ǂ����܂ł͊m�F���Ă��܂���B
�z�@���A������
�����ɔ��A�������������������Ƃ������i������Ă��܂��B���āA�����ƊE�S�̂Ŕ��A���蕨�ɂ����p���`���[�g�Ƃ������i���J���������������Ƃ�����܂��������s���܂����B���̌���������̎�������Ŕ��A����������������܂��������̊Ԃɂ������Ă��܂��܂����B�����Ɣ��A���͑��e��Ȃ����̂Ȃ̂��ƍl���Ă��܂������A�������������������ł����A���̏��i�͉\�ł��邱�Ƃ��ؖ�����܂����B
���A����ނ���@�͑傫��������Ɠ����܂��B��́A���y�r���ŗe��𖧐��܂��͈��͂�������悤�ɂ��Ă����̂ł��B�������邱�Ƃɂ�蔭�������Y�_�K�X������݂���̒��ɗn�����܂��邱�Ƃ��ł��܂��B�ǂ̂��炢�̒Y�_�K�X��������̂������������Ȃ���Ȃ�܂��A���y�����y�ꂪ�I���ɂȂ��Ďc��܂����炱����ǂ��������邩�ȂǓ����肪����܂��B�������A���i�́A�A�������ǂ��A�ׂ��ȖA���Â��ɗ������Ƃ���͂ƂĂ����ꂢ�ő�ϖ��͂����������܂��B������͕r�l�ߎ��ɒY�_�K�X���𒆂ɐ������ݗn�����܂�����@�ł��B�O�҂̑�\���A�������A�r�[���y�уV�����p���A��҂̑�\�����ł͂���܂�������Y�_�����ł��B��҂̒����́A�J�[�{�l�[�^�[�Ƃ������u������ΊȒP�ɔ��A���������Ƃ���ł��B
����܂ł̂Ƃ��됴���̐��E�ł́A������������y�K�X�������ߖ@�ɌR�z���オ���Ă��܂��̂ő���Ƃ�����̕��@�Ɋ��ׂ��ł��傤�B�K���A�Q�O�O�U�N�T�������Ŗ@����������A�Ԃǂ����̂���݂ւ̓Y�����F�߂��܂����̂ō��܂ł��ȒP�ɔ��y�K�X�������ߖ@�̔��A�������̐������ł���悤�ɂȂ�܂����B�ǂ����ő�X�I�Ɉ������A���̐������Ă��������܂��ˁB
�w�@����{
�̂́A�g��̐���{�h�Ƃ��Ďg���Ă��܂������A�����ł͎��Ƃŏ����������Ď����Ӗ����閼�̂ɂȂ��Ă��܂��B�ŋ߂ł͒������Ȃ�܂������A�������s�����Ă������a�U�O�N�ȑO�́A��������̊Ԃʼn��P�ʂł̌����̔������s���Ă��܂����B���l�ɕ\������n�d�l������ɍs���Ă��܂����B���̂悤�Ȃ��Ƃ����������ߎ��ЂŐ����������Ď��Ɖ��ōw���������Ď�����ʂ����������̂ł��傤�B
�g�@�F��
�����́A�F���y���ގ��ł͂Ȃ��Ɛ\���グ�܂������A����y�̂��w�͂Ńj�b�`���i�ł͂���܂����F���̐�������������Ă��܂��̂ł������Љ�܂��B
�i�C�j�������̐F�f�𗘗p
�������ۂ̒��ɐԂ��F�f�Y������̂����肻�̐F�f�𗘗p���Đ�����ԐF�ɂ��܂��B���݁A���̐F�f�͓V�R�̐ԐF�F�f�Ƃ��ĐH�i�̒��F�ɉ��p����Ă��܂��B�V��������������̔����ł���A���{�ōŏ��ɐ����̒��F�ɐ����������i�ł��B
�i���j�A�f�j���v�����̍y��̗��p
�A�f�j���Ƃ������������݂���Ɣ��炪���i�����y�ꂪ����܂��B�A�f�j�����������ɂ͐���͒x��܂����A�ۑ̓��ɐԐF�F�f��A�f�j���̑�p�������܂��B���̍y�ꂪ���Y����ԐF�F�f�𗘗p����ΐԂ���������܂��B���Œ����������ꂪ���������y��ł����A���͂��̂��߂ɗ�⊾���������ꂽ�o��������܂��B�����́A���Œ������������������������̂́A�Ӓ芯����]�����������֗Տꂵ�ď����w�����s���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������邱�ƂŋZ�p�ړ]���~���ɍs��ꂽ�̂ł��B�����A�Ƃ����������Ɏw���ɂ����������̂ł��B�����đ���ڂ́A�݂��Ǝ��s���܂����B�Ԃ��Ȃ�Ȃ������̂ł��B�Ԃ��Ȃ����͎̂��̊�̕��ł����B�����́A�w�������������̂ł͂Ȃ��A���Œ�����������̏����ɕs���ȓ_������A���̍y��ɉ�������ăA�f�j���v�����̍y��̏��x���P�O�O���ɂȂ�Ȃ������̂ł��B�Q��ڂɂ���Ɛ^���ԂȂ���݂�M�������߂����Ƃ��ł��܂����B���̎�������ł́A�ȗ��A�Ԃ��ɂ�����ƒʏ�̔����ɂ�����Ƃ̍g���Z�b�g��̔����Ă�����͂��ł��B
�i�n�j�Ă̐F�f�𗘗p
���݂͌Ñ�Ẵu�[���ŐԂ⎇�F�̌��Ă����݂��邱�Ƃ������m�̕��������Ǝv���܂��B���̐F�f�𗘗p���Đ����𒅐F���܂��B
�ȏオ�F������Ƃ��������ł����A���ׂĂ��ԐF�n���̐F�ł��B��y�̒��ɂ͗ΐF�̐���������Α�O���̎��Ƃ��Ĕ̔��ł���̂ɁA�Ə�k�����ɂ�����������������܂����B�ԐF��͔̂�r�I�ȒP�Ȃ̂ł�����͓���̂ł��B�܂��A�F�f�͑ސF���܂����A��L�̐����̐F����O�ł͂���܂���B���ɓ����ɓ��Ă�ƑސF���x�������܂��B�w�����ꂽ�瑁���̏���������߂��܂��B
�`�@������
���������邱�Ƃ������m�ł��傤���B�P�O�O���A���R�[���̋Ìœ_�i�Z�_�j�́|�P�P�V���ł����A��ނ̋Ìœ_�̓A���R�[���x���Ƀ}�C�i�X��t�������x�ɋ߂��ƌ����Ă��܂��B���Ȃ킿�A�����́|�P�T���A�r�[���ނ́|�T�����ł��B�����́A�Ìœ_��菭���Ⴂ���x���ɂ����܂��ƈ�x�ɑS�̂�����̂ł͂Ȃ����X�ɓ����Ă����܂��B�����������͏����Ȑ��ɋ߂��̂ŁA�t�̂̕����̓A���R�[���x�����㏸���邱�ƂɂȂ�܂��B�K���ȂƂ���Ōʼnt�������s���A�X�̕�����n������ƁA�Z�x�̈قȂ�Q�̐������ł��܂��B���Ȃ킿�A����Ȃ����������̓A���R�[���Z�x�������A�����������͒�Z�x���ɂȂ�܂��B���_�I�ɂ͂P�O�O���߂��Z�x�̐����ƂO���ɋ߂��������ł��܂����A�Q�O�O�U�N�̎�Ŗ@�����łQ�Q���ȏ�̃A���R�[���x���̎��͐����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��Ȃ�܂����̂Ō��݂ł́A���Z�x���̍ō��̃A���R�[���Z�x�͂Q�P.�X���ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�������̐������@�́A���݂͓�����ɂȂ��Ă��܂����A�������Œ��ɓ������ĊԂ��Ȃ��������Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�ƋL�����Ă��܂��B�������A���ɐ�O�ɂ́A���������������Z�x�̈قȂ鐴���邱�Ƃ͒m���Ă����悤�ł��B�吳���ォ�珺�a�̏��ߍ��܂ł́A�����ƊE�͍Ő�[�̎Y�Ƃł������̂ł��B�����Ō����o�C�I�Y�Ƃ̂悤�Ȉʒu�ɂ������ƍl�����܂��B�����ƊE�ɂ͗D�G�Ȑl�ނ���������W�܂��Ă��܂����B���̕��X�������Ɍ������������ꂽ�̂ō����̐��������̋Z�p�I�ȑb���ł����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B�����̌����_���������f�ڂ�����������Ƃ����G��������܂����A����͐V���������┭�����ȂƎv���A�O�̂��ߏ��������������Ɗ��ɔ��\����Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��A��������\�N�O�ɁB�������̂��Ƃ��l����ɂ��A�̂̊Ӓ芯���тɐ����Ɋ֘A�����Z�p�҂̗L�\�����v���m�炳��܂��B
���@�������x�[�X�Ƃ������L���[���ƃX�s���b�c
�����ƊE�́A�p���`���[�g�Ɠ����悤�ɐ������x�[�X�Ƃ������L���[���ƃX�s���b�c���J���������Ƃ�����܂������A���s�ł����B���݁A�����x�[�X�̃��L���[���ōő�̔̔��ʂ�����͔̂~���ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����I�ɔ���Ă���킯�ł͂���܂���B���́A���傤�����g�����������L���[�����Ă݂܂������A�]���͎v�킵������܂���ł����B�����́A�W��Ȗ��킢�̎��Ȃ̂ł������̂����L���[����X�s���b�c�̃x�[�X�ɂ͌����Ă��Ȃ��悤�ł��B�������A�n��̓��Y�i�Ɛ�����g�ݍ��킹�����L���[���y�уX�s���b�c�ł��y�Y�ɂȂ�j�b�`���i�邱�Ƃ͉\�ł���Ǝv���܂��B
�k�@�����ƃq����
�����x�[�X�̃��L���[����X�s���b�c�ɋ߂��W�������̂��̂��̂��炠��܂����B������q�����ł��B�����͔����������̑㖼���ɂȂ��Ă��܂����A�{���ɂ����Ȃ̂������Ƌ^��Ɋ����Ă��܂����B�R�O�N�ʑO�Ɋ⋛�̍����������Ƃ�����܂��B��J�Ă̂��[�݂̂����������M�ɏĂ��ꂽ���h�Ȋ⋛�������āA�����ɔM�����������܂�܂����B���Ȃɋ����S���ʼn��݂���܂����B�ꓯ�������𖡂������Ɋ⋛����̂���⋛�Ǝc�����M�����ĂёS���Ŗ�������ƋL�����Ă��܂��B����}�̕��́A��������Ă������ł��ˁB�������A���ʔ������������Ƃ����L��������܂���B�t�ɂ��������Ȃ������A�ʁX�ɖ�����������������������̂ł́A�Ƃ����v�����c���Ă��܂��B
���鎞�A�ӂƂ��̌������킩�����悤�Ɏv���܂����B�����͔��������ƌ���ꑱ���Ă����̂ł����A���͍����ɂ��鐴���Ɍ������Ă����̂ł͂Ȃ��̂��ƍl�����̂ł��B�̂̐����́A�_�x�������A�G�L�X�������Ȃ����h���ł������Ɛ��@�ł��܂��B���������āA�_�x�����Ȃ��Ȃ��ĊÂ���������悤�ɂȂ�Ɣ��������Ȃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��قǂ̊⋛�̍����̂悤�Ȉ��ݕ�������A������A�~����J���V���[���Ȃǂ̃A���J���������������ɗn������ł��܂��B��������ȑO�̐����ł́A�_�x���ቺ���Â��A�|����������悤�ɂȂ����A�ƍl�����܂��B�������A���݂̐����͂������̂��ƂR�O�N�O�̐����ł����Ă��_�x�́A��������̔������x�Ȃ̂Ŏ_�x���������Ă����������͂Ȃ炸�A�t�Ɏ_�x���Ⴂ���߂Ƀ{�P���悤�ɂȂ��Ă��܂��z�����Ă����قǂ̊������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B
���l�̂��Ƃ��q�����ɂ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł��Ԃ����q����p����Ƃ������Ƃ́A�听���ł���J���V���[���𐴎𒆂ɗn���₷�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
������q�����t�@���́A�Ɠ��̍��������D���Ȃ̂ł��傤���A��ʂ̕��́A���Ɛ����͕ʁX�ɐH���݂̒��ňꏏ�ɂ��������ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���@��A���R�[���Z�x��
���ݔ̔�����Ă����A���R�[���Z�x���̑�\�͐�ɂ��b���܂������A���ł�����g�������h�ł����A����ɑ������͓̂����ߍx�̎�������̃O���[�v�����ꏤ�W�������Ă���g��킭���h�Ɓg��̕��g�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�����̃A���R�[���Z�x���������ꍇ�A�ǂ̂悤�ɂ��Ĕ������J�o�[���邩������ł��B�������͒Y�_�K�X�A��̕��͋�����Ŕ������J�o�[���Ă���悤�Ɏv���܂��B�����́A����ݒ��ŃA���R�[���x����ቺ�����邽�ߐ��x�ɕ����Đ��������܂����A�����ɂ������Ă������鑀����J��Ԃ�����������o�����閡�Ŕ������J�o�[���Ă��܂��B�����R�O�N�����Z�p�҂��S���Œ�Z�x���������ΏۂƂ��Ă��āA���̌��ʁA���i�Ƃ��Đ����c���Ă�����̂��R�ł����琴���̒�A���R�[�����͔@���ɓ�������������������邱�ƂƑ����܂��B
�P�O�@��ʈ����̊댯��
�@�A���R�[���̈Í��̖ʂɂ��G���`��������Ǝv���܂��̂ŁA�Ō�Ɏ��グ�܂����B
�A���R�[�����ʂɐێ悵���ꍇ�̊댯���́A�}���Ɩ����Ƃ�����܂��B�A���R�[�������ݎn�߂ē��̐�҂��ׂ�₷���̂��}���̃A���R�[�����łł��B��C���݂��������Ȃǂɔ��ǂ��܂��B�����ɂ�茌�t���̃A���R�[���Z�x���㏸���܂��ƁA���̔Z�x�ɂ��]�͗l�X�ɉe�����܂��B�ʏ�A��]�\�ʂ́A�������畦���オ���Ă���l�X�ȗ~�]��}�����a�m�i������ԓx����点��悤�Ɋ������Ă��܂��B���̕������A���R�[���ŏ�����Ⴢ����i�K���A������ق됌���ł��B���i�͗}�����Ă��鐔�X�̊���\��₷���Ȃ�܂��B�{���Řb���ł��L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ����Ă�i�K�ł�����܂��B���̈ʂŎ~�߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A����Ɉ���ʂ�������ƌ����̃A���R�[���Z�x���㏸������ɔ����Ăǂ�ǂ�]�̐[������Ⴢ��Ă䂫�A���A�D�����o�č�����ԂɊׂ��Ă��܂��܂��B������ԂɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�]�̍Ő[���Ő��������Ɍ������Ȃ��ċz�𐧌䂷�镔���Ȃǂ��\���Ȋ������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����Ԃł���ƍl�����܂��B�ň��̏ꍇ�͐����������ێ��ł��Ȃ��Ȃ莀�Ɏ���܂��B�ł�����A��C�݂̂����v���邱�Ƃ́A�E�l�߂�Ƃ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ł��B�A���R�[���������y���ނƂ��́A���̊댯���玝�����킹�Ă��邱�Ƃ���ɐS�̂ǂ����Ɏ����Ă��������������̂ł��B�����A���R�[���Z�x�Ɛg�̂ւ̉e���ɂ��ẮA�����悻�\�[�Q�����A���R�[���Z�x�Ɛg�̂ւ̉e���̂悤�Ɍ����Ă���܂��B
�i�\�\�Q�@�����A���R�[���Z�x�Ɛg�̂ւ̉e���j
�����́A�݂Ȃ��܂������̃A���R�[�����łł��B���̋��낵���͏\���������̂��ƂƎv���܂��̂ō��X�����͂������܂��A����ł����łɂȂ�\�������邱�Ƃ����������܂��傤�B�������̐E��͎d�����A���ɐڂ���@������̂ŁA�A���R�[�����ł���������y�����l���m���Ă���܂��B���̐l�B�ɋ��ʂ���̂́A�����ɋ������Ƃł��B�ނ�قǂ���������A�Ⴂ���̎��̓A���R�[�����łɂȂ�O�ɑ��̓��������œ��@���邱�ƂɂȂ����ł��傤�B�s�K�ȕ\����������܂��A�A�����ɂȂ�ɂ��A���R�[���ϐ��ƌ����f�����K�v�Ȃ̂��A�ƍl���Ă��܂����B���ɂ͂���ȑf���͂Ȃ�����A�����ɂ͐���Ȃ��A�Ƃ��ŋ߂܂Ŏv���Ă��܂����B�������A���낵�����Ƃɑf���͉��P�H����邱�Ƃ�m��܂����B���́A�N�ƂƂ��ɁA���߂�悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�Ⴂ���͕p�ɂɓ�������ɂȂ����̂ł����A�ŋ߂͈����̗����ɋC���������Ȃ邱�Ƃ��߂����ɂ���܂���B�������A��Ԃׂ����Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�A���R�[�����ӂ��̊O�֔r������@�\���������̂ł͂Ȃ��̂ł��B���̗l�ȏ�Ԃ���w�I�ɂ́A�u�A�Z�g�A���f�q�h�ϐ�����������ԁv�Ɛ\���̂������ł��B�����ėǂ����Ƃł͂Ȃ��ƌ����܂����B���̂ł��傤���B�A���R�[���͑傫���Q�i�K�ő�ӂ���܂��B���i�K�ŃA�Z�g�A���f�q�h������������i�K�ł��̃A�Z�g�A���f�q�h���Y�_�K�X�Ɛ��֕��������̂ł��B���͑��i�K�Ő��������A�Z�g�A���f�q�h�ł��̕����̌����Z�x�������Ȃ�ƋC���������Ȃ�ȂǓ�������̏Ǐo�����A�������߂Ȃ��Ȃ�̂ł��B���Ƃ��Ǝ��ɋ������͑��i�K�̑�ӑ��x���������ߌ����̃A�Z�g�A���f�q�h�Z�x���������Ă���ԁA�Ⴂ�̂ł��B�ł����炨���ɋ��������̂ł��B���͂��Ƃ��Ƒ��i�K�̑��x���x���A�Z�g�A���f�q�h�����܂�悤�ȑ̎��ł����B���ꂪ�A���N�̈����K���ɂ�菙�X�ɃA�Z�g�A���f�q�h�ɑ��ϐ����l�����Ă������̂ł��B�܂�A�Z�g�A���f�q�h�̍�p�ɑ��݊��ɂȂ����̂ł��B�{�l�ɂ��Ă݂�Δ�����������������������߂�悤�ɂȂ��ėǂ������ƍl���Ă��܂����B�������A�A�Z�g�A���f�q�h�ϐ����l�������ƌ������Ƃ͑�ʂɈ�������ƌ����̃A�Z�g�A���f�q�h�Z�x�������Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����܂��B���̌��ʁA�����_���Q�O���Ƒ̉����Ⴂ�A�Z�g�A���f�q�h�́A�x�Ŏ_�f�ƒY�_�K�X���������鎞�Ɍ�������ċC���ɏ������Ă���̂������ł��B�C��������������悤�ȓŐ����������A���A�Z�g�A���f�q�h�̏��C���ċC�ƂƂ��ɔx����@�ւƏオ���Ă���̂ł��B���̐�y�Ŏ�̕t�߂̊��ɜ������y�����Ȃ�̔䗦�ł�������Ⴂ�܂��B���̎�����m�炳�ꂽ���A�\�z���Ă��鎀��������܂ł̊̑�����������ɕς��܂����B�̑�����ɂ��Ă����̂́A���Ċ̉��Ɛt�������㎀�Ɉꐶ����������ł��B�������A���݂͂܂��̑�����ɂ��Ă��܂��B����́A��̎�����m��������ł��B����������y�͂��ׂăw�r�[�X���[�J�[�ł����B�A�Z�g�A���f�q�h�Ǝ����Ɋ܂܂�锭�������̑��ݍ�p������U�����Ă���A�ƍl������������I������ł��B�V�O���炢�܂ł̐�y�͔�i���҂������A���̐l�����ɂ͍A�����ǂ���l�����Ȃ��̂ł��B�������A�����Ă܂����A���݂̎��̓A�����ɂȂ��f����L���Ă��܂����̂ł��B���Ɠ��l�ɔN���Ƃ��Đ̂�����ʂ����������̓A������S�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�A���������낵����A�������i�����T����ׂ��Ȃ̂ł��B
�Ȃ��A�A���R�[���ϐ����������ŎႢ���납����ɋ����A�����̑f����L���Ă�������͍A�����ɜ��\���͒Ⴂ�Ǝv���܂��B���̂悤�ȕ��ɋ��ʂ�������ʂ̕ϑJ������܂��B�Ⴂ������ɋ�������ƂƂ��Ɏ�ʂ��������Ă��Ă���͂��ł��B�̂͂����ƈ��߂��̂ɁA�Ƃ����������̓A�Z�g�A���f�q�h�̊Q�ł͂Ȃ��A�����݂̂�S�z����ׂ��Ȃ̂ł��B�������A�i���ɂ��A������ɜ�郊�X�N�́A�����Ȃ邱�Ƃ͂���܂��炲�p�S�������B
�Ō�͏����|���b�����܂������A�`���\���グ�܂����悤�ɓK��������S���������U�̗F�Ƃ��Ĕ��������H����ʂ��Ċy�����l���𑗂낤�ł͂���܂��B