三国史記と日本書紀
古代朝鮮について記載した三国史記は1145年に完成した、日本書紀よりも4世紀も新しい歴史書だ。しかし、現存していない新羅本紀、高句麗本紀、そして日本書紀にも記載がある百済本記の内容は継承していると考えられる。
新羅本紀 第二助賁尼師今四年は西暦233年に当たる。5月に倭兵が新羅東海岸に侵攻し、伊飡の于老が倭人と戦い、風を利用して倭人の船に火をかけ、水死させたと記述される 沾解尼師今三年は西暦249年に当たる。伊飡、舒弗邯は官位で舒弗邯となった于老は倭人に殺されている。
助賁尼師今
四年, (中略) 五月,倭兵寇東邊。秋七月,伊飡于老與倭人戰沙道,乘風縱火焚舟,賊赴水死盡。
沾解尼師今
三年,夏四月,倭人殺舒弗邯于老。 (中略)
これ以前に于老は奈解尼師今十四年(209年)に太子と記載され、助賁尼師今の先代、奈解尼師今の王子だったことがわかる。231年には大将軍になり、244年に舒弗邯になり、軍事を担当し、245年には北辺を侵犯した高句麗とも戦っている。
この于老には列伝もある。死亡時期は沾解尼師今七年(253年)にずれて、葛耶古(かつなこ)の倭の使節に倭王を奴隷にし、倭王妃を炊事婦にすると冗談を言ったことから倭王の怒りを買い、倭の将軍、于道朱君が攻めて来て、于老を焼き殺したとある。その後、于老の妻は倭の使節を泥酔させた後、焼き殺し、恨みを晴らした。倭は怒って金城を包囲したが勝てずに帰ったとある。
この于老は日本書紀の一説にも新羅王の宇流助富利智干(ウルソホリチカ)として登場する。
氣長足姬尊 神功皇后 足仲彥天皇 仲哀天皇九年最初の一(説)は仲哀天皇崩御後、男装をした神功皇后が新羅を討ち、宇流助富利智干は頭を地に付けて朝貢を願い出たとある。一説は前半、日本側の記述が多く、日本側に残った記録と考えれる。また、仲哀天皇九年は200年にあたるので新羅本紀と年代は一致していない。
一云、足仲彥天皇、居筑紫橿日宮。 (中略) 是夜天皇忽病發以崩之。然後、皇后隨神教而祭、則皇后爲男束裝征新羅、時神留導之、由是隨船浪之遠及于新羅國中。於是、新羅王宇流助富利智干、參迎跪之、取王船卽叩頭曰「臣自今以後、於日本國所居神御子、爲內官家、無絶朝貢。」
一云、禽獲新羅王、詣于海邊、拔王臏筋、令匍匐石上、俄而斬之埋沙中。則留一人、爲新羅宰而還之。然後、新羅王妻、不知埋夫屍之地、獨有誘宰之情、乃誂宰曰「汝、當令識埋王屍之處、必敦報之。且吾爲汝妻。」於是宰信誘言、密告埋屍之處、則王妻與國人、共議之殺宰、更出王屍葬於他處。乃時取宰屍、埋于王墓土底、以舉王櫬、窆其上曰「尊卑次第、固當如此。」於是天皇聞之、重發震忿、大起軍衆、欲頓滅新羅。是以、軍船滿海而詣之、是時新羅國人悉懼、不知所如、則相集共議之、殺王妻以謝罪。
次の一(説)は新羅王を殺し、砂浜に埋めた。一人の使節を残して、帰還した。新羅王妃は使節を誘惑して、王の埋められた場所を吐かせて殺した。何故か神功皇后ではなく、天皇がこれを聞いて怒って、新羅を攻めて、恐れた新羅の国人が王妃を殺した。と、随分、日本側の主観が入った記述になり、矛盾もあるが、三国史記の列伝と似た記述になる。
『日本書紀の謎を解く』(森博達 中公新書1999)によると、日本書紀は雄略記から書かれ、それを書いたのは中国人だという。それ以前は日本人留学僧によって書かれ、漢文としての妥当性は低く、注記も考証的というよりも恣意性が強い。二つ目の一説は新羅本記から引用し、内容を日本寄りに変更した可能性がある。
日本書紀の卑弥呼比定の公式見解は、神功皇后だが、その根拠は新羅本記の年代だった可能性がある。仲哀天皇九年(200年)と年代は一致はしないが、神功皇后の年代を遡らせた一因と考えられる。于老を攻めたのが本当に神功皇后だったかも疑問がある。新羅本記の倭王は明らかに男王だったからだ。最初の一説は神功皇后が男装したとこじつけた内容になっている。最初の一説のこじつけが、神功皇后を新羅本記の年代に結びつけ、神功皇后の卑弥呼比定に結びついたのだ。また、このことが日本書紀の年代を古事記と比べても100年以上歪ませた原因となっている。
新羅本記の年代が信じられるのならば、233年に于老が戦った倭は卑弥呼かその前の男王の邪馬壹国と考えられる。253年(列伝)に于老を殺した倭王は卑弥呼の後の男王だろう。ただ、新羅本記に出てくる卑弥呼は173年に新羅に使いを送ったとあり、この年代は60,70年ずれている。元々新羅本記に卑弥呼の記載があったのか、三国史記の編纂の中で追加されたかにも依る。三国史記の編纂された時代には卑弥呼の年代はわかっていたはずなので、三国史記で追記されたとは考えづらい。ただ、卑弥呼(原文では「卑彌乎」)という名が漢字まで合っているので明らかに魏志倭人伝を読んだ上で書いた記述だ。新羅本記に書かれていた内容としても、新羅に伝わってきた歴史ではなく、歴史書編纂の中で追記したのだろう。実際の時代から記載された時代は離れており、年代は信用出来ない。于老の年代も4世紀中で、4世紀末の女王だった神功皇后より前の出来事だろう。
日本書紀の神功皇后記に記載がある新羅本紀の記事としては、新羅王子、未斯欣の記事がある。
新羅本紀 第三實聖尼師今元年は西暦402年、沾解尼師今から数えると6代後の新羅王だ。この間、新羅王は昔氏から金氏に変わっており、何世代後かは分かりづらい。未斯欣は前王奈勿尼師今の子で、實聖尼師今は奈勿尼師今の父の妹を王妃としているので、未斯欣は王弟と書かれているが、世代としてはその孫の世代。この年に未斯欣は倭に人質に出されたという。
實聖尼師今
元年,三月,與倭國通好,以奈勿王子未斯欣爲質。
訥祇麻立干
二年, (中略) 秋,王弟未斯欣,自倭國逃還。
訥祇麻立干二年は西暦418年にあたり、王は未斯欣の兄にあたる。この年に未斯欣は倭國から逃げ戻った。この事件は朴堤上の列伝にもあり、朴堤上はその際、自らの命を犠牲にして、未斯欣を救出したという。
また、三国史記とは別に三国遺事にもこの事件について記述しており、未斯欣は美海、朴堤上は金堤上と記載される。朴氏は昔氏の前の王族、金氏は昔氏の後の王族なのでいずれかの王族かは不明だが、王族なみの地位を持っていたと考えられる。三国遺事は干支で年代を記載し、人質に出されたのが390年、帰還したのが425年と、三国史記の新羅本紀と年代が異なるがより事件を物語調に詳細を記述している。
氣長足姬尊 神功皇后
五年春三月癸卯朔己酉、新羅王遣汙禮斯伐・毛麻利叱智・富羅母智等朝貢、仍有返先質微叱許智伐旱之情、是以、誂許智伐旱而紿之曰「使者汙禮斯伐・毛麻利叱智等、告臣曰『我王、以坐臣久不還而悉沒妻子爲孥。』冀、蹔還本土知虛實而請焉。」皇太后、則聽之、因以、副葛城襲津彥而遣之。
共到對馬宿于鉏海水門、時新羅使者毛麻利叱智等、竊分船及水手、載微叱旱岐、令逃於新羅。乃造蒭靈、置微叱許智之床、詳爲病者、告襲津彥曰「微叱許智、忽病之將死。」襲津彥、使人令看病者、既知欺而捉新羅使者三人、納檻中以火焚而殺。 (中略)
日本書紀では、未斯欣は微叱許智伐旱(ミシコチホッカン)、朴(金)堤上は毛麻利叱智(モマリシチ)と記載する。朴堤上の列伝の注記で毛末とも言われていたそうなのでほぼ一致する。朴堤上は倭側を騙し、未斯欣を帰還させ、その時、堤上を焼き殺したのは武内宿禰の子で将軍の葛城襲津彦と記載する。こちらは一説ではなく、本紀に記載される。
于老の一説の記述は仲哀天皇の末年で、こちらの本紀の記事は神功皇后五年と、于老の事件から5年しか経っていない。未斯欣が人質に出されてから、新羅本紀で16年、三国遺事で35年経っているのでこれだけでも、于老の事件が神功皇后の時代では無いことがわかる。
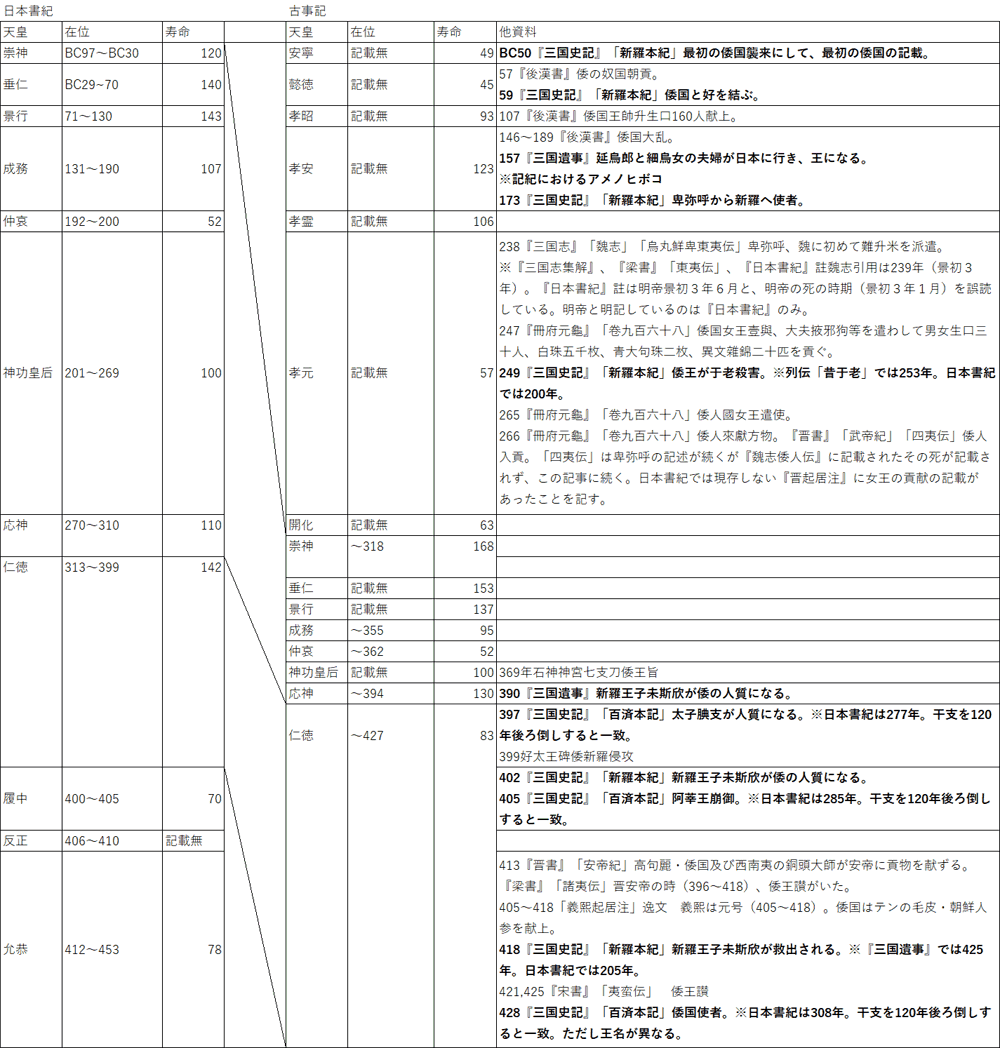
新羅本紀の年代をそのまま信じると于老の事件から1世紀半経っている。ここは新羅本紀の年代がおかしい。新羅王の系図は朴氏、昔氏、金氏が変わり代わり王となり、直列に並べられているが、ここは並列で王が立っていたと考えるべきだろう。
並立した王が直列で並べられた時期は、三国史記の時点か、新羅本紀の時点かというと、于老の二つ目の一説が新羅本紀でそこから卑弥呼比定されたという仮説に立つならば、後者だろう。于老は昔氏の王族だったが、新羅王ではない。いかし、それぞれの一説は新羅王と書いてある。一つ目の一説の新羅王は二書目の新羅王と同一人物なのだろうか。一つ目の一説の宇流助富利智干(ウルソホリチカ)は頭を地に着けて詫びるはめになったが殺されてはいない。一つ目の一説は神功皇后の時代に起きたことで日本側の記録なのかもしれない。
ところが新羅本紀の于老が殺された年代と仲哀天皇九年(200年)は年代が合わない。新羅本紀では卑弥呼が173年に新羅に使節を送ったとあるが、日本書紀の編纂者は魏志倭人伝から卑弥呼の年代(238最初の魏使節派遣、247張政の倭派遣 ※最後に記録される年代)を知っており、卑弥呼の年代が仲哀天皇崩御時に起きた神功皇后の新羅遠征より後の時代ではないと都合が悪い。また、『後漢書』に倭国大乱が桓帝と霊帝の間(146年~189年)にあり、『魏志倭人伝』ではその内乱の後卑弥呼が即位したと記載(※)があるので、仲哀天皇九年(200年)が比定されたのも神功皇后が卑弥呼であるという前提のためだ。この矛盾が本来本紀に記載される一つ目の一説の内容が一説扱いにされた原因と考えられる。そして、二つ目の一説は王族から新羅王に書き換えられ、同一事件を描きならがも内容を日本寄りに改変し、出典が伏せられた理由でもある。
※『後漢書』は宋の時代に范曄が書いたもので、『魏志倭人伝』がある『三国志』が陳寿によって書かれた西晋の時代よりも1世紀半後になる。『後漢書』の倭の記述のほとんどは『魏志倭人伝』の要約と見られ、倭国大乱についても『魏志倭人伝』で内乱が続いた7、80年の男王の時代後、卑弥呼が擁立されたとの記述が出典と考えられる。つまり、実際の倭国大乱の根拠は『魏志倭人伝』となり、桓帝と霊帝の間(146年~189年)というのは范曄の憶測になる。そのような事情を知らず、日本書紀の編者は『後漢書』の記述を年代根拠にしている。
二つ目の一説には新羅王の臏筋(膝の骨と筋)を抜いて、石の上に腹ばいにしたという残酷な記述がある。三国遺事に記述される金堤上は、未斯欣を救出した後、倭王に自分の臣になるならば、重碌を与えると言われても、新羅の犬や豚になっても倭の碌は受け取らないと言い、堤上の足の裏を剥ぎ、オギや葦の上を歩かせても、鉄板の上を歩かせても、屈服しなかったという。新羅本紀の内容の上にこのエピソードも紛れ込んでいる。また、新羅王の妻が復讐した後、倭が攻めてくると新羅の国人に殺されたという記述も、百済本記、日本書紀の本紀にある、百済の王子、腆支が397年倭に人質に出され、405年阿莘王が死ぬと、腆支の弟、訓解が政治を行うが末弟、碟礼が訓解を殺し、王となってしまう。倭兵に守られ腆支が戻ると百済国人が訓解を殺したというエピソードに近い。
堤上のエピソードにせよ、于老の妻のエピソードにせよ、日本側にしてみれば腸が煮えくり返るエピソードで、より残酷に、そして日本側の正当性がある腆支王のエピソードを混ぜることによって、改変されて載せられた一説なのだろう。(R03.09.23追記)
新羅本紀 第一新羅4代国王、昔氏の始祖、脫解尼師今の記述。倭国東北一千里にある、多婆那國(たばなこく)つまり、丹波国、または、但馬国出身という。但馬国は新羅王族系のアメノヒボコが記紀共に伝えられており、古事記によると神功皇后の母の先祖に当たる。北陸の新羅との交流は記紀、三国史記共に伝えるところとなる。九州、対馬を通した交流以外にも、日本海を跨いだ交流があったことを物語ってる。脫解尼師今即位は西暦57年に当たり、この年代が前述の通り、少なくとも1世紀半以上は後ろ倒しになるが、卑弥呼の時代には、魏志倭人伝に邪馬壹国から見て隔絶された地とされる北陸は、新羅と近い関係にあったのだ。そういった関係も含めて、年代の矛盾がありつつも、日本書紀の于老の一説の記述は採用が強行され、神功皇后の卑弥呼比定という公式見解に至ったと考えられる。
脫解尼師今
(中略) 脫解本多婆那國所生也。其國在倭國東北一千里。 (中略)
アメノヒボコについて三国遺事にも記載がある。阿達羅王即位4年(157)に延烏郎と細烏女の夫婦が日本に行き、日本の国人が非常の人だと王にしたと記述がある。ただ、註として日本帝紀つまり日本書紀に王の記載がないので本当の王ではないだろうと記載がある。日本書紀を読んで書いたエピソードの可能性もあるが、あくまで註なので、それ以前の伝承を書き留めた可能性もある。新羅本紀の年代は、並立した王を直列に並べたため、年代がずれている。この後述べる並立を前提にした年代の阿達羅尼師今即位4年は349年になる。卑弥呼の年代ではなく、4世紀半ばに北陸と新羅で通交があったと考えるのも妥当かもしれない。(R03.09.23追記)
参考に新羅王の年代を直列から並列にしてみた。金氏系の王が安定した訥祇麻立干の在位年を基準として、各氏の王を並列にした。王の王妃の父の在位終了からその王の在位が始まるという若干大雑把な仮説になる。
直列の王の在位 ※新羅本紀の在位のまま
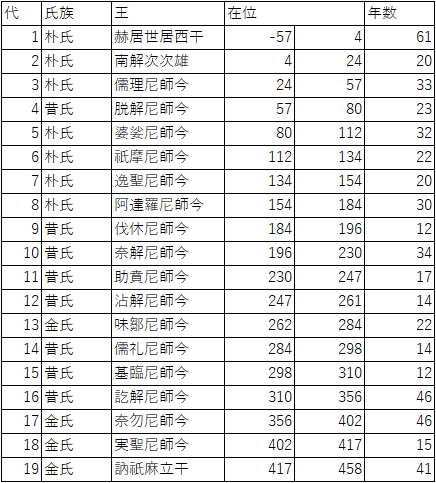
並列の王の在位
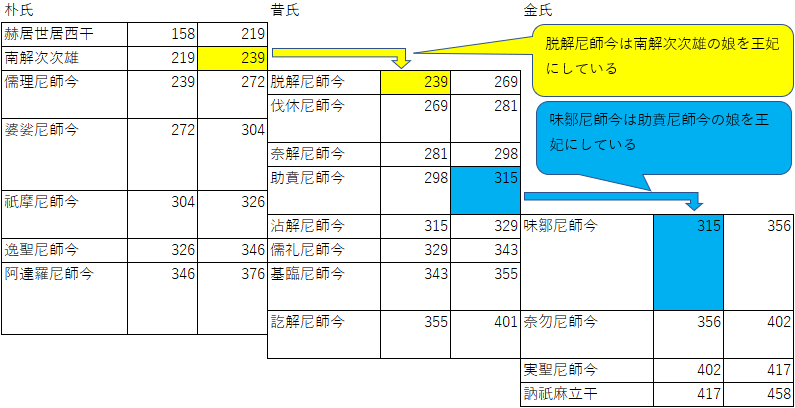
于老が倭と戦って勝利した助賁尼師今四年は301年になり、于老が殺された沾解尼師今三年は317年になる。列伝を信用すると沾解尼師今七年、321年になる。金氏在位のベースは変えていないので未斯欣が人質に取られた年も、解放された年も変わらない。
卑弥呼の使いがあった阿達羅尼師今二十年は365年になってまったく合わない。この記録は新羅本紀編纂時に魏志倭人伝から入れたものだろう。
R03.09.19