僀儞僇偵偍偗傞暥柧偺徴撍偵偮偄偰嘐
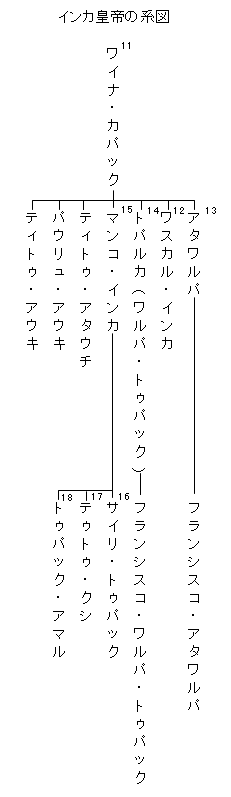 丂亀僀儞僇峜摑婰亁偺挊幰僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偼僗儁僀儞恖僐儞僉僗僞僪乕儖偺僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偲僀儞僇峜懓偺柡偺娫偺巕偩丅亀僀儞僇峜摑婰亁乮亀僀儞僇峜摑婰(巐)亁P.353媿搰怣柧栿丂娾攇暥屔乯偵偍偄偰偦偺僀儞僇峜懓儚儖僷丒僩僁僷僢僋偼杮恖偼儚僀僫丒僇僷僢僋偺孼掜偲偟偰傞丅偩偑丄傾僞儚儖僷偺屻丄傑偩丄僇僴儅儖僇偵偄偨僺僒儘払偑梚棫偟偨僩僷儖僇乮儚儖僷丒僩僁僷僢僋丅僩僁僷僢僋丒儚儖僷側偺偱棯偟偰僩僷儖僇偲傕屇偽傟傞丅乯偲偄偆愢傕偁傞丅僩僷儖僇偼僋僗僐偵摓拝偡傞慜偵巰朣偟偰偟傑偄丄寢嬊僋僗僐偵偄偨儅儞僐丒僀儞僇偑梚棫偝傟傞偙偲偵側傞丅僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偼丄傾僞儚儖僷偲僶儖儀儖僨恄晝偲偺栤摎偱傕傾僞儚儖僷偵尵傢偣偨偙偲偩偑丄侾侾戙峜掗儚僀僫丒僇僷僢僋偼僀儞僇峜掗侾俀恖偑巕懛偺摑帯廔傢傞帪丄堎朚恖偑僀儞僇掗崙傪柵傏偡偺偱斵傜偵廬偆傛偆偵偲梊尵偟偨偲彂偄偰偄傞丅乮亀僀儞僇峜摑婰(巐)亁P.250乯
丂亀僀儞僇峜摑婰亁偺挊幰僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偼僗儁僀儞恖僐儞僉僗僞僪乕儖偺僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偲僀儞僇峜懓偺柡偺娫偺巕偩丅亀僀儞僇峜摑婰亁乮亀僀儞僇峜摑婰(巐)亁P.353媿搰怣柧栿丂娾攇暥屔乯偵偍偄偰偦偺僀儞僇峜懓儚儖僷丒僩僁僷僢僋偼杮恖偼儚僀僫丒僇僷僢僋偺孼掜偲偟偰傞丅偩偑丄傾僞儚儖僷偺屻丄傑偩丄僇僴儅儖僇偵偄偨僺僒儘払偑梚棫偟偨僩僷儖僇乮儚儖僷丒僩僁僷僢僋丅僩僁僷僢僋丒儚儖僷側偺偱棯偟偰僩僷儖僇偲傕屇偽傟傞丅乯偲偄偆愢傕偁傞丅僩僷儖僇偼僋僗僐偵摓拝偡傞慜偵巰朣偟偰偟傑偄丄寢嬊僋僗僐偵偄偨儅儞僐丒僀儞僇偑梚棫偝傟傞偙偲偵側傞丅僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偼丄傾僞儚儖僷偲僶儖儀儖僨恄晝偲偺栤摎偱傕傾僞儚儖僷偵尵傢偣偨偙偲偩偑丄侾侾戙峜掗儚僀僫丒僇僷僢僋偼僀儞僇峜掗侾俀恖偑巕懛偺摑帯廔傢傞帪丄堎朚恖偑僀儞僇掗崙傪柵傏偡偺偱斵傜偵廬偆傛偆偵偲梊尵偟偨偲彂偄偰偄傞丅乮亀僀儞僇峜摑婰(巐)亁P.250乯丂偙傟偑杮摉側傜偽僀儞僇傕傑偨傾僗僥僇偲摨條偵僗儁僀儞恖傪悞傔偰偟傑偄丄帺傜惇暈偝傟偰偄偭偰偟傑偭偨偙偲偲側傞丅亀僀儞僇峜摑婰亁偑彂偐傟偨偺偼僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偑僗儁僀儞偵搉偭偨屻偱丄帺傜偺恎傪庣傞偨傔偵丄偲偙傠偳偙傠偵偙偺梊尵偵偮偄偰彂偄偨偲傕巚傢傟傞丅傑偨丄僩僷儖僇偺懛偲偄偆偙偲偵側傞偲丄傢偞偲儚僀僫丒僇僷僢僋偺孼掜偲曣偺壠宯傪偢傜偟丄僗儁僀儞懁偵偮偄偰偟傑偭偨壠宯側傜偱偼偺揱彸偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅
丂亀僀儞僇峜摑婰亁偱偼僔僄僒丒僨丒儗僆儞偺亀儁儖乕巎亁戞堦晹戞係係復乮亀僀儞僇掗崙抧帍亁憹揷媊榊栿丂娾攇暥屔偲偟偰朚栿偝傟偰偄傞丅P.271偑奩摉売強乯傕堷梡偟偰偦偙偱傕儚僀僫丒僇僷僢僋偺梊尵偵偮偄偰彂偄偰偁傞偲偟偰偄傞丅僔僄僒丒僨丒儗僆儞偼僩儊僶儞僶偱偙偺抧偺桳椡幰偐傜暦偄偨偲偟偰偄傞丅僩儊僶儞僶偼尰嵼偺僄僋傾僪儖丄僽僫乗搰偺搶丄僉乕僩偺撿惣偵偁傝丄傾僞儚儖僷偑懻姤偟偨応強偱傕偁傞丅斵傜偵傛傞偲儚僀僫丒僇僷僢僋偼丄僺僒儘偺戞擇夞墦惇偱僗儁僀儞恖偑傗偭偰棃偨偙偲傪僉乕僩偱偼側偔丄偙偺抧偱抦偭偨偲偟偰偄傞丅偦偟偰斵傜偑嵞傃傗偭偰棃偰墹崙傪帯傔傞傛偆偵側傞偲梊尵偟偨偲偟偰偄傞丅偙傟偼寢壥榑偐傜僗儁僀儞恖偵懳偟偰偍悽帿偱尵偭偨偙偲偐傕偟傟側偄偟丄儚僀僫丒僇僷僢僋偑傑偝偵僺僒儘払偑帩偪崬傫偩昦尨嬠偱巰偵捛偄傗傜傟偨偙偲偱屽偭偨偙偲偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偙偙偼尦乆僇僯儍儖墹崙偺応強偱僀儞僇偑惇暈偟偨応強偱傕偁偭偨丅僔僄僒丒僨丒儗僆儞偑朘傟偨摉帪乮1535-1547擭偺娫乯抝偑彮側偐偭偨偲偄偆丅偦傟偼傾僞儚儖僷攈偲儚僗僇儖攈偺愴偄偺拞偱丄傾僞儚儖僷偑偙偙偺廧柉傪媠嶦偟偨偣偄偲偝傟偰偄傞丅傾僞儚儖僷攈偺崻嫆抧偱偝偊偙偺忬懺側偺偱摉帪偺斀僀儞僇姶忣傪帩偮晹懓偼偐側傝偄偨偲峫偊傜傟傞丅僺僒儘払偼偙偺姶忣傗偦偙偐傜岅傜傟傞揱彸傕棙梡弌棃偨丅僀儞僇丒僈儖僔儔乕僜丒僨丒儔丒儀乕僈偺傛偆偵僗儁僀儞懁偵晅偄偨墹懓傕偦偺揱彸傪僀儞僇偺傕偺偲偟偰棙梡偟丄帺暘偺棫応傪惓摉壔偟偨丅
丂僇僴儅儖僇偵偄偨僺僒儘払偵榖傪栠偡丅僩僷儖僇傪梚棫偟偨偲尵偭偰傕丄僺僒儘偼傾僞儚儖僷傪張孻偟偨偙偲偵傛傝丄彮側偔偲傕傾僞儚儖僷攈偺彨孯偼揋偵夞偟偨丅傾僞儚儖僷偺巕丄屻偵僉儕僗僩嫵夵廆屻丄僪儞丒僼儔儞僔僗僐丒傾僞儚儖僷偲柤忔傞傑偩梒偐偄巕偳傕偼掞峈偵旛偊妋曐偟偰偄偨丅偦傟偱傕丄傾僞儚儖僷偲摨曣孼掜僥傿僩僁丒傾僞僂僠丄僠儍儖僋僠儅偵宲偖彨孯僉僗僉僗偼僺僒儘払傪慱偭偨丅偙傟傑偱僀儞僇懁偺掞峈偑奆柍偩偭偨偑傑偢傾僞儚儖僷攈偲偺愴偄偑巒傑傞偙偲偲側傞丅
丂1933擭9寧丄500恖偺僐儞僉僗僞僪乕儖偼僇僴儅儖僇傪弌敪偟丄僋僗僐傪栚巜偟偨丅偦偺攚屻傪僥傿僩僁丒傾僞僂僠棪偄傞俇愮偑廝偄丄僗儁僀儞恖俉柤傪曔椄偵偟偨丅乮仸乯丂僴僂僴偵摓拝屻偼僄儖僫儞僪丒僜僩60婻偵愭傪掋嶡偝偣偨丅嶳妜抧懷偵偍偄偰僉僗僉僗偺孯悢愮偑僜僩傪廝偭偨丅偦偺嵺丄俆恖偑巰朣丄偦偺懠晧彎幰偑弌偨丅傾儖儅僌儘偺晹戉偑崌棳偡傞偲堦扷偼揚戅偟偨偑丄偦偺屻丄僺僒儘杮懱偑崌棳偟僋僗僐傪栚巜偡摴掱偱僉僗僉僗偼僺僒儘払傪廝偄丄攏偑悢摢巰偵丄曕暫偵晧彎幰偑弌偨丅僠儍儖僋僠儅偑張孻偝傟偨偺偼偙偺帪婜偵側傞丅傑偨丄僩僷儖僇傕僴儖僴偱巰傫偱偟傑偭偨丅儁僪儘丒僺僒儘偵傛傞偲僩僷儖僇偼僠儍儖僋僠儅偵撆嶦偝傟偨偲彂偄偰偁傞丅乮亀戝峲奀帪戙憄彂丂戞嘦婜丂儁儖乕墹崙巎亁憹揷慞榊栿丂娾攇彂揦丂P.94乯丂僩僷儖僇偼儚僗僇儖攈偱傾僞儚儖僷傪嫲傟偰偄偰丄僠儍儖僋僠儅偼僩僷儖僇梚棫偵斀懳偟偰偄偨傛偆偩丅傕偪傠傫丄僠儍儖僋僠儅傪張孻偡傞偨傔偺偱偭偪忋偘偱偁傞壜擻惈傕崅偄偑丄儚僗僇儖攈偲傾僞儚儖僷攈偺妋幏傪偙偙偱傕擿偐偝偣傞丅
仸僥傿僩僁丒傾僞僂僠Titu(Tito) Atauchi偼亀僀儞僇峜摑婰亁戞擇晹乮朚栿柍偟乯偺弌揥偲側傞丅偨偩丄儚僀僫丒僇僷僢僋偺巕偵偮偄偰傕彂偄偰偁傞戞堦晹偵偼婰嵹偑柍偄丅僱僢僩傪尒傞偲愭廧柉偲僗儁僀儞恖偺崿寣愰嫵巘僽儔僗o儗乕儔偺亀惣梞偺楌巎亁乮朚栿柍偟丅僽儔僗o儗乕儔偵偮偄偰偼梞彂Sabine Hyland亀The Jesuits and the Incas亁, Michigan, 2003偵彂偐傟偰偄傞偲偺偙偲丅巹偼枹撉丅乯偵婰嵹偑偁傝丄帺恎偺暦偒庢傝偱偼側偔丄偦偙偐傜偺堷梡偲偺愢傕偁傞丅傑偨僗儁僀儞岅僒僀僩傪尒傞偲傾僞儚儖僷攈丄儚僗僇儖攈偲偺愴偄偱儚僗僇儖攈偵偮偄偰愴偄丄巰朣偟偨摨柤恖暔偑偍傝丄傾僞儚儖僷偺巰屻丄僗儁僀儞偲愴偭偨偲偝傟傞偙偺僥傿僩僁丒傾僞僂僠偺懚嵼傪斲掕偡傞愢傕偁傞傛偆偩丅偟偐偟丄僗儁僀儞懁偺懝奞偵偮偄偰偼僗儁僀儞恖偵偲偭偰晄柤梍側偙偲偱偁偭偨偺偱婰榐偼傢偞偲尭傜偝傟偰偄傞丅偦偺懠丄儚僀僫丒僇僷僢僋偺巕偲偟偰僥傿僩僁丒傾僂僉Titu Auqui偲偄偆恖暔傕偄傞偑丄亀僀儞僇峜摑婰亁偵傛傞偲傑偩偙偺帪偼梒彮偱暿恖暔偲側傞丅庒偄撪偵巰朣偟偨偲偝傟傞丅
丂僺僒儘払偑僋僗僐偵擖傞偵摉偭偰傾僞儚儖僷攈偼掞峈偟偨傕偺偺丄僋僗僐偺斀傾僞儚儖僷攈偼傾僞儚儖僷傪張孻偟偨僗儁僀儞僐儞僉僗僞僪乕儖傪娊寎偟偰偟傑偭偰偄偨丅1933擭11寧15擔僺僒儘偼僋僗僐偵擖忛偟偨丅偦偺20擔屻偵僀儞僇丒儅儞僐傪僀儞僇峜掗偵梚棫偟偨丅
丂傾僞儚儖僷偺張孻屻丄傾僞儚儖僷攈偩偭偨媽僉乕僩墹崙乮尰嵼偺僄僋傾僪儖乯偱偼偦偺僀儞僇憤撀僜儁丒僜僷儚丄彨孯儖儈僯傽僂僀偺撈棫忬懺偵偁偭偨丅偪傚偆偳偦偺崰怴偨側僐儞僉僗僞僪乕儖丄傾儖僶儔乕僪偑500偺曕暫偲250偺婻暫丄儅儎恖偺壸扴偓悢愮恖傪棪偄偰傗偭偰棃傞搑忋偵偁偭偨丅僺僒儘摍500柤偑僋僗僐偵偄傞拞丄僒儞丒儈僎儖偵巆偭偰偄偨100柤傪棪偄傞儀僫儖僇僒乕儖偺晹戉偼師乆偵傗偭偰棃傞僗儁僀儞恖偱200偺曕暫丄80偺婻暫傪曇惉弌棃傞傎偳偵側偭偰偄偨丅傾儖僶儔乕僪偵僉乕僩傪庢傜傟側偄偨傔偵丄愭偵僉乕僩傪扗偭偰偍偔昁梫偑偁傞偲帺屓寛抐偟丄1534擭2寧偵僉乕僩傪峌傔傞偨傔偵弌敪偟偨丅偦偙偵偼斀僀儞僇偺晹懓傕崌棳偟偨丅僀儞僇憤撀僜儁丒僜僷儚偼5000偺暫偱寎偊丄婻暫梡偵棊偲偟寠傪孈偭偨傝傕偟偨偑尒攋傜傟偰偟傑偄丄僉乕僩傪庤曻偟偨嫇嬪丄曔傑偭偰偟傑偄丄嵿曮偺嵼張傪揻偐偣傞偨傔偺崏栤傪庴偗偰丄揻偐側偐偭偨偨傔壩鄑傝偵偝傟偰張孻偝傟偰偟傑偭偨丅傾儖僶儔乕僪偵偮偄偰偼僺僒儘偑傾儖儅僌儘傪憲傝丄傾儖僶儔乕僪偵暫戉傪崅抣偱攧傜偣傞偙偲偱崌堄偟丄傾儖僶儔乕僪傪婣傜偣偨丅
丂堦曽丄僉僗僉僗偼僺僒儘払偑嫀偭偨僴僂僴傪慱偭偨丅僴僂僴偵偼40婻偺婻暫偟偐偄側偐偭偨偑丄愭廧柉俁愮傕枴曽偵壛傢偭偰偄偨丅僉僗僉僗偼杮恖偑棪偄傞愮恖偲暿摥戉俈愮偵暘偐傟偰峌寕偟偨偑戝偒側懝奞傪弌偟偰揚戅偟偨丅僉僗僉僗偼僴僂僴偐傜杒惣僇僴儅儖僇曽柺偵揚戅偟偨丅偦偙偱僥傿僩僁丒傾僞僂僠偲崌棳偡傞丅僺僒儘偼懻姤偟偨偽偐傝偺儅儞僐丒僀儞僇偺暫係愮偲嫟偵僉僗僉僗傪捛偭偨丅僉僗僉僗偼僉乕僩偵岦偐偭偰揚戅偟偨丅偪傚偆偳偦偺帪傗偭偰棃偰偄偨傾儖僶儔乕僪偺孯偲憳嬾偟偰偟傑偭偨丅傑偨丄僺僒儘偑傾儖僶儔乕僪偵憲偭偨傾儖儅僌儘偺孯傕傗偭偰棃偰偟傑偄丄嫴傒寕偪偵側偭偰偟傑偭偨丅僉僗僉僗偼娾嶳偺揤慠偺梫奞偱杊塹偟丄揚戅偺帪娫傪壱偄偩丅偙偺愴偄偵偍偄偰傾儖儅僌儘偺孯偼戝懝奞傪弌偟偨丅僗儁僀儞懁偵偲偭偰晄柤梍側帠懺側偺偱婰榐偑柍偔丄偦偺婯柾偼晄柧偩丅偦偺榖傪暦偄偰僺僒儘偑棊抇偟偨偲偄偆偐傜憡摉側婯柾偲峫偊傟傞丅僉僗僉僗偼偦偺傑傑僉乕僩傪栚巜偟偨偑丄僉乕僩偼婛偵儀僫儖僇僒乕儖偵傛偭偰娮棊偟偰偄偨丅僉僗僉僗偺孯惃偼曗媼傕愨偨傟丄搳崀傪慽偊傞晹壓偵僉僗僉僗偼嶦偝傟偰偟傑偆丅僥傿僩僁丒傾僞僂僠偼偦偺慜偵搳崀偟偨丅
丂偙偙傑偱偼僉僗僉僗傕丄僜儁丒僜僷儚丄儖儈僯傽僂僀傕丄僞儚儞僥傿儞僗乕儐偺拞偱傕懐孯埖偄偩偭偨丅僋僗僐偺僀儞僇峜懓傕傾僞儚儖僷傪峜埵偺櫽扗幰偲偟偰尒偰偄偨偟丄傾僞儚儖僷偑幚岠巟攝偡傞僄僋傾僪儖廃曈抧堟偵偍偄偰傕丄偁偔傑偱晲椡偵傛傞嫲晐巟攝偱丄傾僞儚儖僷攈偵斀敪傪帩偪丄僗儁僀儞懁偵晅偔晹懓偑懡偐偭偨丅偦偺偨傔丄僜儁丒僜僷儚丄儖儈僯傽僂僀偼偁偭偗側偔攋傟偰偄傞丅偨偩丄僉僗僉僗偼僋僗僐廃曈偱偼斀姶傪帩偨傟偰偄偨偨傔丄僗儁僀儞懁偵戝偟偨懝奞傪弌偣側偐偭偨偑丄僉乕僩曽柺偺嶳妜抧懷偱偼怴偨偵傗偭偰棃偨傾儖僶儔乕僪偲傾儖儅僌儘偺嫴傒寕偪傪嬺傜偭偨偵傕娭傢傜偢丄慞愴偟偰偄傞丅僀儞僇峜掗偺張孻偲偄偆巆媠峴堊偵傕娭傢傜偢丄偙偙傑偱愭廧柉傪棙梡弌棃偨偺偵偼丄儚僗僇儖攈丄傾僞儚儖僷攈偺憇愨側愴偄偺屻偲偄偆僞僀儈儞僌偺椙偝偑偁偭偨丅
丂偙偺帪偺僺僒儘偺嫻拞偼偳偺傛偆側傕偺偩偭偨偩傠偆丅橒橲偺僀儞僇峜掗傪偨偰偨偑丄墿嬥偵庢傝溸偐傟偰師乆偵傗偭偰偔傞僗儁僀儞偺楺恖払偵丄僀儞僇偺墿嬥傪暘偗梌偊偨丅僺僒儘杮恖偲偟偰偼帺暘偺尃椡偺婎斦偱偁傞僗儁僀儞恖偺梸朷傕枮偨偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偐偭偨丅偨偩丄摑帯偲偟偰偼僗儁僀儞恖払偩偗偱偼柍棟側偺偱僀儞僇偺摑帯傕偁傞掱搙堷偒宲偄偱峴偐側偗傟偽側傜側偐偭偨丅偨偩丄僗儁僀儞偺摑帯傪偳偙傑偱擖傟偰偄偔偐偵偮偄偰偼愊嬌揑側婥帩偪偵側傟側偐偭偨偩傠偆丅僺僒儘偼僗儁僀儞偵栠偭偨帪偵搳崠偝傟偨丅僗儁僀儞偱偼偦偺傛偆側晄埨掕側抧埵偩偭偨丅傓偟傠丄擔杮偱偼尵偊偽丄挬掛偐傜惇埼戝彨孯偺偍杗晅偒傪傕傜偊丄嫗搒偐傜棧傟偨姍憅偵枊晎傪奐偄偨尮棅挬偺傛偆偵丄僗儁僀儞偺憤撀偲偄偆偍杗晅偒傪傕傜偄偮偮丄僗儁僀儞偐傜墦偔棧傟偨偙偺抧偵帺暘傗僐儞僉僗僞僪乕儖傪椞庡偲偡傞敿偽撈棫忬懺傪曐偪偨偐偭偨偺偱偼側偄偐偲傕憐憸弌棃傞丅僗儁僀儞杮崙偼憤撀偲偄偆偍杗晅偒傪梌偊偮偮婜懸傕墖彆傕朢偟偐偭偨丅偙偙傑偱悢昐恖偱傗偭偰偙傟偨偺偼僗儁僀儞杮崙傛傝傕帺暘払偺椡偩偲巚偭偰偄偨偩傠偆丅
丂僺僒儘偼僋僗僐傪弌偰丄惣晹増娸偺儕儅偵嫆揰傪寶愝偟偨丅偙偺曽偑師乆傗偭偰偔傞僗儁僀儞恖傪庴偗擖傟傗偡偔丄僀儞僇峜掗偺尃椡傪僺僒儘偺曽偵弴師堏偟偰峴偔偙偲偵偪傚偆偳偄偄偲峫偊偨偐傜偩傠偆丅偪傚偆偳偦偺崰丄僗儁僀儞杮崙偵憲偭偰偄偨僺僒儘偺孼掜僄儖僫儞僪丒僺僒儘偑婣偭偰偒偨丅嘊偱弎傋偨捠傝丄僺僒儘偑憤撀偲側傞椞搚偑600儅僀儖偐傜偝傜偵200儅僀儖奼挘偝傟丄傾儖儅僌儘偼偦偺偝傜偵撿600儅僀儖偺憤撀偲側傞偲偄偆傾儖儅僌儘偵晄棙側僗儁僀儞墹幒偺嵦寛偩偭偨丅擇恖偺摑帯幰偩偲屻乆潌傔傞偐傜偲偄偆棟桼偩偑僗儁僀儞墹幒偼偦偺屻偺惌嶔傪尒偰傕傢偞偲斵傜僐儞僉僗僞僪乕儖傪暘楐偝偣傛偆偲偟偰偨偺偱偼偲峫偊偰偟傑偆丅傕偆堦恖斵傜偺暘楐傪朷傓幰偑偄偨丅僀儞僇峜掗儅儞僐丒僀儞僇偩丅
丂傾儖僶儔乕僪偺楢傟偰偒偨暫払偼僋僗僐偵擖傞偲愭廧柉傪恖娫埖偄偣偢丄棯扗傪峴偭偨丅傑偨丄帥堾偼塜幧偵曄偊傜傟丄墹偺媨揳偼暫幧偵曄偊傜傟偨丅懢梲恄偵巇偊傞張彈払傗僀儞僇峜懓偺彈惈払偑僗儁僀儞恖払偺惈偺塧怘偵側偭偨丅僺僒儘偐傜僋僗僐巗偺寶愝傪擟偝傟偨僺僒儘偺掜僼傽儞丒僺僒儘偼儅儞僐丒僀儞僇偺巓枀傪扗偄丄僗儁僀儞偺婻巑偼儅儞僐丒僀儞僇偺岪傪斊偟偨丅斵傜僐儞僉僗僞僪乕儖偼丄僉儕僗僩嫵偺棫応偐傜僀儞僇偺恖乆偺惈偺廗姷傪僉儕僗僩嫵偺壙抣娤偺尦丄埆廗偲寛傔偮偗丄夵廆偺昁梫惈傪弎傋傞偑丄偦傟傛傝傕偼傞偐偵栰斬側朶椡傪僀儞僇偺彈惈偵嫮偄偰偄偨丅尰嵼偱傕嫵夛偵偍偗傞惈媠懸偼懡偄丅惈偵婯棩傪媮傔傞椣棟偼搢嶖偟偨惈傪惗傓丅偦偺壥偰偟側偄梸朷偼嬥嬧傪棯扗偡傞偩偗偱偼朞偒偨傜偢丄惈朶椡偺帺屓惓摉壔偵岦偐偆丅擔杮偺弔夋偺傛偆偵嵟弶偐傜辔弼側傕偺偲偟偰昤偄偨奊偲堎側傝丄惣梞偺奊夋偵偼寍弍偲徧偟偰棁懱傗巆崜側僔乕儞傪屻傠傔偨偝偺寚曅傕側偔昤偔傕偺偑懡偄丅恖奿偺懜廳傪慽偊傞偺偼憡庤偺恖奿偵懳偟偰偱偼側偔丄帺暘偺梸朷傪憡庤偵桳柍傪尵傢偝偢墴偟晅偗傞偨傔偩丅憡庤偺恖奿傪柍帇偟丄帺暘偺暔嵎偟偩偗傪墴偟晅偗丄帺暘偺怣嬄懄偪帺暘偺梸朷偺偍傕偪傖偵偡傞丅偦偺墭偄梸朷偑擣傔傜傟側偄偲偡傞側傜偽嶦滳偵慽偊傞丅愭偢抐嵾偟側偗傟偽側傜側偄偺偼偦偺傛偆側帺暘偺梸朷偺帺屓惓摉壔側偺偵傕娭傢傜偢丄抐嵾偼帺暘偑棟夝弌棃側偄丄偁傞偄偼棟夝偡傞搘椡傪峴偭偰偄側偄傕偺偵懳偟偰峴偆偲偄偆偁偒傟壥偰偨懺搙傪偲傝懕偗傞丅場壥墳曬丄偦偺傛偆側幰偵偼昁偢曬偄偑棃傞丅帺慠傗恄傪堌傟偱偼側偔丄帺暘偺僆僫僯乕偺帺屓惓摉壔偺摴嬶偵曄偊偨幰偵偼丄偦偺幚懺偺嵎偺撧棊偵撍偒棊偲偝傟傞帪偑昁偢棃傞丅偦傟傪揤鎛偲屇傇丅偙偙偵棃偰暥柧偺徴撍偼奜偐傜偩偗偱側偔丄撪偐傜偺徴撍偺儅僌儅傪惗傒弌偟丄徴撍偼暒揰傪寎偊傛偆偲偟偰偄偨丅
H25.09.05