インカにおける文明の衝突について⑤
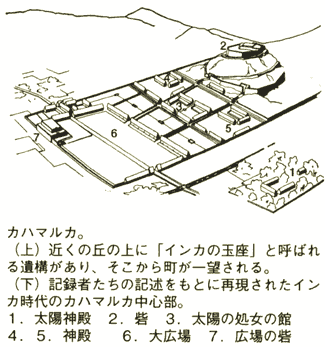 ピサロの従兄弟ペドロ・ピサロの『ピルー王国の発見と征服』(『大航海時代叢書 第Ⅱ期 ペルー王国史』増田善郎訳 岩波書店で邦訳されている。)によるとアタワルパはその日午後まで酒を飲んでいた。それほど相手を舐めてかかっていたとも言える。あるいは宗教的な高揚の中でスペイン人を迎えようとしたのか。それから3時間かけて行列を伴い、日没頃カハマルカの広場にやってきたという。アタワルパの輿に続いて、チンチャの酋長も輿に担がれて続いた。カハマルカの広場は壁で囲われていて、後の行列が入れるように詰めながら入っていった。そして広場隅々を満たしたという。かといって八万の全軍が広場に入れるほどの広さがあった訳ではない。フランシスコ・デ・ヘレスによると4千人以上いたという。残り7万6千の軍は皇帝を広場に残し、ここで分断されてしかも、逃げられないように密集してしまった。だが、広場にはスペイン人達の姿は無かった。家臣によるとスペイン人は恐れの余り建物から出てこれないとの報告だった。すると、バルベルデという修道士と一人の兵士、通訳がやってきたという。そこでキリスト教をアタワルパ達に教えるために来たこと、その教えがこの聖書に書いてあること、それを通して友になることを要請すると伝えた。ペドロ・ピサロによるとさらにスペイン王への帰服も求めたとしている。アタワルパは初めて見るとその本と文字を興味深く思い、見せてくれと頼んだ。ただ開け方がわからず放り投げて、ピサロ達の行中の悪行を責めた。すると修道士はそれを先住民のせいにした。アタワルパは盗んだ全てを返還するまでここで動かないと言った。『銃・病原菌・鉄』の中で強調されるのはフランシスコ・デ・ヘレスが伝える聖書の開け方がわからず、赤面してムキになるアタワルパの姿だが、ここで行われたのは両者の大義の問い合いだった。アタワルパにとっては物理的な暴力による戦いよりもここでの戦いはそういう戦いと認識していた。『ペルー征服』になるとブレスコットらしいオーバーな表現と感動要素を交え以下のような問答を描いている。
ピサロの従兄弟ペドロ・ピサロの『ピルー王国の発見と征服』(『大航海時代叢書 第Ⅱ期 ペルー王国史』増田善郎訳 岩波書店で邦訳されている。)によるとアタワルパはその日午後まで酒を飲んでいた。それほど相手を舐めてかかっていたとも言える。あるいは宗教的な高揚の中でスペイン人を迎えようとしたのか。それから3時間かけて行列を伴い、日没頃カハマルカの広場にやってきたという。アタワルパの輿に続いて、チンチャの酋長も輿に担がれて続いた。カハマルカの広場は壁で囲われていて、後の行列が入れるように詰めながら入っていった。そして広場隅々を満たしたという。かといって八万の全軍が広場に入れるほどの広さがあった訳ではない。フランシスコ・デ・ヘレスによると4千人以上いたという。残り7万6千の軍は皇帝を広場に残し、ここで分断されてしかも、逃げられないように密集してしまった。だが、広場にはスペイン人達の姿は無かった。家臣によるとスペイン人は恐れの余り建物から出てこれないとの報告だった。すると、バルベルデという修道士と一人の兵士、通訳がやってきたという。そこでキリスト教をアタワルパ達に教えるために来たこと、その教えがこの聖書に書いてあること、それを通して友になることを要請すると伝えた。ペドロ・ピサロによるとさらにスペイン王への帰服も求めたとしている。アタワルパは初めて見るとその本と文字を興味深く思い、見せてくれと頼んだ。ただ開け方がわからず放り投げて、ピサロ達の行中の悪行を責めた。すると修道士はそれを先住民のせいにした。アタワルパは盗んだ全てを返還するまでここで動かないと言った。『銃・病原菌・鉄』の中で強調されるのはフランシスコ・デ・ヘレスが伝える聖書の開け方がわからず、赤面してムキになるアタワルパの姿だが、ここで行われたのは両者の大義の問い合いだった。アタワルパにとっては物理的な暴力による戦いよりもここでの戦いはそういう戦いと認識していた。『ペルー征服』になるとブレスコットらしいオーバーな表現と感動要素を交え以下のような問答を描いている。バルベルデ「(キリストの贖罪、磔刑、昇天を話した後)その際、救世主は使徒ペドロに地上の代理権を託し、この代理権は使徒の継承者である立派な賢人達に伝えられ、彼らは法王なる称号の下に地上のすべての君主達を支配した。最近即位した法王の一人が世界で最も強大な君主たるスペイン皇帝に西半球の原住民を征服し、改宗させることを委託した。皇帝の将軍たるピサロこの重要な使命を実行するために今や到着したのである。拙僧の言を快く受入れ、汝の誤れる信仰を誓って絶ち、救済を望み得る唯一の教えたる上述のキリストの教えを信仰せよ。また、皇帝チャールス(※カルロスの英語読み)五世の貢納者たることを認めよ。しかる時皇帝は彼を臣下として援助し、保護し給うであろう。」
アタワルパ「予は何人にも貢納せず。予は地上のいかなる君主より偉大である。汝の皇帝は偉大な君主であろう。海を越えて遙々その臣下を送ったことより見て予はその真なるを疑わぬ。予は彼を悦んで兄弟として遇しよう。汝が話せる法王とやらは狂人であろう。自己の所有に非ざる国をいかにして分かち与え得ようぞ。予の信仰に関しては予は変更する意思を持たぬ。汝の神は、汝の言うごとくんば、彼が造れるその人間により殺された。しかし予の神は」と沈みつつある太陽を指差し、「今なお大空に輝き、子孫をみそなわせた給う。」
『ペルー征服(上)』 P.290-291
ここまで突っ込んだ話がされたがどうか、されてもそこまで伝わったかどうかは不明である。(※) だが、このブレスコットの物言いは、この時とこれから続く世界観と世界観の衝突を象徴するものとなっている。
※この場面の問答は後代にカハマルカの事件が描かれる際、象徴的な場面で様々な言い回しと創作で描かれる場面となっている。ワイナ・カパックの姪とスペイン人の間に生まれたガルシラーソ・デ・ベーガの『インカ皇統記』第二部(邦訳無し。『インカ皇統記(四)』のあとがきに記載。)においてもアタワルパ嫌いらしく、スペイン人がこれまでやってきた破壊行為はインカの予言が伝えるパチャマカマックとしてやってきて、帝国を滅ぼすために来たのだろうと、アタワルパに自虐的に言わせている。
しかし、インカの太陽神と皇帝が一極支配なのに対し、ヨーロッパには世界観を司るローマ教皇に並んで、実効支配を行う皇帝がいる。ヨーロッパにおいてはその2重構造から1極支配者の大義の問いあいでは片がつかない。むしろその大義はその後の暴力のためにある。バルベルデはピサロのいる広場中央宿舎に戻り、聖書が侮辱されたことを伝えた。
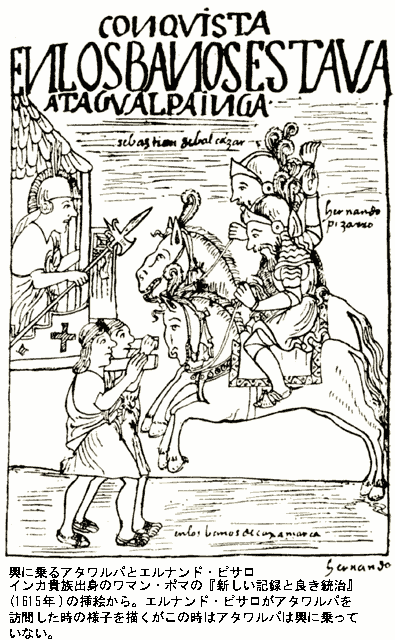 すると持ってきた軽大砲が発射され、ラッパが鳴り響いた。2隊の騎馬隊が両翼から飛び出し、馬に取り付けられた鈴を鳴らした。情報としては得ていた大砲だが、実際のその発射音、そしてこれらの音響効果はインカ側に大混乱を起こさせた。そこに中央からはピサロが率いる歩兵が突撃し殺戮を始めた。アタワルパの行列は広場の壁を押し倒して逃げた。騎兵はその速さで逃げるインカの人々をその先まで追いかけ殺戮した。中央の歩兵は輿に乗ったチンチャの酋長を殺してしまった。アタワルパの輿は輿を担ぐインカの人々が殺されても殺されても次から次へと担いでいった。インカの兵士の士気は低かったわけではないが、圧倒的な太陽神インカ皇帝への命がけの盲従でもあった。アタワルパも輿に乗っている場合では無かったが、絶対的な信仰がこの非戦術的な光景を作り出してしまった。ついに輿はひっくり返されアタワルパは捕まってしまった。
すると持ってきた軽大砲が発射され、ラッパが鳴り響いた。2隊の騎馬隊が両翼から飛び出し、馬に取り付けられた鈴を鳴らした。情報としては得ていた大砲だが、実際のその発射音、そしてこれらの音響効果はインカ側に大混乱を起こさせた。そこに中央からはピサロが率いる歩兵が突撃し殺戮を始めた。アタワルパの行列は広場の壁を押し倒して逃げた。騎兵はその速さで逃げるインカの人々をその先まで追いかけ殺戮した。中央の歩兵は輿に乗ったチンチャの酋長を殺してしまった。アタワルパの輿は輿を担ぐインカの人々が殺されても殺されても次から次へと担いでいった。インカの兵士の士気は低かったわけではないが、圧倒的な太陽神インカ皇帝への命がけの盲従でもあった。アタワルパも輿に乗っている場合では無かったが、絶対的な信仰がこの非戦術的な光景を作り出してしまった。ついに輿はひっくり返されアタワルパは捕まってしまった。アタワルパは虜囚の辱めを受ける中でも侍女に囲われて、皇帝の威厳を守った態度をしていた。このことが今後もアタワルパ派の好戦的な将軍達の抵抗を出来ないようにさせていた。4万人を指揮していたアタワルパ派の将軍チャルクチマはピサロの指示でアタワルパの命令としてやってくるように言われ、同じく捕らえられてしまう。1万人を残し、残り3万人を郷里に帰し武装解除した。また、ピサロの兄弟エルナンド・ピサロに50騎を付けて、また、チャルクチマを同行させ、先にクスコに行かせた。道中で神殿を冒涜し、クスコでは太陽神殿から金を剥ぎ取ったが皇帝やチャルクチマを人質に取られたインカの人々は無抵抗だった。
アタワルパは狡猾な人間と記されている。部屋で金で満たすからそれを条件に釈放を願い出た有名な話は、策略からだったとも言える。アタワルパの心配はこの場面においてさえワスカルに再び皇位を奪われることにあった。ワスカルはアタワルパのインカの黄金を売り渡すアタワルパの行為に怒りを覚えていた。この時期にワスカルが殺されるという事件が起きており、ペドロ・ピサロはそれはアタワルパがチャルクチマを通して指示したこととしている。ワスカルの死に偽りのものと思われる涙を流している。
1533年2月中旬(『ペルー征服』から。4月14日説もあり)、アルマグロが84名の騎兵、150名の歩兵とともにカハマルカに到達した。ピサロとしてはアタワルパとの黄金の契約がその後も続くと、当時険悪になっていたアルマグロが金を受け取れなくなると懸念してた。ちょうどその頃アタワルパが指示し、スペイン人を皆殺しにするために近くに大軍の兵が集まっているという噂が流れていた。この噂はピサロが流した可能性もある。(※)アタワルパと仲の良かったエルナンド・ソトに偵察に行かせている。しかし、その様子はまったく無かった。クスコから戻ってきた同じくアタワルパと仲が良かったエルナンド・ピサロにはスペインに行かせた。こうすることでアタワルパ処刑の機運を高め、スペイン人コンキスタドール600名内部の問題を解決しようとしていた。
※ペドロ・ピサロの『ピルー王国の発見と征服』によると現地人通訳がアタワルパの妻の一人を手に入れたくてピサロにその噂を吹き込んだとしている。
アタワルパもピサロもお互いの世界の内部事情で狡猾に動いていた。ピサロは優れた戦術眼を持っていたが、戦略眼は現場の叩き上げらしく内部事情に流されやすい。イギリス、フランス、オランダという後期の帝国主義者達は、植民地化する地域の内部矛盾をそのまま残し、それを利用することによって統治を行った。しかし、ピサロは内部事情でアタワルパを処刑してしまった。ピサロはアルマグロ残党に自宅で殺される際、警備の兵がいなかったとされる。このように奇襲が得意な人物は奇襲に弱い。
アタワルパもまた、ワイナ・カパックと共に従軍しキート王国周辺を征服し、対ワスカル戦では電撃的な勝利を収めており、それなりの戦術眼を持っていたようだ。しかし、カハマルカで捕虜となり、8万人の軍勢のうち7000人を失っている。(※) アタワルパもまた奇襲には弱かったのだろう。中国では官途の戦いで曹操は奇襲で袁紹に勝ったが、赤壁の戦いで惨敗した。日本におけては桶狭間の戦いでは2万5千(こちらも4万人説もあり。)の今川義元が、3千の織田信長に、自らの首を上げられ、しかも3000人の死者を出している。崩れた大軍は大量の死者を出す。これは少人数ならば撤退は楽だが、整列せず各自がバラバラになって大軍が逃げる場合、パイプが詰まるように撤退が困難になるためと考えれる。インカ側を大混乱に陥れた大砲についても、インカ皇帝、インカ貴族以外にその情報が行き渡っていたかも疑わしい。自分や少数の人間で企みを行う指導者は相手側の虚を突くことは得意だが、現場に権限を渡さないため、現場は敵の奇襲に備えられない。
※カハマルカでの死者の数については8000人説(トルヒリョ)、7000人説(ルイス・デ・アルセ)、6-7000人説(無名コンキスタドール)、2000人説(フランシスコ・デ・ヘレス)がある。アタワルパが率いた軍の数8万人については、フランシスコ・デ・ヘレスが記述する、ピサロが一人のキリスト教徒に500人のインディオがいると記載したことによる。ただ、その前にエルナンド・ピサロの訪問時に3万人以上としている。ペドロ・ピサロはピサロがカハマルカ到着時、アタワルパが4万人以上率いていると報告を受けたとしている。これを『銃・病原菌・鉄』では、エルナンド・ピサロは「インディオの数を4万と見積もったが、それは我々を勇気付けるための嘘で実際は8万人以上いる」と記述している。
第3次遠征でニカラグアから途中参加したベナルカサル率いた30名の兵士の中にミゲル・デ・エステーテという人物がいてその著書『ベルー情報』によると囚われのアタワルパはスペイン人達を宦官にするつもりだったと語ったという。ピサロに負けずアタワルパも相当残忍な人物のようだ。第1回の遠征からピサロに同行しているフランシスコ・ロベス・デ・ヘレスの著書『ペルー征服正史』で「頭のするどい人間特有の機知に富んだ発言をしていたが、これを聞いたスペイン人たちは野蛮人でもこれほど利口な人間がいるのかと驚いているのである」と記している。(柴田秀藤『インカ帝国の虚像と実像』(講談社選書メチエ 1998 1章の4、2章の1参照。) 宿舎にいるうちに焼き払って殺さずにアタワルパ自らわざわざ会いに行ったのは宦官にするために生け捕るという目的があったようだ。アタワルパからすればスペイン人も物珍しい野蛮人なのだ。特にヘレスの記述からは『銃・病原菌・鉄』で描かれる初めてヨーロッパ文明に接する上での滑稽さや囚われの身となりスペイン人達のなすがままに利用される哀れさもない。また、ブレスコットやその原典となったガルシラーソ・デ・ベーガが描く劇的で神話的な面もない。アタワルパを殺害した理由はその存在感にスペイン人が恐れをなした、あるいは利用しきれない人物と捉えたからとも思われる。ブレスコットには西洋優位の偏見もあったが、基本的にはガルシラーソ・デ・ベーガが描いたインカ帝国とスペイン人コンキスタドールの神話に乗っかっている。 H27.10.18追記
ヘレスの著書は邦訳もされている。(フランシスコ・デ・ヘレス ペドロ・サンチョ『インカ帝国遠征記』増田義郎訳 中公文庫2003 P.129) しかし、ここはアタワルパを殺す際に言いかがりをつけている場面であり、アタワルパに罪を着せるため、わざとそのような言い方をしているようにも読める。ピサロはコルテスのアステカ侵略を前提にインカ侵略を慎重に進めていたと思われるが、どこまでがピサロの頭の中にあったものなのか疑問である。むしろ、ピサロ達がインカ内部の内ゲバに巻き込まれていったという面も大きいと考えられる。
1533年7月28日にアタワルパはカハマルカの大広場で処刑された。最初は火あぶりの刑が言い渡されたが、キリスト教に改宗すれば、絞首刑にすると言われた。インカでは皇帝の遺骸は保存することになっているので、アタワルパはやむを得ずキリスト教に改宗した。インカの将軍チャルクチマも処刑された。チャルクチマはキリスト教への改宗を拒み、火あぶりの刑となった。キリスト教の大義は結果を左右するものでは無かったが、残忍さの中で露出した。中国において、北朝、金、元、清と異民族王朝による漢民族に対する支配が行われたが、王朝は常に中華王朝だった。ペルーにおいてはスペイン人の制服はインカ王朝になることは無かった。これはキリスト教による先住民信仰の破壊と改宗による。これが一神教による絶対神信仰が成せるものだった。ピサロ達はインカの文化遺産であった金の工芸品を、偶像崇拝の排除を大義に、兵士の取り分やスペイン本国への送付で分配出来るように、インカの鍛冶屋に強いて金の延べ棒に変えさせた。
このアタワルパの最後は、日本で言えば源平合戦で勝利した源頼朝が東の海から来航したペリーに殺されてしまったようなものだった。暴力による敵側絶対君主の殺害。ピサロが第3回遠征で少人数でたいした被害もなく出来たこと、『銃・病原菌・鉄』のようにカハマルカの事件をもって文明の衝突はスペイン側の勝利が決まった瞬間として想像されることが多い。しかし、実際はこの暴虐をもって長い戦いの口火が切られた。そしてその後ろにはスペイン本国というより巨大な悪にインカだけではなく、ピサロ等コンキスタンドールも追い詰められていくことになる。コンキスタンドール達は死ぬ間際になって自分達の悪行を悔いたという。この事件は現代に至るまでスペイン十字軍とその帝国主義の不当性を証明する事件なのだ。そしてインカという一極中央集権体制のこの脆さ、これは戦後日本のテーマにも繋がっている。これはこの文明の衝突を描く上のでの最後のテーマになる。
H25.08.31